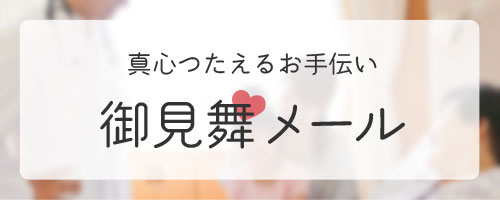透析センター
看護方針
透析治療は医師、看護師、臨床工学技士、栄養科など様々な職種がただ一つ「患者さんのために」連携をとりチームワーク良く治療を行っております。
透析治療は何十年も続く治療です。「友達の家に遊びに行ってくる」「少し出かけてくる」感覚で何事もなく通院できることが理想と考え透析看護を行っております。
看護体制
子育て世代の方は勿論、幅広い年齢層の方々がやり甲斐を持ち生涯看護師として働いていく事ができる職場としてライフワークバランスに配慮した体制つくりを行っています。日本腎不全看護学会認定の指導士や、腎臓病指導士を持つ看護師、糖尿病重症予防(フットケア)研修を修了した看護師を配置するとともに資格取得や学会発表、看護研究にも積極的に取り組み良質な透析看護が提供できるようにスキルアップに努めています。
設備
透析監視装置:透析センター内40台、入院病棟対応2台(オンラインHDF23台)


超音波診断装置:1台
更衣室:男性1室、女性1室(写真は女子更衣室)


円滑な腎代替療法への導入 —血液透析療法・腹膜透析療法・腎移植—
各種治療にもかかわらず腎機能が低下し、末期腎不全となった場合には、腎代替療法を行うことになります。腎代替療法には透析療法(血液透析および腹膜透析)と腎移植(献腎移植および生体腎移植)があります。透析療法への導入に際しては、個人の生活や仕事の様式を重視し、納得の行く形で血液透析・腹膜透析の透析方法を選択していただけるように心掛けています。当院では維持透析療法として血液透析117名、腹膜透析32名(2021年8月現在)の患者さんの診療を行っています。
血液透析用バスキュラーアクセス(シャント、人工血管など)の作製はクリニカルパスを使用し、導入時の入院期間の短縮に努めています。また、積極的にハイパフォーマンス膜を使用して透析をしており、透析療法の重大な合併症のひとつである透析アミロイドーシスの予防、進展阻止などを目標に血液濾過透析も行っています。また、バスキュラーアクセス不良に対しては年間100例前後(腎内70件・血外30件)に経皮的血管拡張術(PTA)を行っています。
腹膜透析では段階的導入法(SMAP法)によるカテーテル手術を取り入れ、極力入院期間を短く(最短5日程度)しています。導入前に時間を設けることで、患者さんの不安への対応や腹膜透析の練習なども十分に行うことが出来ます。毎週月・火曜日の午後、金曜の午前に腹膜透析外来で対応しております。 移植療法については患者さんに積極的に啓発して推進に努めています。献腎移植を希望される方については臓器移植ネットワークへの登録をお勧めしています。実際の移植については新潟大学附属病院等を紹介して移植を行ってもらっています。
特殊療法 業績数
| 平成27年度(2015年度) | 平成28年度(2016年度) | 平成29年度(2017年度) | 平成30年度(2018年度) | 平成31年度(2019年度) | 令和2年度(2020年度) | 令和3年度(2021年度) | |
| CHDF(例数) | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| 腹水濃縮再静注(回数) | 53 | 47 | 37 | 36 | 36 | 81 | 48 |
| 血漿交換(例数) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 血漿・血液吸着(例数)* | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| PMX* | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lcap, Gcap | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LDL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 免疫吸着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ビリルビン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*8月現在
| 腎臓内科医師 | 3名 |
| 臨床工学技士 | 6名 |
| 看護師 | 23名 |
| 看護介護補助者 | 2名 |
COVID-19(新型コロナウイルス)拡大により、火・木・土曜日の午後透析(3:00~開始)は対象患者を制限して透析を実施中。