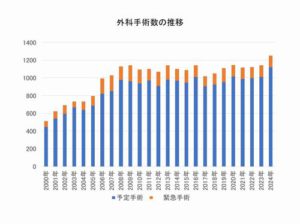-
-
診療科案内
-
-
部門案内
-
地域連携支援部
-
創立90周年記念誌
巻頭言
90周年誌作成にあたり
長岡中央綜合病院 病院長 矢尻洋一
皆様のお陰を持ちまして、長岡中央綜合病院は令和7年(2025年)に創立90周年を迎えることができました。感謝申し上げます。
昭和10年(1935年)「すべての人が必要な医療を漏れなく享受できる世の中でありたい」、その思いのもと、大勢の貧しい農家の皆さんが苦難の末に設立した中越医療組合病院が当院の始まりです。
平成27年(2015年)今から10年前、80周年にあたり全408ページに及ぶ「八十年のあゆみ」を発刊しました。あれから10年が経過しました。この間にコロナ感染症により、医療機関はもとより、社会全体が今までにない経験をしました。そして、コロナ禍後、全国的な医療経営危機の中、新潟県厚生連においても現在、経営再建中であります。今日、人口減少・少子高齢化、地方過疎、低迷する経済状況の中で、地域医療にとっては厳しい医療情勢ですが、当院の設立当時の思いを受け継ぎ、病院の理念である「良質で心温まる医療を提供する」を実践し、その理想を実現できるように願っています。
「八十年のあゆみ」巻頭で吉川明病院長は100周年を視野に置きながら80周年記念誌を作成したと書かれています。今回100年までの中間で、記憶の新しいうちに記録に残すこととし、90周年誌を作成しました。来るべき100年(2035年)記念誌に繫がるものとなります。厳しい財務状況に加え、より多くの方に閲覧していただけるように紙媒体でなく、デジタルでホームページからご覧いただくようにしました。
最後にお忙しい中、本誌に寄稿いただいた多くの方々と編集に尽力した職員に心から感謝申し上げます。
診療科
—消化器内科
消化器内科、内視鏡室について
副院長 高村昌昭
今回の執筆にあたり、参考資料として当院80周年の際に当時副院長をされていた富所隆名誉院長が執筆された寄稿文を頂いた。1960年代からの当科の歴史が詳細に記されているので参照されたい。当科の歴史は内視鏡室の歴史そのものであり、以下まとめて直近10年ほどのことを記す。
1.当科の人員構成と人事異動の概要(表は敬称略)
|
2016年 |
吉川 明 |
富所 隆 |
佐藤 知巳 |
渡辺 庄司 |
福原 康夫 |
佐藤 明人 |
岡 宏充 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
堂森 浩二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
小林 由夏 |
渡辺 庄司 |
福原 康夫 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
|
岡 宏充 |
堂森 浩二 |
茂木 聡子 |
|
|
|
|
|
|
2018年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
小林 由夏 |
渡辺 庄司 |
福原 康夫 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
|
岡 宏充 |
小川 光平 |
後藤 諒 |
夏井 一輝 |
野澤 良祐 |
|
|
|
|
2019年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
佐藤 祐一 |
小林 由夏 |
福原 康夫 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
|
岡 宏充 |
小川 光平 |
後藤 諒 |
前田悠一郎 |
|
|
|
|
|
2020年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
佐藤 祐一 |
小林 由夏 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
|
中野応央樹 |
堀 亜洲 |
五十嵐崇徳 |
|
|
|
|
|
|
2021年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
髙村 昌昭 |
小林 由夏 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
|
中野応央樹 |
杉田 萌乃 |
後藤 収 |
宮崎 遥可 |
|
|
|
|
|
2022年 |
富所 隆 |
吉川 明 |
髙村 昌昭 |
小林 由夏 |
佐藤 明人 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
|
中野応央樹 |
杉田 萌乃 |
宮崎 遥可 |
吉田耕太郎 |
|
|
|
|
|
2023年 |
髙村 昌昭 |
小林 由夏 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
中野応央樹 |
丹羽 佑輔 |
永山 逸夫 |
|
佐藤 千紘 |
吉田耕太郎 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年 |
髙村 昌昭 |
小林 由夏 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
松井 徹 |
中野応央樹 |
丹羽 佑輔 |
|
永山 逸夫 |
佐藤 千紘 |
堀江 篤 |
|
|
|
|
|
|
2025年 |
髙村 昌昭 |
小林 由夏 |
本田 穣 |
岡 宏充 |
松井 徹 |
中野応央樹 |
丹羽 佑輔 |
|
佐藤 千紘 |
堀江 篤 |
米山 匠 |
|
|
|
|
当科はこの10年間、常時8~12名の医師体制で推移しており、上級医の専門分野および上級医と若手医師のバランスが良好な、安定した診療体制を維持している。
以下に、主な人事異動を時系列で記載する。
2017年には吉川明院長が名誉院長に就任され、富所隆副院長が新たに院長に就任された。同年、佐藤知巳先生が上越総合病院へ副院長として異動され、また腫瘍内科・消化器内科の専門である小林由夏先生が赴任され、消化器悪性腫瘍に対する化学療法分野の診療体制が強化された。
2019年には佐藤祐一先生が副院長として着任され、渡辺庄司先生が小千谷総合病院の消化器内科部長として異動された。
2020年には、消化器疾患全般にわたり指導的立場にあった福原康夫先生が開業され、同年には中野応央樹先生が新たに着任された。
2021年には佐藤祐一副院長が新潟医療センターへ副院長として異動され、その後任として髙村が副院長に着任した。
2023年には佐藤明人先生が開業された。先生は長年にわたり、指導的立場としてESDやその切除標本の病理学的な見方を伝授していただいた。現在もご多忙の診療の合間をぬってESDの指導に来ていただいている。
2024年に松井徹先生が赴任された。先生は胆膵領域が専門で同領域の診療体制が強化された。
また、これまでに当院で研修を行い、当科を選択した研修医は11名にのぼり、現在は新潟県内各地で活躍している。当科の教育体制は、若手医師への丁寧な指導と段階的なスキルアップを重視し、内視鏡手技やカンファレンスへの参加、さらには学会発表や論文作成を通じて、実践的な力を養える環境を整えてきた。
今後も、専門性と総合力を兼ね備えた診療科として地域医療に貢献するとともに、次世代を担う若手医師が成長できる場としての役割を果たしていきたい。
2.当科の主な検査・治療件数
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
上部内視鏡 |
9,510 |
9,307 |
9,512 |
8,978 |
8,723 |
9,139 |
8,926 |
8,972 |
8,579 |
|
食道ESD |
19 |
32 |
31 |
31 |
34 |
24 |
36 |
31 |
24 |
|
胃ESD |
208 |
179 |
182 |
147 |
159 |
181 |
205 |
205 |
191 |
|
食道ステント留置術 |
14 |
9 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
6 |
|
胃・十二指腸ステント留置術 |
25 |
26 |
17 |
14 |
9 |
23 |
17 |
17 |
20 |
|
食道静脈瘤治療 |
21 |
42 |
24 |
13 |
28 |
45 |
39 |
26 |
44 |
|
PEG (内視鏡的胃瘻造設術) |
22 |
24 |
27 |
14 |
17 |
25 |
27 |
22 |
22 |
|
LECS (腹腔鏡・内視鏡合同手術) |
2 |
7 |
4 |
1 |
4 |
0 |
1 |
3 |
4 |
|
下部内視鏡 |
3,542 |
3,338 |
3,344 |
3,354 |
3,165 |
3,245 |
3,125 |
3,152 |
3,306 |
|
ポリペクトミー |
277 |
397 |
477 |
560 |
683 |
744 |
859 |
778 |
907 |
|
大腸EMR |
694 |
638 |
662 |
626 |
543 |
602 |
499 |
543 |
466 |
|
大腸ESD |
45 |
38 |
54 |
45 |
56 |
52 |
54 |
61 |
59 |
|
大腸ステント留置術 |
30 |
27 |
29 |
25 |
31 |
18 |
25 |
35 |
42 |
|
小腸内視鏡 |
– |
7 |
22 |
28 |
32 |
36 |
46 |
57 |
67 |
|
ERCP |
466 |
437 |
449 |
379 |
406 |
388 |
456 |
441 |
473 |
|
EUS |
252 |
290 |
268 |
220 |
253 |
218 |
262 |
250 |
292 |
|
EUS-FNA |
57 |
83 |
97 |
95 |
130 |
103 |
131 |
113 |
120 |
|
EUS-BD (胆管ドレナージ) |
7 |
16 |
11 |
8 |
9 |
10 |
14 |
11 |
13 |
|
EUS-CD (嚢胞ドレナージ) |
2 |
4 |
5 |
2 |
6 |
6 |
3 |
10 |
8 |
|
PTGBD/PTCD |
54 |
43 |
45 |
45 |
36 |
67 |
72 |
73 |
86 |
|
エコー下肝生検 |
15 |
18 |
12 |
13 |
9 |
12 |
27 |
28 |
39 |
|
TACE (肝動脈化学塞栓療法) |
101 |
105 |
93 |
59 |
42 |
50 |
36 |
45 |
51 |
|
RFA (ラジオ波焼灼療法) |
4 |
10 |
13 |
2 |
4 |
9 |
3 |
6 |
11 |
当科の検査・治療件数に影響を及ぼした出来事は二つあり、新型コロナウイルス感染症 (2020年~)と消化器内科輪番制の変更 (2023年4月~) である。コロナ禍により一時的に検査・治療件数が減少したものもあるが、大部分はコロナ禍前の水準にまで回復している。一方、小腸内視鏡や肝胆膵領域の検査(EUS-FNA、エコー下肝生検)および治療(PTGBD/PTCD)は増加傾向にある。
2024年4月からは医師の働き方改革が始まり、通常勤務時間内での効率的な検査・治療運用が求められるようになった。これに対応するため、当科では検査・治療に対応可能なX線透視装置を導入し、放射線科や看護部と連携の上、並列での検査・治療運用に着手した。
今後、超高齢化社会の進展に伴い、当科には安全性と確実性を確保しつつ、より高度で低侵襲な医療の提供が求められる。多職種と連携・協力しながら質の高い医療を地域に提供するとともに、次世代を担う若手消化器内科医の育成にも努めていきたい。
呼吸器内科
血液内科
創立90周年を迎え、血液内科のこの10年
血液内科 坪井康介
当院は1935年に開院し、今年2025年7月に創立90周年を迎えました。80周年誌に当科の歴史について記載がありますので、その後約10年間について記載します。
2013年3月までは、小林政先生、岸賢治先生の2人体制で診療を行いました。同年4月に私(坪井康介)が当院に就職、3人体制で診療を行いました。2014年4月からは小林政先生が小千谷総合病院に異動(同病院副院長)となり、2人体制となりました。2015年8月からは武藤祥宏先生(総合診療科兼務)が加わり、再び3人体制となりました。その後2022年3月に岸賢治先生が、2024年5月に武藤祥宏先生が辞められ、以降2025年9月現在まで、1人で診療を行っています。
診療内容に関しては以前から変わりなく、移植医療を除く血液疾患全般を診ています。新規血液疾患患者は年間約100-120例程度です。そのうち、急性白血病は10例程度、慢性骨髄性白血病は5例程度、骨髄異形成症候群は20例程度、多発性骨髄腫は15-20例程度です。特に悪性リンパ腫は増加傾向にあり、2021年度は年間90例程度まで増えましたが、平均すると70例程度です。
入院患者数は2020年度もっとも増加していましたが、コロナ禍以降やや減少しています。
それでも入院患者数は年間のべ200例を超えています。入院患者数が多いのは、悪性リンパ腫の患者さんが増えた影響と思われます。悪性リンパ腫の多くの治療は2コース目以降外来でも可能な治療ですが、遠方の方は短期入院で治療を継続しています。もともと急性白血病などの血液疾患の抗癌剤治療は長期入院を必要としていましたが、近年急性骨髄性白血病の一部の患者においては短期入院でも可能な治療法が確立したり、支持療法が充実したりしたため、長期入院を回避できるようになりました。これらのおかげで平均入院期間は以前に比べ短縮傾向となりました。患者さんにおいても、大変喜ばしいことと思います。
当院100周年にむけて
近年血液疾患患者は増加傾向にあると思います。しかし当院はもちろん、県内の病院で余裕をもって診療ができているところは少ないように思います。県内の血液内科医の高齢化、血液内科医不足により、当院が100周年を迎えるころ、ここ中越地区では混乱が生じているかもしれません。当院血液内科のことだけを言えば、一日も早く血液内科医を確保し、チーム医療ができる日が来ることを願っています。今もそうですが、100周年を迎え、さらにその先も、長岡赤十字病院と協力し合い、長岡地域の血液疾患患者の治療が滞りなく進むことを願っています。
腎臓内科
糖尿病センター
糖尿病センター
糖尿病センター 八幡和明
毎年大学からの若手ドクターと一緒に糖尿病の臨床を行っている。ありがたいことに当院にやってくる先生は皆まじめで今どきのナイスガイ、ナイスレディで患者さんやスタッフ、そして他の診療科の先生にも大変喜ばれている。みんな優秀なので学問や研究面では、もはや私が教えることもほとんどないくらいだ。せっかく一緒に勉強するならと、チーム医療の大切さと診療の際の心の持ちようを伝えるようにしている。忙しい外来診療の中では教える時間が少ないので、入院症例を通してチーム治療の進め方や考え方などを指導するようにしている。
病棟では毎朝8時半から医師団、糖尿病特定認定看護師、薬剤師、事務クラークがそろって入院症例のカンファランスをしている。個々の症例の特徴を簡単にプレゼンしつつ血糖の推移や検査結果などを参考にしながら治療を進めている。特に24時間の血糖変動(フリースタイルリブレ)を読みときながら適切なインスリンや薬剤の選択ができることは大きな進歩といえる。毎朝のカンファは大変と思うかもしれないが、一日一日の変化を確認しておくことは互いのスタッフの関わりに役に立つと信じて続けている。そして週に1回はチームの全員が集まってカンファランスを行う。一例一例じっくりと1週間を振り返りつつ、メンバーの持っている情報や意見を出し合いながらチームの方針を確認していくようにしている。その中で特に大切にしているのは糖尿病を持つ人の思いを聴くことで、PAID(Problem Areas In Diabetes Survey(PAID)糖尿病問題領域質問票)を用いた分析や、それぞれの関わりの中から見えてきたその人自身の心の変化に注目している。糖尿病の治療をする中で抱えている不安や悩みはどんなことがあるか問題点を明らかにし、その人の価値観や希望を聞きながら治療の選択肢を示し、みんなで協力して治療方針を決めていくSDM(Shared decision Making 共有意思決定)を取り入れるようにしている。私たちの支援で治療に取り組む姿勢が変わることができることを願って日々の指導に取り組んでいる。
患者指導としては先代の中島先生、鈴木先生がはじめられた糖尿病教室をリニューアルしながらずっと続けてきたこの教室では単なる知識の講習にとどまらず、自分の身体や指導媒体に触れながら学ぶ体験型の学習を行っていて、医師だけでなく栄養士や薬剤師、看護師がチーム医療の一環として担当している。参加者の笑顔や拍手のなかに理解が深まったことが実感できる。のべ1000回になるので記念のイベントをやろうと計画していたが、コロナ禍になって現在まだ延期している。そのほかにもいろいろの患者指導を行ってきた。糖尿病食を患者と医師が一緒に食べる会食会、外食ツアー、コンビニ探検、調理体験などを行ってきた。また検査技師が病棟にきて実施した様々な検査の意味や結果の説明も行っている。そのような様々な関わりを通して若手医師やスタッフとチーム医療の面白さをともに学んでいる。一緒に活動してくれるスタッフには心から感謝している。こういったチームでの活動は病院内外でも評価され、各地から見学に来る人も多く、薬学部や栄養学校などの学生も実習に来てくれるのは励みになる。
さて近年は糖尿病を取り巻く環境も大きく変化してきた。入院してくる患者は教育入院というよりは、高血糖緊急症、合併症の悪化、手術前の血糖マネージメント目的の患者が増えてきた。その一方他科に入院している糖尿病患者に対する血糖マネージメントの比率が増加している。急性期疾患や手術を受ける患者に適切な血糖マネージメントを行うことで、原疾患の治療成績の向上や合併症の予防、入院期間の短縮などが得られ病院全体の診療の質の向上に寄与していると自負している。しかし短期間の入院中に血糖を整えることが主眼になっていて、各診療科にまたがる大勢の患者のデータを電子カルテで見ながらインスリンの調整をしていくことが多い。問題のある患者はベッドサイドに伺うのだが、短時間の診療では患者の立場になって考える余裕があまりないことは、若手医師の糖尿病診療に対する理解や意欲を歪ませていないか一抹の不安がある。
糖尿病診療のやりがいは長期にわたっての全人的なフォローにあると思って自分なりの診療を続けてきた。しかし急性期病院では短いサイクルでの紹介・逆紹介の病診連携が求められており、糖尿病診療のやりがいや面白さをどうやって若手医師に示せるのか悩んでいる。学会や研究会などでともに学んだ若手医師やスタッフが他の病院に異動して活躍している姿を見聞きするとうれしくなってくる。これからも大きな糖尿病チームとして広く貢献していきたいと思っている。
最後に当院の「糖尿病センターの掟」を掲げて終わることにしよう。皆さんのお役に立つことを願っている。
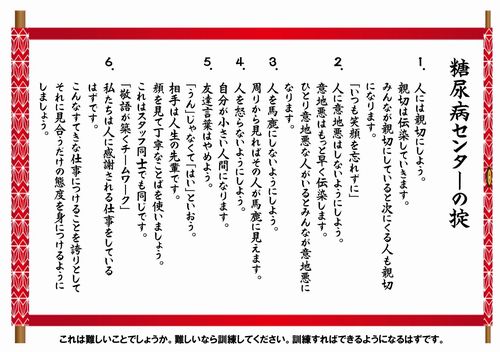
糖尿病センターの掟
神経内科
神経内科の歩み
神経内科 渡邊浩之
長岡中央綜合病院の神経内科は新潟大学脳研究所神経内科からの外来出張医により始まり、1986年4月から長嶋勝が初めての常勤医となった。長岡の3病院のなかでは長岡赤十字病院に次いで2番目の開設となる。1992年3月長嶋が退職したあと新潟大学から大橋寿彦が半年間応援に来ていて、1992年11月に1978年卒の大野司が赴任した。その後は長い間一人医長時代が続いた。
2009年から1987年卒の渡邊浩之が加わり常勤二人体制となった。この頃から医師の間でも働き方改革の芽生えが見られ、新潟大学神経内科においても医局人事での一人医長はできるだけ避けるようになっていった。2005年から急性期脳梗塞のtPA療法が可能となり、2015年頃には血管内治療のエビデンスが確立した。いずれも発症後すぐの対応が必要となる。そのため急性期脳梗塞の診療が、地域の急性期拠点病院で集約的に24時間体制で行われるようになり、急性期拠点病院でのマンパワーの充実が求められた。2018年度から2005年卒の石川正典が加わり常勤3名となり、2020年4月から2010年卒の柳村文寛が加わった。ただ大野は嘱託となり、外来中心の診療となっている。2022年4月から2008年卒の酒井直子が非常勤で加わった。2022年8月には柳村が異動となり、代わりに1992年卒の鈴木隆が加わった。2024年2月から石川は異動となり、代わりに2014年卒の井上佳奈が勤務している。従って、現在常勤は渡邊・鈴木・井上の3名で、非常勤が大野・酒井の2名の計5名となっている。
スタッフ全員が神経内科専門医で、渡邊・鈴木・大野は神経内科指導医でもある。他に渡邊は日本内科学会総合内科専門医、認知症専門医・指導医、大野は日本内科学会総合内科専門医、リハビリテーション学会認定臨床医、酒井は日本内科学会認定医、日本頭痛学会専門医、井上は日本内科学会認定医、日本リハビリテーション学会認定臨床医である。当院は日本神経学会教育施設 日本認知症学会専門医教育施設、日本脳卒中学会一次脳卒中センターに認定されている。
臨床検討会は院内では神経内科検討会(新患紹介と難しい症例の検討)を平日の朝に連日行っており、脳外科との合同検討会とリハビリカンファレンスは各々週1回施行している。
院外で長岡地区の画像臨床カンファレンスを月1回、中越神経内科懇話会(中越地区神経内科臨床報告会)を年2回程度開催している。
近年の診療実績としては、2019から2023年の年間の新規入院患者数は200人台前半から後半へ増加傾向で、疾患別では脳梗塞が一番多く、他にてんかん等の発作性疾患、髄膜炎等の中枢感染症、多発性硬化症等の中枢性脱髄疾患、筋萎縮性多発性硬化症(ALS)・パーキンソン病などの変性疾患、ギラン・バレー症候群等の免疫性末梢神経障害などがある。
長岡中央訪問看護ステーションとともに主にALSの在宅人工呼吸器患者の訪問診療・レスパイト目的の入院も行っている。
2019年度からは入院患者のせん妄対策としてせん妄・認知症ケアチーム(DST)を渡邊と認知症看護認定看護師である栗和田を中心として立ち上げ、全病棟の看護師と共同して活動している。同チームで2020年からはせん妄予防を目的とした、せん妄ハイリスク患者のスクリーニング及びケアを開始した。また2024年からは身体拘束最小化の取り組みを開始し、拘束率は減少してきている。
2025年10月からは頭痛学会専門医の酒井医師により頭痛外来が開設される予定である。
神経内科は2017年9月の日本神経学会理事会にて「脳神経内科」と標榜診療科名を変更した。これにより心療内科や精神科との差別化を行い、脳・神経の疾患を内科的専門知識と技術をもって診療する診療科として、また「脳神経外科」の内科側のカウンターパートであるとの位置づけを明確にした。
近年の高齢化に伴い認知症、てんかん、脳血管障害等の対象患者は増加し、また急性期脳梗塞に対するtPAや血管内治療の進歩、神経免疫疾患の治療の進歩、アルツハイマー病の疾患修飾薬の上市など脳神経内科を巡る環境は変化している。頭痛、めまい、しびれなどのcommon diseaseへの対応も必要である。当院では限られた医療資源を有効活用するため、病診・病病連携を緊密にしながら対応していきたいと考えている。
腫瘍内科
腫瘍内科
腫瘍内科 小林由夏
腫瘍内科は2017年に新設となった当院では一番新しい専門分野です。90年の歴史の中では末尾のほんの数行に過ぎませんが、少し当科の紹介をさせていただきます。
一般的に腫瘍内科(Medical Oncology)は、がんの内科的治療、特に薬物療法に関わる科です。腫瘍内科の歴史は、抗がん剤の開発とその臨床応用の進展と密接に関連しています。
近年の腫瘍内科学の台頭は著しく、特に過去20年間で大きな進展がありました 。1997年に米国FDAがB細胞性非ホジキンリンパ腫を対象に抗CD20抗体リツキシマブを承認したことが一つの大きな節目です。その後、がん分子標的治療薬の開発が進み、2023年7月までに日米で161剤が承認されました 。その後も毎月のように新薬の情報が送られてきており、トラスツズマブ–デルクステカン、ベルズチファン、チスレリズマブ、一番最近の薬物療法ニュースで上がっている横文字に翻弄されて、アップデートが大変です。
免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の導入や、遺伝子異常に基づいたがん分子標的治療、がんゲノム医療の臨床導入も新しい展開だと考えられます。当個人的にチャンピオン症例として紹介している患者様は、本来の抗がん剤治療であれば予後が限られていたところ、アメリカ在住で研究員の息子さんの助言で、国立がんセンター東病院のがんゲノム検査を受検し、当時の新規薬剤の適応症例と診断されました。その後転移病巣はすべて消失し、薬物療法を終了して5年目の現在も完治の状態を継続しています。がんセンターからも何度も問い合わせがくるレア症例ですが、このようなケースはこれまで経験したことがなく、間違いなくがん治療のネクストステージであると思われます。
腫瘍内科自体の歴史を紐解くと、大学病院の腫瘍内科は東北大学が黎明期を担ってきました。初代教授の斉藤達雄先生は、抗がん剤の臨床的評価を行うための効果判定基準を設け、新規抗がん剤の評価を行いました 。その後、1978年に涌井昭先生が二代目教授に就任し、抗がん剤の作用機序の基礎的研究に力を注ぎました 。1991年には三代目教授の金丸龍之介先生が就任し、分子生物学の発展に伴い、がんの生物学的研究が進められました 。四代目教授の石岡千加史先生は臨床腫瘍学会の理事長をお勤めになり、2024年には川上尚人が五代目教授に就任し、新規治療や薬剤の開発に積極的に取り組んでいる名門中の名門で、当院はゲノム連携病院として新潟大学を拠点病院に活動していますが、実はさらに中核拠点病院である東北大学腫瘍内科とも関連しています。
一方、日本では腫瘍内科を設置している一般病院がまだ限られています。全国で約400以上の「がん診療連携拠点病院」が指定されていますが、そのすべてに腫瘍内科があるわけではありません。
日本臨床腫瘍学会が認定する「がん薬物療法専門医」は全国で約1600人(2022年時点)とされており、地域によって偏りがあります。東京都には250人、大阪府には163人いる一方で、新潟は26名、大学とがんセンターを中心に在籍しています。
そんな中、2名の薬物療法専門医で腫瘍内科を拓くことができたのは、前富所隆院長、現矢尻洋一院長をはじめ多くの方々のお力添えによるものです。当科スタート後の独自の活動として、薬物療法同意書、免疫チェックポイント阻害薬治療同意書、入院時には終末期治療の希望の同意書を導入しました。外来では新規治療開始症例、抗がん剤漏出例、薬剤によるinfusion reactionが疑われた全例に関して、週に1回多職種で行うカンファレンスを始めました。開始時は医師と通院治療センター看護師のみでしたが、現在は薬剤師、栄養科が加わり、外来薬剤指導に関する依頼書の作成などを行い、時にはケースに関して個別に対応をすることもあります。また病棟でも、先のメンバーに加えてリハビリ科、ケースワーカー、退院支援看護師の参加するカンファレンスを継続しています。各部門に学生さんなどが来られた時には参加していただくことも多いです。症例の個別把握や顔が見える関係でよりよい協力体制を作るチーム医療を実践することが、腫瘍内科としての役割ではないかと思っています。
2023年12月からは、ゲノム診療も開始しました。この時も医療支援部、病歴管理室、病理部門、看護部門、医事課、検査室に大変お世話になりました。現在も着実に出検件数を増やしており、2025年にはゲノム検査の結果が臨床試験に結び付くことを期待して、CONNECTトライアルという患者紹介システムの臨床試験にも参加しました。がん薬物療法のもう1本の柱になっていくものと考えています。
まだまだ未熟な科ではありますが、100年史でも「まだ存続しています」とご報告できるよう、がん治療の進歩とともに歩む精進を続けたいと思います。

外来多職種カンファレンスの様子

病棟多職種カンファレンス
循環器内科
循環器内科の10年間を振り返る
循環器内科 中村裕一
2010年代後半の循環器内科は、常勤医3人態勢が軌道に乗り、安定期を迎えた時期であった。さらに新潟大学循環器内科のご配慮で2014年からは出張をいただくこともでき、マンパワー的に余裕が出てきた時期であった。
この時期の大きなイベントに、2018年度のシネアンギオ装置のリニューアルがあげられる。2005年の新病院開院以来12年間働き続けてきたアンギオ装置に不具合が生ずる時期になったための更新で、6週間の工事の後2018年4月から新しい装置が稼働した。バイプレーンの装置を導入し、画像解析技術の向上とも相まって少ない造影剤と放射線で検査・治療ができるようになった。あわせて周辺機器の多くを更新した。あらたに光干渉断層画像診断装置(OCT)や3次元マッピング装置(CARTO3)も導入し、動脈硬化や不整脈の治療に活用できるようになった。
ハードウエア面のもう一トピックは高度治療部(HCU)開設だ。集中治療部門を持たないことは、当院の長年の課題だった。当科は扱う疾患の特性上、呼吸・循環管理を要することが多く、心室細動などの致死的不整脈に対しては、文字通り秒単位の即時対応が必要である。従来、一般病棟で診療してきたが、個々のスタッフの頑張りでしのいできた側面が強く、安全管理上不安な点があった。人員配備や予算などさまざまなハードルがあったが、富所病院長の勇断で2019年4月開設の運びとなった。我々にとっては待望のHCU開設であった。急性心筋梗塞や重症不整脈、呼吸・循環補助を要する重症心不全、心肺停止蘇生後の体温調節療法などがHCUで集中的に管理されるようになり、一般病棟では特殊で負担のおおきな疾患や治療が、余裕をもって取り組める、ある意味普通の疾患や治療となった。我々もこれまで以上の安心感で、患者をゆだねることができるようになった。
2020年1月から始まったコロナ禍は循環器内科にとっても他人事ではなかった。コロナ感染で血栓性が亢進することが判明し、急性心筋梗塞など、血栓を基盤とする疾患の報告が相次ぎ、コロナ感染者の急性心筋梗塞への対応に備える必要が生じた。心カテ室の感染防護、スタッフのPPE装着訓練、院内移送の手順確認、コロナ病棟(母体は5西呼吸器内科病棟でAMIの管理経験なし)での急性期管理など、検討課題が山積した。幸い当院でのコロナ感染AMIは数件にとどまったが、PPEを装着しての緊急カテは、思いのほか視界が悪く難渋した。軽症で合併症のない症例であったことが幸いであった。高齢のコロナ合併心不全も相次いだ。高齢コロナ感染者は、コロナ感染の予後が悪いことに加えて、隔離期間中のリハビリ介入が不十分なことによるADL低下が深刻な問題だった。なんとか隔離期間を乗り切ってもADL低下が著しく自宅復帰ができない症例がおおく、これは、コロナが軽症化した今日でも、なお続いている課題である。
不整脈治療:CARTO3導入以後、田川医師の頑張りで不整脈に対するカテーテル治療が本格化した。心房細動に対するカテーテルアブレーションの件数は2024年度には30件を超え、クライオアブレーションなど新技術の導入も進めている。
心臓リハビリテーション:高齢人口の増加に伴い心不全患者が急増している。高齢心不全患者では、在宅に復帰できるようADLを落とさない治療と、再入院を減らすための疾患管理と患者教育が大切である。当院は2018年に心大血管リハビリテーション認定施設を取得し、慢性心不全患者への教育システムつくり、心不全患者への段階的リハビリの導入、多職種の介入による総合的なサポート体制の構築を進めている。
腫瘍循環器内科:当院は長岡地区の地域がん診療連携拠点病院で、多くのがん患者を診療している。近年開発された新規がん治療薬には、心血管合併症をきたすものもあり、臨床的に注目されている。またがん治療の進歩によりがんサバイバーが高齢化し、これらの患者における心血管系疾患の合併が新たな課題となっている。当院でも化学療法関連心血管合併症をきたした症例が経験されており、これら学際的な領域にも知見を深めて対応する必要があると考えている。
働き方改革と地域医療再編:2024年に始まった働き方改革では、医師ひとり当たりの労働時間の上限が規定された。これに対応するためには、業務の見直しと効率化を進める必要があるが、これには単一施設での対応では限界がある。医療資源の供給体制をふくめ、地域全体での役割分担の見直しを進める必要があると思われる。
小児科
小児科
小児科 竹内一夫
私、竹内が小児科医となったのが1994年であるが、その頃すでに郡司哲己医師と松井俊晴医師が小児科部長をされており二人は長岡中央綜合病院小児科の代名詞的存在であった。その頃は子どもの数も多く小児科病棟は入院患者でごった返していた。当科は喘息患児の治療や教育に力をいれていたこともあり、喘息の入院患者はつねに50名程度であったと聞いている。喘息だけでなく川崎病、てんかん、内分泌疾患、夜尿症など専門性の高い診療もお二方で担っており中越地区の小児医療で大きな存在感を示していた。当院小児科の発展はお二人の尽力によるといっても過言ではない。周産期新生児を専門としている竹内が当院に赴任したのが2008年である。当院は地域周産期母子センターであるが、それまでは新生児医療に関しては総合周産母子センターである長岡赤十字病院に頼りがちであった。以後は、当科でも新生児医療をすすめ長岡赤十字病院と連携して行うにようになった。
郡司医師が2019年に、松井医師が2023年にと二人のレジェンドが退職され、竹内が小児科部長を引き継いだ。お二人とそのさらに先人たちの築き上げたレベルと信頼を維持できるのか大きなプレッシャーを感じている。現在は竹内、堀、鈴木、皆川、桜沢の5人のチームで診療を行っている。皆川はアレルギーを専門としており、太田こどもとアレルギークリニックの太田匡也医師と協力して食物アレルギー負荷試験を精力的に行っている。
小児医療をとりまく環境は大きく変化した。当初は前述のごとく外来患者、入院患者ともに多くて多忙であったが、現在は非常に少なくなっている。その理由はいくつかある。
まず、小児喘息管理の進歩である。ステロイドが積極的に使用されるようになり、喘息で入院する子どもがとても少なくなった。20〜30年前はまったく異なる管理法が行われており、毎月のように発作を起こして入院する児もめずらしくなかった。管理の進歩で喘息の子どもが入院せずに済むようなったことは喜ばしいことである。
次に予防接種の進歩である。予防接種で対応できる病原体の種類が増えワクチンも進歩してきた。たとえば、ロタウイルス腸炎の予防接種が開始される前は、流行期になると胃腸炎の子どもで病棟があふれかえっていたが現在はそのようなことは全くなくなった。また、肺炎球菌ワクチンが開始されてからは肺炎や中耳炎が減った。さらにより広くカバーできる肺炎球菌ワクチンが次々に開発されている。
最後に少子化である。小児患者数の減少という形で少子化を実感している。新生児医療についても、赴任当初は、当院の分娩数は年間1000件以上あり新生児治療室はほぼ常に満床であった。現在は分娩数が激減し新生児治療室の入院患者がいない日もある。少子化は日本の将来に関わる大きな問題である。国や自治体が頭を悩ませ策を講じているが効果は未だみられない。
少子化に伴い小児医療に対するニーズも変化してきたように感じる。昔は受診者が日々外来に押し寄せ、ひとりひとりの診察時間が十分にとれているとは言い難かった。また、患者さんの方もそれをわきまえてか、とりあえず薬をもらえればよいというスタンスであったように感じる。現在は処方、治療のみならず親の安心や満足に応えることが求められている。診察時に子どもの生活や子育てについて相談されることも珍しくない。受診者が減少して時間が十分にとれるようになったぶん、そのようなニーズに応えることが可能となった。患児とその家族にとっては好ましいことであり、これはこれで小児医療の進歩と言えるのかもしれない。
また、不登校や発達障害など以前は教育分野の守備範囲であったものも医療の対象となっている。今後、各自治体で5歳児健診が導入される予定となっている。目的は就学前の発達障害のスクリーニングである。漏れがないように行おうとすると発達障害を疑われた子どもが大勢医療機関を受診することになるだろう。現在、発達障害診療は一部の小児科医精神科医による特殊な診療となっているが、今後は小児科の一般的な診療分野となっていくのかもしれない。
外科
21世紀 長岡中央綜合病院外科の歩み
外科 河内保之
はじめに
私は2000年10月に新潟大学からの派遣医師として当院外科に勤務を開始し、翌年に常勤となって以来、今年でちょうど四半世紀が経過しました。長岡中央綜合病院の90周年を機に、この25年を振り返ってみたいと思います。
21世紀外科のスタート
1980〜90年代を支えた外科スタッフは転勤や開業により交代し、2001年には全員が入れ替わり、外科医5名(常勤2名、出張3名)での再出発となりました。当時は消化器癌に対する有効な薬物療法が乏しく、外科は拡大手術の時代でした。他臓器の合併切除や広範囲リンパ節郭清が盛んに行われ、胃癌では現在なら3〜4時間で行える腹腔鏡手術も、当時は開腹手術で膵・脾合併切除、傍大動脈リンパ節郭清を伴う拡大手術に7〜8時間を要することも珍しくありませんでした。少人数での診療体制のため、外来終了後に手術を開始し、帰宅は深夜になることもしばしばでした(現在の働き方改革からすると到底許容されない状況です)。
こうした積極的な外科治療は地域の医療機関からも高く評価され、切除困難とされた進行癌患者さんの紹介が増加しました。その結果、2000年の手術件数512件は2003年には734件へと増加し、外科医も常勤2名が加わり7名体制となりました。
病院新築移転と鏡視下手術の導入
2005年10月、病院は現在の川崎町に新築移転しました。これを契機に手術件数は急増し、2007年には年間1,000件を超えるようになりました。大腸癌に対しては2002年に腹腔鏡手術を導入し、2024年には85%以上が腹腔鏡下手術となり、累計2,800件を超えました。食道癌は2004年から胸腔鏡手術を導入し、現在はほぼ全例で行われ、300例を超えています。胃癌は2008年から導入され、現在はほぼ全例が腹腔鏡下で行われ1,200例を超えました。さらに肝切除や膵切除など他領域にも鏡視下手術が拡大しています。
2006年から2019年まで当院で行った「ライブデモ手術」も鏡視下手術の普及に大きく寄与しました。年1回、国内の第一人者を招き、患者さんの同意のもとで執刀いただいたもので、中越地区のみならず県内外から最大70名以上が見学に訪れました。こうした取り組みは県内の腹腔鏡手術の発展にも大きく貢献したと自負しています。
現在では、安全で確実な腹腔鏡手術が日常診療に定着し、術後疼痛の軽減、早期離床、短期入院が可能となりました。
専門性の深化
外科スタッフは拡充し、現在は常勤7名、派遣医5名の計12名体制となっています。当院では疾患ごとに専門性を高める取り組みを進め、胃癌・大腸癌領域では国立がん研究センターを中心とした多施設共同臨床試験に参加し、多くの患者さんの協力を得ながら新たな治療法の開発に携わっています。
また、日本外科学会・消化器外科学会の認定施設であるとともに、大腸肛門病学会、食道学会、乳癌学会、肝胆膵外科学会、胃癌学会、胆道学会などの認定・指導施設資格も取得してきました。さらに、消化器内科・腫瘍内科・放射線科など関連部門との連携を強化し、集学的治療を推進しています。乳腺外科領域でも形成外科・放射線科と連携し、診断から術後補助療法、乳房再建まで一貫した治療体制を整備しました。
高齢化社会への対応
2000年における当院の胃癌・大腸癌患者さんの平均年齢は67歳で、80歳以上は15%程度でした。2024年には平均73歳、80歳以上31%、90歳以上2%となり、高齢患者さんの手術が日常となっています。高齢者は臓器機能低下により合併症リスクが高く、麻酔科との連携による全身麻酔の安全性向上、低侵襲術式の選択、術前からの栄養・リハビリ介入などに取り組んでいます。さらに、看護部・薬剤部・栄養科・リハビリ科と連携した予防的介入により、高齢患者さんが手術後も地域で元気に生活できるよう支援しています。
これからの外科
近年、全国的に外科専攻医の減少が課題となっています。厚生労働省の統計によれば、過去30年間で医師数全体は2倍以上に増加したにもかかわらず、減少しているのは出生数減少の影響を受けた産婦人科と消化器外科です。全国的に消化器外科を専攻する割合は約8〜10%ですが、当院では基幹型臨床研修病院としてこれまで約160名の研修医が修了し、そのうち18%(28名)が外科を専攻し、県内外で活躍しています。若手外科医の育成も私たちの大切な使命と考えています。
おわりに
外科医療はさらなる技術革新の時代を迎えています。当院でも高難度症例への腹腔・胸腔鏡下手術の適応拡大や、ロボット支援手術の導入を検討しています。加えて、AIやビッグデータ解析を用いた手術・治療支援も開発が進んでいます。これらは単なる新技術ではなく、患者さんの安全と満足度向上を目的とした進化です。
ただし変わらないのは「患者さんのために最善を尽くす」という姿勢です。長岡中央綜合病院外科は、今後も安全で確実な手術と術後の生活を見据えたケアを両立させ、地域医療の柱として役割を果たし続けます。
100周年、そしてその先へ――。

外科は2025年8月現在12名のスタッフで診療中
整形外科
長岡中央綜合病院整形外科における10年の近況
整形外科 浦川貴朗
長岡中央綜合病院80周年誌にて長谷川淳一よりこれまでの整形外科の軌跡を紹介しました。この度90周年誌が発行されることになりましたので、ここ10年の近況及び最新の診療内容について報告いたします。
まず人事について報告いたします。副院長兼整形外科部長の長谷川淳一が2017年に退職し、矢尻洋一が整形外科部長となりました。続いて2022年矢尻が院長に就任したことで、現浦川貴朗が整形外科部長となりました。現在整形外科は専門医7人、専攻医3人、研修医0-2名にて診療にあたっております。

次に整形外科の日常診療について紹介いたします。まず朝8時より全員で前日の骨レントゲンを確認しております。さらに治療に困るような症例について意見を出し合い最適な治療法が選択できるようにあらゆる角度から検討しております。

8時30分からは各々分かれての診療になります。外来では、創処置を処置室で、一般診察を2、4-7診察室で行なっております。基本的に外来診察は午前中となりますが、水曜日は午後診察を行なっております。また、3週に1回水曜日午後にリウマチ外来を新潟大学医歯学総合病院の近藤直樹医師より担当してもらっております。
9時30分からは各医師週1回、入院担当患者さんのリハビリや診療状況について病棟看護師、理学療法士、入退院支援看護師を交えた多職種カンファレンスを開催しております。ここで入院中の治療の方向性を確認したり、退院に向けたリハビリの進め方について検討したりしております。

大腿骨近位部骨折にて入院された患者さんの再骨折を予防する目的でリエゾンカンファレンスを毎週水曜日午前9時20分より開催しております。村山医師、薬剤師、看護師、医療ソーシャルワーカーで最適な骨粗鬆症治療薬の検討を行なっております。
手術は、毎日10時30分から行なっております。整形外科の手術件数はここ10年約1500件となっております。
最後に脊椎班、関節班、手外科班より10年の近況及び最近の診療内容について報告いたします。
脊椎班 高橋一雄
2015年から2024年にかけて、毎年270~300件の手術が施行されました。2015年は頚椎、胸椎が約70件、残りが腰椎でしたが、その後も大きな変化はありません。2015年以前の約10年は矢尻、高橋一雄の2名が担当しておりましたが、2018年より若手の高橋郁子医師が赴任しました。赴任後まもなくナビゲーションシステムが導入され、大学で研鑽されてきた高橋郁子医師のもとに安全、確実にインストルメント手術が行われるようになりました。大活躍の高橋郁子医師でありましたが残念ながら2年半で転勤されました。その後は若手医師が1年交替で派遣されるようになりましたが、熱心な医師が多く助かっております。2022年矢尻医師が院長になったため代わりに浦川医師が赴任しチーフとなりました。現在は主に浦川、高橋一雄、若手医師の三人で診療にあったっております。
この10年でのトピックは何といっても椎間板酵素注入療法(コンドリアーゼ)の登場であろうかと思います。約5年前に始まった椎間板ヘルニアの治療です。局麻で行われます。当院では日帰りで行っております。これまで合併症で全身麻酔がかけられず手術できなかった患者さんにも用いることができるようになりました。約80%に有効であります。本法を積極的に行っている当院では椎間板ヘルニアの手術が激減しております。残念ながら現在供給が一時的に止まっております。早期の再開が待たれるところであります。
関節班 村山敬之
関節外科は膝・肩・スポーツ整形外科を担当しています。2013年より当科で関節外科診療の中心を担ってきた有海明央が2019年10月に異動となり、後任として村山敬之が赴任し現在まで診療を行っています。また、関節外科研修として新潟大学整形外科医局より毎年1名が派遣され、有海、村山と共に診療に携わってきました。
膝関節診療では、変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術、人工膝関節単顆置換術、人工膝関節全置換術や膝靭帯断裂、半月板損傷に対する関節鏡下の低侵襲手術に取り組んできました。肩関節診療では、腱板断裂や反復性肩関節脱臼に対する関節鏡下手術が多く行われるようになりました。2014年より修復不能な腱板断裂に対して本邦でもリバース型人工肩関節置換術を施行可能となり、当院での施行件数も増加傾向にあります。その他、足関節や肘関節のスポーツ障害に対する手術にも積極的に取り組んでおります。
手外科班 善財慶治
直近10年の手外科診療について
- 人事では2015年時点では長谷川淳一、善財慶治の2名が中心となり診療を行っていました。2017年4月に長谷川が三条市富永草野病院に赴任し、後任として河内俊太郎が就任しました。河内は2021年10月に新潟南病院に赴任し、以後山田政彦(2022年10月に新潟手の外科研究所病院に異動)、石坂佳祐(2023年10月に新潟市民病院に異動)、今井真(2025年4月に新潟臨港病院に異動)と手外科研修中の医師が交代で勤務しました。2025年8月現在は高橋響が在籍しています。
- 手術数は2015年から2024年の間で年平均419例(353例~467例)でした。内訳は、骨折・脱臼・靭帯損傷等226例(年平均、以下同様)、腱手術15例、末梢神経手術65例、炎症性疾患62例、腫瘍類11例、マイクロサージャリー12例などであり、併施手術として手関節鏡手術が45例でした。
トピックス
- 橈骨遠位端骨折はここ10年も減少することなく毎年70例前後手術となり、より粉砕した骨折も多くみられるようになりました。これに対応すべく新たに開発された内固定材(遠位設置用プレート、固定角可変プレート)を用いた手術が増えてきています。また、関節鏡の併用によって、より正確な関節面の整復・内固定が得られるようになりました。
- 橈骨遠位端骨折症例の中には同時に遠位橈尺関節を支える三角線軟骨複合体も損傷している場合があり、これに対しても関節鏡を用いた診断・治療を行えるようになりました。
- また、橈骨遠位端骨折は骨粗鬆症に起因する脆弱性骨折のうち最も早く生じる場合が多いことから、受診時にルーチンに骨密度などの検査を行ってスクリーニングし、必要に応じて早期から骨粗鬆症治療に介入することで将来の骨折連鎖を予防する活動も開始されています。
- 整形外科領域におけるエコーの普及が急速に進んでおり、手外科領域でもまず手術などの際の腕神経叢ブロック時に導入され、現在ではエコー下ブロックがスタンダードとなりました。また、腫瘍や皮下異物、腱鞘炎などの診断や治療におけるエコーの使用が外来でも数多く行われるようになりました。
- Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注入療法はそれまでの手術による部分腱膜切除に比し短期間での回復、術後疼痛が少ない、合併症リスクが低いといった点で画期的な治療法であり当院でも2018年に導入したが、製造元から本国への供給が停止されたため2021年以降は使えなくなり、現在は主に物理的に病的腱膜を脆弱化した後破断する経皮的腱膜切離術を行っています。
- 近年、手根管症候群の一因であるトランスサイレチン型アミロイドの検索から心アミロイドーシス予防を目的とした循環器科との連携も行われるようになりました。
形成外科
形成外科
形成外科 渡辺玲

形成外科外来で 左より クラーク大竹さん、渡辺、太刀川看護師 2025年8月
少し形成外科の歴史について触れさせてください。
新潟大学医学部形成外科は1979年に整形外科の診療班として本格的に診療を開始しました。(当院に長く勤めておられました星栄一先生が始められました)1996年度より文部省から新潟大学附属病院形成外科の新設が認可され、同年7月から柴田実先生が初代教授に就任されました。
2015年柴田先生が退任し、同8月から松田健先生が二代目の教授に就任されました。
2017年には新潟大学形成外科同門会が正式に発足しました。(それまでは整形外科の同門会に属している形でしたので、ここで初めて形成外科単独の同門会となりました)
私が当院で形成外科医として勤務を始めたのは2014年の7月からになります。
専門医を取得し、数年経過してから医師11年目の時です。
長岡に来る前はというと、杏林大学を卒業した後そのまま大学に残り勤務していました。
柴田先生とも、松田先生とも1か月という短い間でしたが新潟大学勤務中にご一緒することができました。
私がこちらに勤務するまでの間、2011年2月から形成外科の常勤医は上條正先生おひとりでした。
私が異動してきて2人体制となり、当初はあまり忙しくなかったのですが、数ヶ月もすると忙しくなってきました。
当時形成外科の外来には高野美智代看護師が勤務していました。以前おられた星先生とも長い期間一緒に働いてきた方です。私が来てからというもの、あれがない、これがない、このテープを用意してくれ、なんでこれがないんだ、とかなりうるさいことを言い、とても困らせてしまったと思います。言い訳になりますが、テープ一つこだわるのが形成外科医なのです。また、切れないはさみほどイライラするものはありません。どういう時にどのテープを使うのか、それはなぜか、機能的にはもちろん、見た目も美しくあってほしい、そういうところを気にするのが形成外科医なのです。テープの種類を増やし、常に切れるはさみを複数用意してもらえるようになりました。ありがたいことに当初から担当していただいたJメディカル(現在クロスウィルメディカル)の遠藤さんも興味をもってくださり、当院で使用可能なテープの一覧等、カラーで表を作ってくださいました。それを用いて看護師向けの勉強会等も行いました。
2015年4月からは高橋万寿子看護師が形成外科担当となります。
まだまだ形成外科は院内でも知られていないことが沢山あり、周知のため、病院祭で講演会をすることもありました。形成外科として特有なものの一つに再建があります。
新潟県では乳房再建の件数が全国平均を下回っており、東京の大学病院では毎週のように行われていたのをみてきた私としては少し寂しいものがありました。
乳がんの患者さんは近年増加傾向にあり、低年齢化しているため、必ず需要があると思うのです。
乳房再建を保険で行うためには指定の学会に所属して講習を受けることはもちろん、専門医が常勤医として勤務していなければなりません。また施設を登録、医師も登録し、症例も毎年報告することが義務付けられています。
登録してから実際に手術が可能になるまで少し時間を要しましたが、無事、施設認定を受け、2015年から保険で乳房再建を行うことが可能になりました。
(それまでは症例も少なかったですし、インプラントでの乳房再建については自費でおこなっていました。)
上條先生と2人体制がしばらく続いていましたが、火曜日の全身麻酔の手術の時は隔週で大学から宮田昌幸先生が手伝いに来ていただいていたので、特に人手に困ることはなかった記憶があります。
当院の研修医は希望があれば当科をまわることができ、毎年数人くらいは研修に来ていました。まわり始めと終わりで飲み会をすることも楽しみのひとつだったのですが、コロナ禍でそれも激減しました。
東京では形成外科医は溢れて余っていますが、新潟では足りていません。毎年、医局員の確保に苦しんでいるというのが正直なところです。
2015年に入って当科をまわってくれた研修医のうち、2人が形成外科に入局するという信じられないことが起こりました。研修医10人のうちの2人ですから、すごいことです。
その時は同じ学年で4人も同期がいましたから、とても運が良かったと言えます。
加藤真帆先生、田中宏明先生、彼らは大学勤務中に当院にバイトに来る機会もあり、嬉しいご縁を感じました。今では立派な形成外科専門医です。当時は入局してもらえるとは思っていませんでした。
2019年1月からついに形成外科にも担当の医療クラークの方が外来診療の際に同席してもらえるようになりました。関朱美さんです。
2019年4月から野澤昌代先生が加わり、3人体制になりました。
症例も多くなり、外来も2診、時には3診同時進行もあり、外来看護師が2名になりました。高橋真寿子看護師に加え、福田綾美看護師、野澤先生、私、と女子ばかりで上條先生はつらかったかもしれません・・・
福田看護師が退職された後は金子美和看護師が加わりました。
2020年からは医療クラークとして大竹忍さんが加わりました。
外来診療時はいつも助けていただき、感謝しかありません。
2022年、上條先生が退職されてから塚田鼓先生が加わり、女子3人体制です。
その次の年、塚田先生が異動した後、当院研修医だった丸山里緒先生が加わり、また女子3人体制になりました。(同じ研修医だった島田慧先生も形成外科に入局してくれました。)
野澤先生は当院勤務中に無事に論文を提出、試験にも合格し、専門医を取ることができました。(ご協力頂いた周囲の先生方、スタッフの方々ありがとうございました。)
2023年5月から太刀川裕美看護師が加わります。2024年3月末、高橋看護師が退職するまでは看護師二人体制でしたが、その後は太刀川看護師のみとなりました。
同じ4ブロックの小児科の石積看護師や渡辺看護師の力も借り、何とかやっています。
2024年7月から野澤先生が県央基幹病院の1人医長として異動、丸山先生と私の2人体制になります。
2024年10月から丸山先生が県立中央病院に異動となり、ついに1人体制になりました。
1人体制になってから約1年経過します。
診察の制限をさせて頂いていますが、それでも1人だとできることに限界があり、ご迷惑をおかけしております。
今までも周りの方々に日々助けられていたこと、1人になってより強く感じています。
これからも微力ながら中越の医療に貢献できるよう、頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
過去の写真をいくつかご紹介します

形成外科外来1診 ひだりから渡辺、高橋看護師、上條先生 2018年7月 形成外科外来で

ひだり奥より クロスウィル遠藤さん、クラーク大竹さん、金子看護師、高橋看護師
ひだり手前より 宮田先生、福田看護師、渡辺、野澤先生 2021年5月
脳神経外科
脳神経外科
脳神経外科 加藤俊一
診療体制、最近10年間の変遷
青木廣市 初代部長:1981年(昭和56年)4月~2001年(平成13年)8月
竹内茂和 部長:2001年9月1日~2017年(平成29年)3月31日
谷口禎規 部長:2017年4月1日~2025年(令和7年)3月31日
当院脳神経外科は、1981年(昭和56年)4月、青木廣市初代部長が赴任開設以来44年間診療を継続している。当院創立90年のうち、約半分の期間の診療を担ってきた事になる。竹内茂和部長退任後は谷口禎規部長以下常勤医3名体制で診療に当たっている。
脳神経系の救急疾患としての頭部外傷、脳血管障害及び院内他科・地域のクリニック病院からご紹介頂く脳腫瘍の患者さんを対象に、中越地域の幅広い医療ニーズに対応している。最近のトピックスとしては、2019年のHCU病棟開設に伴い、くも膜下出血症例、血栓溶解の適応となる発症早期の急性期脳梗塞患者、重症頭部外傷、全身麻酔手術後症例はバイタルサインチェックと神経症候の厳重な観察のためにHCU病棟管理となり医療資源が重点的に配置された。従来の一般病棟であった7階東病棟はHCU病棟開設に伴い混合病棟となり、神経疾患以外の患者も入院し、7階東病棟が満床時は神経疾患症例も他病棟への入院管理に更新された。
2020年初頭に始まったコロナウイルス蔓延は脳神経外科診療に甚大な影響を及ぼした。緊急を要さない予定手術の延期、発熱患者へのウイルス検査の追加、感染防護の徹底、懇親会や学会参加の制限、医療者の県外移動の自粛、オンラインでの学会参加や勉強会の増加。院内でのマスク着用や入院患者の家族面会制限は現在も継続している。外来患者数・入院患者数・手術件数はコロナウイルス蔓延を契機に減少傾向となり、入院患者数・手術件数は漸次回復傾向となったが外来患者数は減少が続いている。

図1
コロナウイルス以外にも2024年4月以降の働き方改革の実施は院内全体の労働時間減少を促進し、長時間手術や時間外手術が激減した。現場の地域医療の中では、患者年齢の高齢化、域内対象人口の減少も外来入院患者数・手術症例数の下降に影響を及ぼしている。院内検査ではCTアンギオ活用で従来の診断用脳アンギオ検査(DSA)数が減少。診療面では、従来の顕微鏡手術以外に内視鏡手術導入による低侵襲化で高齢患者にも手術適応を拡大している。
令和時代医療の特徴として、院内院外ともにチーム医療・医療連携が強く求められると共に医療効率・医療安全が重視されるようになった。脳卒中患者転院調整のための医療機関同士の地域連携は平成時代より機能していたが、当院が域内の総合病院としてかかりつけ医から求められる病診連携、地域消防隊からの急患対応・ドクヘリ患者の受け入れ、院内他科との連携(脳神経内科に平日昼間の脳梗塞患者初期対応依頼・毎週の合同症例検討会開催、放射線治療科に脳転移患者の頭部定位放射線治療依頼と入院管理対応、リハビリ部門による休日含めての急性期リハビリテーション導入)で入院患者へ多職種対応で医療を提供している。他にも入院患者の院内転倒頭部外傷への対処で院内医療安全の一翼を担い、院内発症脳梗塞急性期患者へも往診している。医療効率の面では、クリニカルパス導入により入院期間の短縮化が図られ慢性硬膜下血腫の入院期間は5~6日間となった。医療安全の面では、転倒転落防止や夜間せん妄患者への対処、手術室内での術前タイムアウト実施はルーチン化した。
課題は地域での若手脳神経外科医師の育成と考える。当院では初期研修で脳神経外科を選択する研修医は多いものの、後期研修医や専攻医として脳神経外科医を志す若手医師は少ない。域内の人口高齢化に伴い今後も当院での認知症や脳卒中患者は増加傾向が予想され、その中で脳神経外科疾患の患者は一定数存在し、持続的な脳神経外科診療継続のためには若手医師にとっての魅力的な診療体制や教育体制を構築していくことが急務である。
デジタル化された院内デバイスを有効に利用しつつ、スタッフ(写真1)同士の意思疎通を円滑にし、状況変化が激しい昨今の社会情勢の中で地域中核病院脳神経外科として持続可能な診療を今後も目指して行きたい。

写真1
呼吸器外科
血管外科
皮膚科
90周年をふりかえり(近年10年のイベント)
皮膚科 和泉純子
当院は昭和16年7月に新潟県中央病院として開院し、皮膚科診療は昭和17年に益田兼清医師のもとで皮膚科泌尿器科として発足しました。昭和17年から平成25年までの歴史は創立80周年記念誌を御参照ください。
平成15年からは皮膚科医師一人の体制の医療が永く続きましたが、平成25年7月に高橋利幸医師が赴任して医師二人体制の医療が提供できるようになりました。
また高橋医師は抗加齢医学専門医でもあり、疾病予防に力を注がれております。
平成25年に308±2nmの波長をもつエキシマライトを搭載したターゲット型UVB照射器が導入され、尋常性白斑、尋常性乾癬、円形脱毛症、結節性痒疹などの皮膚疾患の治療内容が更に充実しました。薬剤では多種の生物学製剤が登場し適応疾患が増えた事で、入院を余儀なくされる患者さんは減少傾向にあります。またその他の面では、綜合病院ならではの皮膚科医の役割がずいぶん拡大したように思われます。皮膚科としての患者数や診療点数にはカウント表示されない他科に入院中の患者さんからの診療依頼が増加して、1日平均8件程度にもなり日々奮闘しているところです。
今の研修医制度では皮膚科の研修は必須ではありませんが、当科での研修を希望された医師らから2名の皮膚科専攻医が誕生して他地域で活躍しておられることは大きな喜びです。
現在、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士など多様な専門分野を持つ医療従事者がそれぞれの専門性を活かしつつ情報を共有して連携・協力しながら最適な医療とケアを提供するチーム医療が推進される中、いち早く和泉医師は褥瘡対策チームを取りまとめ、高橋医師は栄養サポートチームへ参加し、共に活発に活動し実績を挙げております。
この10年間でさらに超高齢化社会は進み、その中で患者さんが住み慣れた地域で一生生活する為には皮膚科医も多職種による連携を一層強くする必要がある時代になったと痛感しています。
泌尿器科
産婦人科
産婦人科
産婦人科 加勢宏明
婦人科手術件数(産科手術を除く)は、2019年の384件から2024年も384件と横ばいで推移しています。しかし、その内訳には変化がみられ、腹腔鏡下手術は77件から107件へと増加し、とくに腹腔鏡下子宮全摘術も36件から58件へ増加しました。2020年から導入した腟式腹腔鏡下子宮全摘術は順調に増加し、2024年には31例となっています。
当院の特徴である骨盤臓器脱手術は、120例前後で推移していますが、メッシュによる矯正術(TVM手術)は減少傾向にあり、2024年は48件となりました。一方で、骨盤臓器脱症例でも腟式腹腔鏡手術の導入にしており、2024年は15例と増加傾向です。
悪性腫瘍症例はこの10年間で大きな変化はありませんが、直近2〜3年は子宮頸部上皮内腫瘍が減少傾向にあります。子宮体癌については、腹腔鏡下手術の施設認定を取得し、2024年よりIA期体癌への実施を開始しました。
分娩件数は少子化の影響を強く受け、2016年の1,044件から2024年には359件まで減少しました。そのなかで、社会状況の変化に対応し、超音波検査技師によるスクリーニングエコーや新型出生前診断(NIPT)を導入してきました。さらに、2025年9月からは無痛分娩を開始しています。

現在のスタッフ
以下に2015年4月以降に勤務した産婦人科医師を列挙します。
2015年4月 加藤政美、加勢宏明、本多啓輔、横田有紀、大島彩恵子
2015年5月 加藤、加勢、本多、古俣 大、横田、大島
2015年6月 加藤、加勢、古俣、横田、大島
2015年7月 加藤、加勢、古俣、横田、大島、上田遥香
2015年10月 加藤、加勢、古俣、横田、上田
2016年1月 加藤、加勢、古俣、横田、上田、風間絵里菜
2016年2月 加藤、加勢、古俣、横田、風間
2016年4月 加勢、古俣、横田、松本賢典、風間
2016年7月 加勢、古俣、横田、松本、齋藤強太
2017年7月 加勢、古俣、横田、松本、高橋考太朗
2018年4月 加勢、古俣、横田、松本、安田麻友
2018年7月 加勢、古俣、横田、戸田紀夫、安田
2019年4月 加勢、古俣、横田、戸田、川浪真里
2020年4月 加勢、古俣、横田、春谷千智、清水圭太
2021年10月 加勢、古俣、横田、春谷、高橋佳奈
2022年4月 加勢、古俣、横田、春谷、高橋、横田一樹
2022年10月 加勢、古俣、横田、春谷、深津俊介、横田(一)
2023年4月 加勢、古俣、横田、春谷、木谷洋平、深津、倉井 伶
2023年6月 加勢、古俣、横田、木谷、深津、倉井
2023年9月 加勢、古俣、木谷、深津、倉井
2024年4月 加勢、古俣、木谷、霜鳥 真、小林澄香
2025年4月 加勢、古俣、木谷、小林琢也、相庭晴紀、寺澤昂希
2025年10月 加勢、古俣、小林、今井 諭、相庭、寺澤
眼科
眼科
眼科 高田律子
長岡中央綜合病院創立90周年記念で眼科についての寄稿をさせていただきます。
創立80周年記念で当時の眼科部長が当院眼科事始めから創立80周年までの当科の経緯を詳述しておりますので、当方は主にそれ以降の眼科の変遷を述べさせていただきます。
創立80周年までとの大きな違いは電子カルテ導入で、眼科にとっては電子カルテ導入前・導入後と言っても過言ではないほど診療・手術・治療成績に影響を与える重要な出来事となりました。当方は新潟大学医歯学総合病院及び新潟県立中央病院で2回電子カルテ導入を経験、前者は一医局員として後者は眼科部長として指揮を取る立場でした。この経験を活かして当時から現在に至るまで一人医長となっている長岡中央綜合病院眼科の電子カルテ移行に対応できる人員として医局からの依頼があり2016年の電子カルテ導入直前に当院に赴任しました。
眼科は検査器械見本市と言ってもよいくらい日常の検査機器に精密かつ高額な機器が多く、電子カルテに接続するケーブルの本数が他科と比べ一桁違うことから接続に膨大な費用と手間がかるため大学でも県立病院でも移行時に総務との予算のやり取りが欠かせないのですが、当方が当院に来たときは既に予算配分が決まっており変更不能となっていました。このため当時のシステム担当と密に連絡をやり取りし、外来スタッフに日常診療に支障をきたさないようにこれまでの検査機器や紙カルテのデータを電子カルテに移行するよう依頼、不足しているモニター等は元々あるものをやりくりして日常業務に支障をきたさないように準備して電子カルテ移行にこぎ着けました。電子カルテではどうしても診察時のパソコンの動作が紙カルテよりも遅くなり診察に時間がかかることから、電子カルテ移行を契機に完全予約制に変更しました。
その後もプライバシー保護の観点から名前で呼び出しをしていたのを受け付け番号で呼び出すように変更したり、外来の検査機器の配置変えをしてより広く使えるようにしたりと工夫を重ね現在に至っています。
手術に関しては新潟県内で最も早期に術中OCTを導入し、黄斑円孔や黄斑下血腫などの網膜黄斑部疾患の治療成績向上に役立っています。またコロナ禍で病床制限されていた白内障手術はこれまで通り予約できるようになり長期間の手術待機は解消されています。なお難易度の高いプレート移植を伴う緑内障手術は当院が施設基準を満たしていないため、主に施設基準を満たしている長岡赤十字病院眼科へ紹介となっています。
今後も検査機器および手術機器更新を予定しており、患者様への負担軽減と手術成績向上を目指しスタッフ一同精進してまいります。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
90周年の耳鼻咽喉科・頭頸部外科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 岡部隆一
2020年に前任の田中久夫先生が退職され、2020年4月から太田久幸先生が後任として赴任され2020年10月からは尾股丈先生が異動になり当院の耳鼻咽喉科は二人体制となりました。
もともと中越地区では長岡赤十字病院で耳鼻咽喉科領域の癌すなわち頭頸部癌の治療を行っていましたが2020年度から当院へ中越地区の頭頸部癌治療の拠点を移すこととなり2021年4月からは私が太田久幸先生と交代で赴任し現在に至ります。
その間当科の名称も耳鼻咽喉科から耳鼻咽喉科頭頸部外科に変更となり、症例の増加に伴い2023年4月から2人体制から3人体制(3人とも耳鼻咽喉科専門医)へ増員となり2024年4月からは4人体制(専門医2名、専攻医2名)に増員となっております。
頭頸部癌治療の拠点病院としてだけでなく若手育成の病院としても活動を始めています。
2026年秋には頭頸部癌認定研修施設も申請予定です。
当院の治療は頭頸部癌治療全般を行っており、進行癌に対する従来の拡大・再建手術だけでなく早期癌や再発病変に対する内視鏡を用いた低侵襲治療(鏡視下咽頭悪性腫瘍手術、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術)も行っております。放射線治療は有害事象を抑えるためのIMRTも導入しており、薬物療法については保険診療となっている化学療法(抗がん剤治療)についてはほぼすべて行っております。また再発転移症例の治療、緩和ケアについても緩和ケア科と連携して行っております。
当科の病棟は6西病棟で呼吸器内科、皮膚科、形成外科と混合病棟でしたが2019年にCOVID19が流行したことで呼吸器内科単科の5西病棟がコロナ対応の病棟に変更になり、呼吸器内科のサブの病棟である6西病棟がメイン病棟となることで6西病棟がひっ迫しました。また当科の頭頸部癌治療が軌道に乗り入院患者数が増えたことでさらに6西病棟のひっ迫が悪化しました。また当科の病床数も13床から18床に増加することになりそこで当科(10床)と呼吸器内科のみの混合病棟に変更し5西病棟へ移動、また7西病棟にも8床をいただき、5西と7西病棟が当科の病棟となりました。5西病棟は手術入院、7西病棟は抗がん剤、照射線治療を中心に治療を行っています。
また当院は臨床研修医の育成にも務めており、当科も常勤医が増えたこともあり研修医の対応も可能となったため研修医の実習の受け入れを行えるようになりました。ありがたいことに研修医が当科の研修を選択してくれるようになり毎月1-2名の研修医が実習してくれています。ひきつづき当科は研修医育成にも力を入れていきたいと思います。
以上最近10年の当院耳鼻咽喉科頭頸部外科の変化になります。

放射線治療科
当院における放射線治療の歩み
放射線治療科 阿部英輔
放射線治療はがん治療の3本柱の一つであり、手術や薬物療法と並ぶ重要な治療法である。
当院では1971年(昭和46年)にコバルト照射装置が設置され、放射線治療はこの時点から始まった。
当時の資料が残っていないため、どのように治療が行われていたのか詳細は不明である。
1981年(昭和56年)に放射線治療装置として直線加速器(リニアック)が設置され、放射線治療は新潟大学医学部放射線医学教室から非常勤で派遣される放射線腫瘍医が担当する体制となった。
当時の直線加速器のX線エネルギーは4MVのみで、鉛のブロックを組み合わせて照射野を作成していた。
2005年(平成17年)10月の新病院開院に合わせて直線加速器も更新され、Varian社製Clinac 2100C/Dが設置された。
これにより、X線エネルギーは4MVと10MVが使用できるようになり、またMLCも搭載され、標準的な三次元原体照射を行うことが可能になった。
その後、放射線治療装置の経年劣化が進み装置の更新が必要となったことから、放射線治療装置機種選定委員会を設置し、新潟大学医学部放射線医学教室にも参加いただき、新たな放射線治療体制の検討を進めていった。
放射線治療の進歩により全国的に高精度放射線治療が普及してきたこと、また、当院はがん診療連携病院として標準的な放射線治療を実施できる必要があるとされたことより、高精度放射線治療に対応できるようスタッフを充実させ、放射線治療装置を更新することが決められた。
2018年(平成30年)に新潟県厚生連として初の医学物理士を採用し、放射線治療部門に配置した。
2019年(令和元年)に放射線治療棟を新設し、同年8月に放射線治療科が新設され、常勤の放射線治療医として阿部英輔が赴任した。
2台の高精度放射線治療装置(Accuray社製Tomotherapy(Radixact)、Varian社製TrueBeam)が設置され、当院における放射線治療は原則として全例が画像誘導放射線治療(IGRT)で行われることとなった。
高精度放射線治療の展開
2019年8月 放射線治療科を新設。
2019年8月 Accuray社製Tomotherapy(Radixact)による強度変調放射線治療(IMRT)を開始。
2019年11月 Varian社製TrueBeamの稼働開始。
2021年8月 体幹部(肺)定位放射線治療開始。
2021年11月 体幹部(肝)定位放射線治療開始。
2022年5月 頭部定位放射線治療開始。
2024年9月 肺腫瘍に対する定位放射線治療(マーカーレスの動体追尾照射)を開始。
2025年2月 肝腫瘍に対する定位放射線治療(金属マーカー留置での動体追尾照射)を開始。
2025年9月 椎体病変に対する定位放射線治療を開始。

放射線治療棟 (2019年5月23日撮影)

内観

内観

内観

Accuray社製 Tomotherapy (Radixact)

Varian社製 TrueBeam

左から坂井(医学物理士)、本田(放射線腫瘍医)、阿部(放射線腫瘍医)、久島(医学物理士)
放射線診断科
放射線科
放射線診断科 山本哲史
当院放射線科の歴史および新潟大学との関係に関しては80周年記念誌での佐藤敏輝放射線科先代部長の玉稿に詳しいですが、放射線科専門医の誕生からほどない1955年1月に新潟大学放射線医学教室から招聘された専門医峯木輝夫の赴任以来、すでに70年が経過しています。長岡中央綜合病院の90年、新潟大学放射線医学教室の100年の歴史の中でその大半を共に歩んできたことになります。
その後も錚々たる先達が当院放射線科を牽引すべく新潟大学放射線医学教室から派遣され、放射線科というものの基礎や初期の放射線技師の教育、健診業務などさまざまなものを作り上げてこられました。現在の我々は黎明期からのそうした先輩方の努力の積み重ねの上で日々の仕事ができていることを大変ありがたく思っております。
当院ではその歴史的に健診やドックが県内の他施設に比べて多く、今も業務量のかなりを占めていますが、現在の画像診断の主役は近年急速に増加したCTやMRIです。
2009年4月の私の赴任直前である3月に導入されていた、160mmの範囲をほぼ一瞬で撮影することが可能で心臓の冠動脈や頭部の特殊撮影に優れた東芝の320列エリアディテクターCTは、2020年にはディープラーニングを応用した画像再構成技術を用いることでノイズを減らして被ばくを低減、またDual-Energy撮影が可能になり撮影も高速化した、キヤノンメディカルシステムズの同じく320列エリアディテクターCTに更新されました。赴任当時は8列だった東芝のCT2台は2012年にいずれも64列マルチスライスCTに更新されましたが、そのうちの1台は2021年に320列と同様にディープラーニングで被ばく低減を可能にしたキヤノンの80列マルチスライスCTに更新されています。
2010年の当院初の3.0T MRI導入時には放射線技師と一丸になって努力しました。その後、3.0T MRIは2022年に同じくフィリップスの最新型に更新され今に至ります。東芝製だった1.5T MRIは2018年に東芝あらためキヤノン製のものに更新されています。
このように最新の機器に更新することで、身体の情報がより高速に、より詳細に、より安全に得られるようにと順調に進化させてきました。
この10年CTやMRIの撮影件数は増えてはいないのですが、撮影機器の高速化に伴い可能になった撮影範囲の拡大や特殊撮影の増加から1件あたりの画像数が急速に増えており、特にCTでは撮影1件で数千枚に達することも少なくありません。十秒ほどの撮影で1000枚以上の画像が作成できるのですから無理もありません。結果として業務量は増加しています。
10年ちょっと前でしょうか、AIによる画像診断が放射線科医に取って代わるという噂が急速に流れ始めました。実は二十数年前にもCAD(コンピューター支援診断)が放射線科医を駆逐するという噂が流れていましたが、一部は導入されたものの残念ながらそれほど役に立たず業務の助けにはなりませんでした。ずっと過去にもCTが出現〜普及したとき、MRIのときもそれぞれ、これで放射線科医は無用の長物になると言われていたと聞き及んでいますが、その予測に反して現在もこれらの画像は放射線診断医の業務の主体です。以前のCADとは違って、AI診断は確かに胸部写真やCTでの肺結節の検出、頭蓋内出血の検出など単機能での能力は高く、今度こそは本物ではないかと思えます。でも画像診断に限らず診断という作業は極めて多数の単機能診断の集合であり、それが満たされるまでにはまだ時間が必要なようです。そして全身の画像診断は決してその他の診断よりも単純なわけではありません。画像診断をすべてAIが行い放射線診断医が必要がなくなるときは、医師が、人間が診断というものを行う必要がなくなるときではないか、などと考えながら今日も画像診断に勤しんでいます。とりあえず今は少しでも助けてもらえるようになるとありがたいとすら思います。
この10年の放射線科医は常勤の佐藤、山本の2名の他には2015年度は羽根田と小川、2016年度は羽根田と押金、2017年度は髙松、2018年度は山田と富永、2019年度は上原と後藤、2020年度は竹内と本田でした。2021年4月の佐藤退職後は、常勤山本の他は2021年度は竹内と小川、2022年度および2023年度は竹内と瀧澤で全3名でした。2024年度は山本と竹内が専攻医3年目の片岡と専攻医になったばかりの尾﨑を指導、2025年度は山本、竹内、小川の3名の放射線診断専門医が、専攻医2年目の木原を指導しつつ読影しております。少数精鋭といえば聞こえはいいですが、日々奮闘しております。
臨床研修制度が始まって以来その研修先として選択されることも多く、この10年もほぼ全期間で研修医を受け入れ指導をしています。放射線治療医の阿部が赴任してからは放射線治療科でも指導していただけるようになりました。
そう、放射線科としてのこの10年の最大のトピックは、放射線治療棟が2019年5月に完成し、放射線治療専門医である阿部英輔が2019年8月に赴任したことで、放射線治療科が独立した診療科となったことです。放射線画像撮影および診断と同等の長い歴史をもつ当院の放射線治療に、はじめて放射線治療医が常勤することになり、治療の一つの選択肢として放射線治療を考慮しやすくなったのは当院にとって本当に大きなことです。
これからも放射線治療科をはじめとした各科と協力しながら当院の診療をよりよくすべく頑張っていきたいと考えております。

現在のスタッフ
麻酔科
麻酔科
麻酔科 石井秀明
当院麻酔科は、昭和59年10月に新潟大学麻酔学教室より赴任された益子和徳先生によって開設されました。その後の人事、手術室における麻酔管理、ペインクリニックの診療は80周年誌の通りです。
近年の教育活動として、当科は麻酔科専門医の育成のために、新潟大学医歯学総合病院麻酔科専門研修プログラムの専門研修連携施設(A)として、専攻医の研修を担っています。さらに、臨床研修指定病院として、毎年10名程の研修医を受け入れて、麻酔科の基本的な手技や知識などを修得できるように指導しています。
診療において、当院は日本麻酔科学会認定病院であり、麻酔科専門医が常勤しています。麻酔管理件数は年間3300件を超え、麻酔科医不足が常態化しています。年々増加する麻酔管理件数に対して、新潟大学医歯学総合病院等から麻酔科医を連日派遣して頂き対応しています。麻酔科医不足の改善が喫緊の課題であり、環境整備に取り組んでいます。
昨今、厚生連の経営改善の取り組みについて報道されましたが、安全に麻酔管理するために必要不可欠な医療機器の更新や新規購入が困難な状態が続いています。有限の医療資源を効率的に活用し、この難局を乗り越えられるよう日々努めています。
今後も、より安全で質の高い周術期管理をめざし、地域医療を担う責務を果たしていきたいと考えています。
歯科口腔外科
歯科口腔外科
歯科口腔外科 山賀雅裕
当院における歯科の沿革につきましては、80周年記念誌に掲載しましたように、昭和41年6月の開設から10年ほどの間の記録はほとんど残っていませんでした。その後、昭和51年4月1日より、新潟大学歯学部歯科保存学第一講座(現う蝕学分野)の関連病院として、常勤1名と医局からの週2、3回の出張医による診療体制が確立されて今日まで続いています。
この10年間は常勤医の交代や診療内容の変更はなく、外来での一般歯科治療が中心ですが、患者さんの多くは、基礎疾患の治療のために他の診療科も受診されていますので、口腔領域と全身の健康状態の関連を念頭に置いて診療にあたっています。また、入院中の患者さんの口腔ケアや入れ歯の修理、調整などでは、歯科衛生士が中心的な役割を担い、迅速な対応を心がけています。
地域の歯科医院からの紹介は、従来から、埋伏歯や智歯などの若年者の難抜歯と、抗凝固薬や抗血小板薬服用中の高齢者の抜歯がかなりの割合を占めていましたが、最近では、骨吸収抑制薬の長期服用例や、全身状態の把握が困難な超高齢者の抜歯依頼が増加しています。
院内他科からのコンサルトでは、外来、入院ともに、基礎疾患の治療中に歯の痛みや義歯の不具合などを訴えて歯科治療が必要となったケースと、がんの治療(手術、化学療法、放射線療法)に伴う合併症や有害事象の予防、軽減を目的とした口腔機能管理依頼が多数を占めています。
令和2年度から歯科衛生士が1名増員となりましたが、がん治療の長期化や実患者数の増加に伴い、当科の外来のみですべてのニーズに対応することが困難となっています。今後は、当院でがん治療を受けられる皆様が、地元の歯科医院で口腔機能管理を継続できるよう、連携を深めていきたいと考えています。
|
|
R1年 |
R2年 |
R3年 |
R4年 |
R5年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
新規患者数 |
849 |
836 |
759 |
753 |
777 |
|
周術期等口腔機能管理計画策定数 |
129 |
126 |
105 |
156 |
139 |
|
周術期口腔機能管理のべ件数 |
590 |
803 |
871 |
874 |
1.013 |
救急診療
当院の救急診療の現況
救急委員長 循環器内科 中村裕一
2015年~2025年の当院の救急活動を振り返る。
【概観】
長岡市の救急は、当院、長岡赤十字病院、立川綜合病院の三施設で三病院輪番体制を敷いている。三次を長岡赤十字病院が担当し、他の2病院は二次医療を提供しているが、高エネルギー外傷など救急隊が一見して判断できる傷病者以外はすべて搬送される。原則として長岡医療圏を対象としているが、魚沼地区、県央地区、柏崎地区からの搬送もあり、対象人口は35万人を超える。当院は輪番病院の一翼として「地域の医療は地域で守る」「当番日には断らずに診る」を合言葉に救急医療に取り組んでいる。毎月の救急外来利用者は900人強で、そのうち約3割が救急搬送例で、長岡医療圏の患者が9割を占める。救急搬送件数のうち内科系が半数で、整形外科、脳外科、外科をあわせると8割を超え、このうち約4割の患者が緊急入院している。
【当院の救急体制】
当院には救急科がなく、日中に救急外来に常駐する医師がいない。このため業務遂行にあたり多くの先生方にご協力をいただいている。平日日中の救急対応は、各科対応を基本としているが、診療科が定まらない場合には、研修医が日中救外当番の先生方にバックアップしてもらいながら診察している。当番日の休日・時間外は内科系・外科系医師1名ずつと、それぞれに研修医が副直としてついている。患者の多い休日日勤と準夜には3人目のフリー研修医を配置している。看護師は、救急外来専任の看護師を中心に外来看護師が当番日には3交代勤務で、非当番日は当直体制で勤務している。
【教育活動】
当院の救急医療の展開は研修医の力に負うところが大きく、彼らへの教育活動を精力的に行っている。毎日の研修指導のほかに、4月には救急蘇生法(ICLS)講習会、5月には1ヶ月かけて各科の専門医による救急モーニングレクチャー、12月にはJMECC(内科救急コース)も開催している。スタッフ対象のICLS講習会も定期開催しており、2025年には100回目の開催を果たした。HCUや5階東病棟など心臓急変の多い病棟では除細動・蘇生についての勉強会が定期開催されている。
【コロナ感染症と救急外来】
2020年1月から約2年半にわたり世界中を大混乱に陥れたコロナ禍はわが救急外来も見逃してくれなかった。救急外来は有熱患者の侵入門戸であり、コロナ禍ではあらゆる患者にコロナ感染者の可能性があった。通常業務が常に感染リスクと背中あわせで、自分や家族の健康が損なわれる恐怖があった。また、見逃して院内に入れてしまうと、クラスターを発生させ病院機能を停止させるリスクもあった。PPEを装着しながらこれらのストレスのなか頑張ってくれたスタッフの皆さんに、心から感謝したい。
【救急外来の課題】
当院の救急外来の課題の第一は人手不足だ。平日日中の急外当番(いわゆるサード番)は、従来内科医師が担ってきたが、内科医の減少のため2024年度から外科系の先生方にも参加していただいている。看護体制についても救急外来の人員配置ばかりでなく、内視鏡・放射線科などの救急機能を維持するために負担をお願いしているし、ご苦心いただいてもいる。
救急専門医の確保も長年の課題であるが、なかなか良いご縁に恵まれていない。
三病院体制の維持も曲がり角に立っている。立川病院の消化器内科閉鎖や小児科の輪番離脱があり、他の2病院の負担が増している。これについては、地域の人口動態や医師供給体制と地域医療再編、働き方改革など、さまざまな問題が複合しており、当院だけでは解決困難な課題と考えられる。長期的視点に立って長岡の将来の医療供給体制について考慮すべき時期がきていると思われる。
高度治療部
高度治療部(High Care Unit:HCU病棟)
高度治療部 循環器内科 中村裕一
2019年4月1日、3階東病棟に12床(個室4床 開放8床)の高度治療部(HCU病棟)が開設された。HCUは、内科系、外科系を問わず、重症・大手術後の患者に対し、24時間を通じ厳密に観察し、最新の先進医療技術を駆使した集中治療・管理を専門に行う部門である。これまで各病棟で行われてきた大侵襲手術の術後管理や、呼吸・循環・神経系モニタリングを必要とする症例の治療、人工呼吸器・血液浄化装置・補助循環装置を用いる患者の管理をHCUに集約し、医師・看護師に加え、理学療法士、臨床工学士、管理栄養士など多職種が参画することにより、当院で実現できる最高の医療・ケアを提供することを目的としている。
HCU開設の準備は、2005年の新築移転直後から水面下では企図されていたが、具体的な動きは2017年下半期から始まった。設置場所は当初術後患者の管理が需要の過半を占めることから、2階の手術室近くも考慮されたが、最終的に医局に近い3階東病棟を改修することになった。部屋割りが決まり、ベッドやモニタリング装置、レントゲン・エコーなどの資機材も選定され、工事が始まった。看護師の人選は開設半年前の10月に坂内看護師長を中心に開始され、12月には各病棟から2名が選任されHCUのスタートメンバーが確定した。各メンバーは各病棟の業務のうちHCUへ移管されるものを互いに教えあい共有するとともに、他病棟の業務に参加し経験を深めていった。終業後には勉強会が開かれ、各科の医師から疾患や治療、術後患者を看るうえでの注意点などについて講義してもらい知識を深めた。3月半ば過ぎに施設が完成すると、病棟内での動線を確認するなどして始動に備えた。
4月1日、開設初日の入室者は4名だった。いずれも術後患者で、恙なく翌日に退室できた。ただ、不慣れで急患に瞬発力よく対応するには不安あり、という状態だった。翌4月2日は救急当番日。この日も4人を収容し、AMIの緊急入院も一人いた。試練の1日でもあった。朝一番に劇症型心筋炎疑いの57歳の男性が心肺停止となって搬送されてきた。IABP PCPSによる循環サポート、人工呼吸器管理がおこなわれ、蘇生後の体温調節療法が必要な状態だった。“The 集中治療”という症例だったが、開設2日目でよちよち歩きのHCUには荷が重いと判断し、従来通り5階東の循環器病棟に収容することになった。HCU病棟としては忸怩たる思いであった。しかし、メンバーは皆この悔しさを忘れず、努力を重ね経験を積んで成長してくれた。今日では、院内の急変患者や機械的補助療法を要する患者など、重症例の多くをHCUが担っており、病院全体から頼りにされ、その期待によく応えてくれる存在になってくれていると思う。
近年の利用状況は安定している。年間の総入室者数は令和6年度は1394名だった。当初の予想どおり、術後と救急/集中治療患者の比率は2:1と、術後管理が多数派である。術後患者は約半数が外科で、整形外科、婦人科、呼吸器外科で約9割を占める。救急/集中治療患者は、循環器内科が4割強で、脳外科、外科、消化器内科を合わせて約8割となる。
開設当初、各病棟が持っていた知識・経験を持ち寄る形で動きだしたHCUだったが、近年はHCUからの全館に向けての発信も増えている。人工呼吸器からの標準的離脱プロトコルの導入がその代表例で、これには特定行為看護師が中心となって活躍してくれた。心血管作動薬や鎮静薬の標準化もすすめ、業務の効率化・安全性の向上に努めている。
HCUへの高度医療の集約化の結果、人工呼吸器、PCPS、透析などの高度な生命維持装置の管理、集中モニタリング、血管作動薬などを一般病棟看護師が経験する機会が減少した。これらのスキルに対する一般病棟看護師の不安や学習ニーズを埋めるために、今後はHCUでのローテーション研修を行うなど、学習の場としてのHCUの活用を考えてゆきたい。開設の目的、「当院で実現できる最高の医療・ケアを提供」をHCUから病院全体に広めてゆきたいと願っている。
看護部
—看護部長リレー
90周年目の看護部について ~惹きつけられる看護部を目指して~
看護部長(2025年4月~) 島川夏代
2025年4月、小千谷総合病院より異動にて横山氏から看護部長の任を引き継ぎました。創立90周年という節目の年を迎え、これまでの歴史とこれからの未来へ向けて看護部長としての重責を感じています。今回の記念誌の掲載においては、現在当院で勤務されている歴代の看護部長にも寄稿をお願いし、看護部長リレーとして掲載させていただくことにしました。
看護部は看護部長の島川の他に、副看護部長3名体制[五十嵐久美子(医療安全管理者)、岩根和子(業務・他職種連携・渉外・広報担当)、平澤陽子(教育担当:新人研修・キャリアラダー・特定行為研修等)]へ変更となり、ベッドコントロールは師長の輪番制とし、新しい体制でスタートしました。また、手術や救急医療などの高度かつ専門的な医療を提供する体制を評価する急性期体制充実加算の取得が開始となりました。地域の中核病院として、高度専門治療と救急機能を担う急性期病院であることを職員が誇りと自覚を持って働いていると感じています。
今の看護部が抱えている最も深刻な問題は要員不足です。6階西病棟を休床して450床の運用をしているのも看護要員不足の為です。離職を防ぎ、働き続けられる環境をつくるために赴任後、まずは看護部アンケートを実施し、現場の困っていることや改善に向けたアイデア、ご意見など多数の声を聞かせてもらいました。
その中でも認知症患者の対応に困っている声が最も多く、超高齢社会が進む中、急性期病院においても認知症患者の対応が求められていることがわかりました。認知症看護認定看護師を中心として、院内デイケア『すまいるマロン』を8月から開始しました。6階西病棟を利用し、週3回、14:00~16:00に体操や制作活動、レクリエーションなどのアクティビティを行い、楽しみながら生活リズムをつける取り組みです。身体的拘束最小化にも力を入れていますので、患者さんにとってもよい環境を提供できるよう継続していきたいと思います。看護師にとっても看護業務に専念できる時間ができ負担軽減につながればと思っています。
今後は、オムツを高吸収のアイテムに変更し、オムツ交換の回数を減らすことや、看護記録の負担軽減を図るためのDX化にも積極的に取り組んでいく予定です。更には希望する働き方ができるために、すべての病棟で希望者が2交替制夜勤をできるようにしていきたいと思います。労働人口が減少していく中で、自分たちの働き方を見直し、今よりも楽に仕事ができるように創意工夫しながらベッドサイドケアの充実を図っていきたいと思います。
7月以降、日本看護協会のデータベース(DiNQL)事業に本格的に参加を始めました。同規模病院との比較で他施設との違いや自施設の強みや弱みを把握し、病棟マネジメントや看護の質向上、質改善を図ることをねらいとし、今後データを有効に活用していきたいと考えています。
2040年を見据え、生産年齢人口の減少と超高齢社会が進む中、看護は人々の地域での療養生活を支える最も身近な存在として、今後ますます地域の中で役割を発揮していくことが求められていきます。看護部理念の「私だったら、私の家族だったら、どんな看護を受けたいかを考えて看護を提供する」を実践し、一人ひとりの患者さんを大切に、思いやりの心でその人らしく生きることを支える看護をしていきたいと思います。
これまでの看護部の歴史をつくりあげてきた歴代の看護部長の方々の想いを受け継ぎ、看護部理念や“3つのH”の看護を大切に継承していきたいと思います。私の使命として、働く職員を大切に、やりがいを持って生き生きと働ける職場環境をつくっていきたいと思っています。そして、スタッフから「この病院で頑張って働きたい」と思ってもらえるような惹きつけられる魅力ある看護部を目指していきたいと思います。

現在の看護部長室メンバー
看護部長としての2年間を振り返って
看護部長(2023年4月~2025年3月)
横山晶子
私は2023年4月より定年までの2年間、看護部長として任にあたりました。この節目の時期に看護部をまとめる立場で病院運営に関わることができたことは、私にとって大きな誇りであり、かけがえのない経験となりました。中越地域の複数病院、看護学校、そして厚生連本部での勤務を経て、14年ぶりに長岡中央綜合病院に戻ってまいりました。再びこの地で働けることに懐かしさを感じたとともに、より高度で専門的な医療提供が可能となっていることに大きな緊張と責任を感じたことを今でも鮮明に記憶しています。
着任した年の5月は、新型コロナウイルス感染症が2類から5類へと移行し、社会は「ウィズコロナ」へと歩みを進めました。しかし、医療現場では急性期離れがささやかれ、看護職員の確保が深刻な課題となっていました。当院においても例外ではなく、看護師が安心して働き続けられる環境づくりが急務であると痛感しました。
そこで私は、ライフスタイルに応じた柔軟な勤務体制の構築をめざし、変則2交代制夜勤や2交代制夜勤の導入を進めました。家庭や個人の事情に合わせて勤務を選択できる体制は、看護師ひとり一人の働きがいと定着率の向上につながると信じています。また、看護師の超過勤務時間の削減に向けて、モデル病棟によるイノベーション活動にも取り組みました。業務が多忙を極める中でも、現場の看護師たちは生き生きと工夫を凝らし、実際に超過勤務時間の削減を実現してくれました。その姿に深く心を打たれ、看護の力と可能性を改めて実感しました。この取り組みをさらに多職種を巻き込んだ大きな活動へと広げていきたいという思いもありましたが、課題は多く、残念ながら実現には至りませんでした。しかし、看護部の仲間たちが見せてくれた前向きな姿勢と挑戦の姿は、今後の病院づくりにおいても大きなヒントになると確信しています。
今、医療現場は人口減少や超高齢社会、物価上昇に追いつかない診療報酬など、厳しい状況に直面しています。このような中で、地域の皆様に愛され、信頼を得続けるためには、病院および看護部の理念、病院の機能と役割をひとり一人が理解し、自身の看護実践がどのようにそれとつながっているのかを意識することが何よりも重要だと感じています。
看護は、病気そのものに向き合うのではなく、人々の生活に寄り添い、支える営みです。病院90年の歴史の中で連綿と提供し続けられたものと思い、誇りを感じます。これからも、地域の皆様に信頼され、より良い看護を追求し提供し続けられるよう願っております。
創立90周年に寄せて
看護部長(2018年4月~2023年3月)
土田八重子
在籍中を一言で言うならば、看護師人生の中で波瀾万丈な5年間でした。
着任後は急性期病院としての役割を果たすため、HCU病棟開設が課せられていました。改修工事、医療機器やベッドの準備に始まり、人員配置では旧3階東病棟から他病棟への異動、HCU病棟への配置と看護職員にご協力いただき平成31年4月に開設となりました。HCU病棟運営も軌道に乗ったところ、「新型コロナウィルス感染症」の流行、感染症対策の母と言われるナイチンゲール生誕200年の年でした。感染症患者の受け入れのため病院長指揮のもと職員が一丸となって対応。看護部職員は懸命に患者様へ対応し看護部の力強さ、底力を実感しました。
コロナ渦においても、看護師特定行為研修、外国人技能実習生の受入、ワーク・ライフ・バランス事業、病院機能評価受審など、たくさんの事に取り組んできました。看護師の負担軽減、タスクシフト・タスクシェアに向けて、外部委員介入のワーク・ライフ・バランス事業に参加、多職種で話し合いの場を持ち検討できたことはタスクシフト・タスクシェアの一歩に繋がったと感じています。看護師の負担軽減対策として日勤看護師と夜勤看護師が区別できるように夜勤看護師は青色マスクを着用することにしました。現在も夜勤看護師は青色マスクを着用しています。先日ある副院長が青色マスク看護師に指示を伝えており「17時過ぎの指示は青色マスクでしょ」いう言葉を聞き、青色マスクが定着していることを嬉しく思いました。
看護部教育では厚生連看護部のめざす看護師像「地域ニーズに応えられる自律した看護師」に向け、キャリアラダーシステムを導入し看護師のスキルアップに取り組み看護実践力を高め、現在も継続されています。看護の専門性が高められ看護師の活躍の場が拡大していきました。
コロナ渦で疲弊し退職していく看護職員も多くいました。看護への思いを繫げたいと思い「3つのH Head(頭)・Hand(手)・Heart(心)の看護」を掲げました。多くの知識を頭に詰め込んで考える、思いやりの心を込めて患者様に手をあてる看護、日々実践している看護を言葉にしました。この看護に共感して就職してくださった看護師もいました。

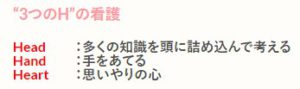
私事ですが、昭和・平成・令和と看護師人生を過ごしてきました。看護師を続けてこれたのは、たくさんの方々と出会い、支えていただいたおかげと感謝しております。この場をかりてお礼申しあげます。
長岡中央綜合病院の益々の発展、職員が明るく生き生きと働き続けられ100周年を迎えられるよう祈念しております。
「90周年に寄せて」
看護部長(2016年4月~2018年3月)
鈴木光江
2年間の三条総合病院勤務を経て当院で定年まで2年間を勤務させていただきました。脈々と受け継がれてきた良質な看護を継承していく責任を感じ緊張するとともに、初日には少しワクワクして廊下を歩いていたことも思い出します。
赴任した2016年はすでに2月に病棟部門で電子カルテが導入されており、6月の外来部門の稼働を受け完全電子カルテ化がなされました。患者情報の共有や伝達・記載ミスの減少・利便性の向上・業務の効率化など多岐にわたり大きな変革がもたらされました。幸いにも大きなトラブルもなく移行でき、看護師たちのパソコン操作適応力に感心しました。
一方で、病床稼働率は高率で推移し、在院日数短縮という命題の中、看護師不足の状況は変わらず業務は多忙を極めました。看護師達の健康面が大きな気がかりでしたが、毎日朝・夕の看護師長とのミーティングをもとに病床管理・人員調整を行う日々のやりくりの中で7:1看護基準が継続できたことは、看護師長達の協力あってのことと深く感謝しています。その姿には私自身が幾度も励まされました。
そのような折、2019年2月に待望の院内保育所「たんぽぽ」が開所しました。夜間保育も可能であり、託児先の心配がなく職場復帰に専念できる環境は離職防止にも寄与し、新たな人員確保の面からも非常に頼もしい存在でした。
医療をめぐる社会情勢の中で、病院と地域の更なる連携強化が求められたのもこの頃です。入院前から退院調整まで支援の明確化に向けて入退院支援看護師を配置するととともに、2018年の診療報酬改定を見据えて業務内容の検討を始めてみると、更に多職種との連携なくして実践できないと強く感じました。この頃、「全職種の横のつながりを大切にしよう」との院長からのイベント開催提案を受けて仮装綱引き大会を企画しましたが、これぞ我が長中の結束力・求心力を実感させられるものとなりました。各部署から大勢の参加があり、一時仕事を忘れた大きな歓声やあふれる笑顔を目のあたりにして、嬉しくも清々しい気持ちになったことも良い思い出です。
現在も再就職し短時間勤務をさせていただいております。出勤初日は、大好きな病院でまた仕事できることを嬉しく感じましたが、医療を取り巻く環境はますます厳しさを増していくようで、現在の勤務場所でも実感するところです。
当初の地域医療構想がターゲットとしていた2025年を迎えた今、更に15年後を見据えた新たな構想へ向けて次期診療報酬制度も変わると聞いております。人材確保・処遇改善や物価高への対応など、院長様を始めとして病院の舵取りには多大なご苦労がおありのことと思いますが、今後も長岡中央綜合病院が地域に信頼され愛される病院であり続けることを願っております。


90周年を迎えて
看護部長(2006年4月~2010年1月)
大桃啓子
80周年記念誌で編集に携わらせて頂き、当時は新潟医療センター勤務でしたが、微力ながら手伝わせてもらいました。一からの資料集めで多くの先輩方に協力して頂き、本当に感謝しています。
そしてあっという間に10年が過ぎました。
私は定年退職後、1年半して再就職し、総合案内で週4日3時間の勤務をしています。
その間メンバーも変わり、正面にカウンターが設置され、患者サポート窓口として加算もとれる様になりました。週1回のカンファレンスで問題共有し各部署との連携を大切にしてきました。
主に患者さんの相談対応、何科を受診したらよいか、相談事に対してのよろず相談所的役割をしています。
一番頼りにしていたのが総合診療科です。まだ一般的に広まっていなかった中、私たちも先生方に勉強会を開いて頂き、具体的な受け入れについて話し合いをしたりと、新たに勉強をさせてもらいました。総合診療医の退職により、2年前に廃止になってしまいました。以前に比べて多種多様な症状で悩む患者さんは確実に増えています。復活を強く望んでいます。
2020年にコロナ禍が始まり、大きな変化と我慢を強いられ、現在に至っていますが、一層の感染予防に気を付けて仕事をしています。
2021年に地域医療支援病院となり、役割が明確になってきました。直接来院の新患の患者さんを受け入れることができず、開業医と紹介しながらかかりつけ医を持つようお話しています。
案内をしていると何十年も前の患者さんから声をかけて頂き、古参になったものだと実感しています。
医療の進歩で目まぐるしく変わっていく現場でこそ、患者さんに寄りそい地域に愛され信頼される病院としてあり続けて欲しいと願っています。
教育体制
看護部教育体制の経過
副看護部長(教育担当) 平澤陽子
当院の病院理念は「地域の中核病院として皆様の健康を守る為良質で心温まる医療を提供し予防・保健・福祉活動を積極的に推進いたします」である。看護部理念は「私だったら、私の家族だったらどんな看護を受けたいのかを考えて看護を提供する」であり、看護部教育理念は「病院・看護部の理念に基づき『豊かな感性・高い倫理観・専門的知識・技術を身につけ、患者中心の看護ができる自律した看護職』を育成する」である。そのため看護部教育方針としては「高い倫理観をもち自律した看護職の育成」「専門的知識と看護技術、判断力に優れた看護職の育成」「患者中心のケアを実践できる看護職の育成」「組織の一員として役割を遂行できる看護職の育成」「自律的に学び自己研鑽できる看護職の育成」を掲げている。この方針の基、教育研修は、教育担当副看護部長、主任会、教育委員会が中心となり、師長会、記録委員会、褥瘡委員会、医療安全委員会、救急委員会、入退院支援委員会の協力を得て企画運営を行っている。
厚生連看護部教育理念は「地域ニーズに応えられる自律した看護職員の育成(ともに学びともに育つ)」である。厚生連看護部が目指す看護師像として
- 専門職として質の高い看護、やりがいのある看護を追求し、主体的に実践できる
- 患者を全人的視点で捉え、患者中心の看護が提供できる
- 多職種と連携し、組織の一員として果たすべき役割を自覚し、実践できる
- 対象を尊重し患者の権利の擁護を基本とした対応ができる
- 専門職として自己研鑽できる
を掲げている。本部教育委員会では、毎年外部講師を依頼し新人研修、看護倫理研修、リーダーシップ研修、看護研究発表会を行っている。社会情勢や医療を取り巻く環境の変化のスピードは年々加速している中、先を見据えた研修内容となっており、参加者は多くの学びを得ている。
専門職として生涯学習支援が推進される中、2021年3月新潟県厚生連看護部は、専門的な能力の発達や開発、臨床実践能力、管理的な能力を段階的にキャリアアップしていくキャリアラダーシステムを導入した。これを受け、当院は各部署のクリニカルラダーと全部署共通のキャリアラダーを作成し運用を開始した。そして、目標管理シート、成長エントリーシート等個人のキャリアを可視化できるポートフォリオを作成し、キャリアラダーと連動した個々のキャリアアップを推進している。キャリアラダー認定を受けるための研修は、ラダーレベル別研修やSQUE・学研eラーニングを活用し、その時代に合った内容へブラッシュアップされてきた。実践レポートも自身の行った看護を振り返り考察していく内容から、自身の組織貢献について述べることができるようステップアップできる内容としている。2024年までのキャリアラダー認定者数はレベルⅠ 70名、レベルⅡ 42名、レベルⅢ 23名、レベルⅣ 3名となった。
また、2024年より看護管理者の計画的なキャリア形成と育成を支援するため、マネジメントラダー・コンピテンシー評価を導入した。マネジメントラダーは日本看護協会版(2019年)を引用し「組織管理能力」「質管理能力」「人材育成能力」「危機管理能力」「政策立案能力」「創造する能力」としている。合わせて、行動を裏付ける思考パターンを含み総合的な能力を評価するコンピテンシー評価の導入を検討し、東京大学医学部附属病院看護部(編集:武村雪絵)「看護管理に活かすコンピテンシー」の評価表を引用し作成した。主任から看護部長までが自身の行動の指針となることや、振り返りから行動変容につながり、組織貢献できるツールであると考えている。しかし、キャリアラダーシステムも同様であるが評価をする者によって視点に違いがあり、評価方法の標準化や評価者の育成が今後の課題となっている。
新人看護師教育体制はプリセプター制をとっており、主に3年目以上の経験をもつ看護師がプリセプターの役割を担っている。プリセプターは、新人看護職員へのリアリティショックを最小限に留め、職場適応への支援を行う。役割を担う者へは3か月、6か月、12か月でフォローアップ研修を行い、情報共有や支援方法の検討から学びの場となっている。実地指導者は、OJTで直接指導し看護技術の評価や学習を支援する役割を担っている。プリセプターや実地指導者が不在の時は、スタッフがそれらの役割を代行している。主任・師長は自部署のスタッフ、プリセプター、実地指導者へ助言、指導、支援を行い、新人看護職員教育体制を整えている。
中途採用者支援体制は、令和元年、中途採用看護師が、当院のシステムやルールを理解して早期に職場適応できるよう「中途採用看護師支援マニュアル」が作成された。オリエンテーションする内容や支援スケジュール、夜勤開始前チェックリストを盛り込んだ。年々助勤看護師や応援看護師が多くなり、令和5年「助勤看護師、応援看護師支援マニュアル」を作成した。内容をブラッシュアップし、電子カルテのオリエンテーション内容をより細かく丁寧にできるものとした。中途採用者、助勤者、応援ナースのナレッジを理解し、理解度に応じた支援を行っていくことで、早期にチームの一員として働くことができる結果となっている。
看護補助者との協働においては、看護師の指示のもとで業務を行うという法的位置づけを遵守しながら、看護チームの一員としての役割と責任を果たすことが必要となった。看護補助者業務に必要な基礎的な知識・技術を習得するための院内研修の実施や、看護師に対して看護補助者活用推進に向けた研修も必須となり、計画的に実施している。当院は2024年11月「看護補助者キャリアラダー活用ガイドブック」を作成した。キャリアラダー構成項目は適切で安全な介護を提供する「介護実践能力」、組織の理念を理解し自部署の目標管理に貢献できる「組織的役割遂行能力」、看護チームで働く一人ひとりが意識し内省するための「社会人基礎力」の3つの大項目とした。看護補助者個々のキャリア発達をサポートしていくことで、看護・介護の質向上につながり、看護部組織が活性化していくことを期待する。
2025年公益社団法人日本看護協会は「看護の将来ビジョン2040~いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護~」を提言した。看護が目指すものとして「その人らしさを尊重する生涯を通じた支援」「専門職としての自律した判断と実践」「キーパーソンとしての多職種との協働」の3つを目標に掲げている。「その人らしさを尊重する生涯を通じた支援」は、人々の個別性を重視しその人にとって最適な支援を行い、その人らしく最後まで過ごせるよう対話を行って行くこと、そしてそのご家族に対するグリーフケアを支援する教育を盛り込む必要があると考えている。「専門職としての自律した判断と実践」では、限られた人数で質の高いケアを提供していくためにアセスメント能力をさらに向上していく必要があると考えている。新人教育から、フィジカルアセスメント・ヘルスアセスメントの経験知を増やしていくことで、対応能力の向上や全人的に捉える視点を養っていく必要がある。このように、看護という専門職の役割をしっかり認識し、実践できた上で、「キーパーソンとしての多職種との協働」において、患者を中心としたコーディネーターの役割を担えることが重要である。
これからの時代は看護を開発・創造していく力が必要になると考える。看護師一人ひとりが考え、意見を出し合い、変革へ挑戦していく姿勢をもち、長岡中央綜合病院の発展に貢献することを願っている。
外来
外来
看護師長 林智子
長岡中央綜合病院は、開院以来90年にわたり、地域の皆さまと共に歩み、安心と信頼の医療を提供してきました。外来部門では、34診療科の外来診療に加え、救急外来、内視鏡室、放射線科などの検査部門を備え、予防から高度な治療まで幅広く対応しています。また、健診センターにも看護職員を配置し、健康維持や早期発見にも力を注いでいます。
外来受診者数は1日平均1,200名を超え、医療の進歩と入院期間の短縮化に伴い、従来は入院で行われていた治療や検査の多くを外来で受けられるようになりました。私たちは、患者さんが通院しながらも安心して診察・検査・治療を受けられるよう、多職種と連携し、円滑で質の高い医療提供に努めています。
当院は「紹介受診重点病院」「地域医療支援病院」「がん診療拠点病院」としての役割を担い、地域の診療所や病院と密接に連携しています。がん看護外来では、がん患者さんやご家族の不安を和らげ、治療に関する支援を行う専門的な看護を提供しています。さらに、2023年には「がんゲノム医療連携病院」に指定され、最新の医療にも積極的に取り組んでいます。
救急医療においても、年間4,000台を超える救急搬送を受け入れ、長岡医療圏の二次救急輪番体制に協力しながら地域の安全を守っています。2023年には救急救命士が外来に配属され、救急体制のさらなる充実を図りました。新型コロナウイルス感染症が流行した際には、発熱外来を立ち上げ、一般外来と動線を分けて感染症患者の診療を行い、地域の医療を守る役割を果たしました。
現在、外来看護部門には109名の職員が勤務しており、救急救命士2名と2025年からは主任看護師4名を配置し、より専門性の高い看護を提供してまいります。
私たち外来看護師は、スローガンである
「地域の皆様から信頼される安心・安全な医療提供と優しい看護」
を胸に、これからも地域の皆さまの健康と暮らしを支える外来医療を実践してまいります。


透析センター
透析センター
看護師長 小林良子
当院透析センターは昭和47年6月、血液透析治療目的に開設され、スタート当時の残っている記録をみると患者数は1名、のちに4名に増えたようです。その後、昭和58年に腹膜透析治療分野を加え、平成10年から夜間透析を開始したという歴史があります。
スタッフは、医師2名、医療クラーク1名、臨床工学技士7名、看護師スタッフ23名、看護助手1名です。糖尿病重症化予防フットケア研修受講者1名、腎臓リハビリテーション講習会受講者2名がおり、専門的視点のもとカンファレンスを行いながらその患者さんに合ったケアが行えるよう、チームワーク良く頑張っています。
現透析センターの状況を記すと当院維持透析患者74名、血液・腹膜透析併用患者6名、腹膜透析患者15名(うちカテーテル埋め込み済5名)、日中は月~土曜日、夜間透析を月水金に、感染症などで隔離が必要な方の対応を火木土の午後に行っています。腹膜透析は月・火曜日の午後から診察をしています。
昨年度透析導入患者は29名、当院の専門性や市内救急体制への参加から、他院で維持透析をされている方の入院中の透析管理を69名受け入れました。透析治療に加え、持続的血液濾過透析・単純血漿交換・エンドトキシン吸着療法・シャントエコーと多岐にわたった治療を担当しています。
透析は終わりなく一生続く治療です。風邪をひいたから、今日は気分が乗らないからといって透析を休むこともできません。患者さんの辛さに寄り添い、水分・食事の制限を守りながらも快適に生活できる方法を一緒に考えています。透析に通院されている方も高齢化が進んでいます。1人で通院が難しくなった透析患者さんの通院手段について相談したり、皮膚状態や足の観察、透析中でも行える運動を可能な方は取り入れています。
また、透析終末期、人生の最終段階において患者さんはどのように過ごしたいのか、患者さん、ご家族と今後を見据えた話し合いの「事前指示書」に少しずつではありますが取り組んでいます。実際に透析をしている方だけでなく、透析を始める前の患者さんへ血液透析、腹膜透析どちらがいいのか、その方のライフスタイルに合わせた透析が選択できるよう一緒に考えアドバイスを行う「療法選択外来」も行っています。
今後も私たちスタッフ一同、『長岡中央綜合病院の透析センター』としての自覚と責任をもって治療・看護・処置に携わっていきたいと考えています。

手術室
手術室/中央滅菌室
看護師長 小熊綾子
手術室と中央滅菌室は、2階にあります。手術室10部屋+結石破砕室1部屋の11部屋と回復室、そして器械の洗浄・滅菌業務を行う重要な役割を担う中央滅菌室と連なった構造となっています。また、全手術室の外側に回収廊下が設置されていて使用済みの器械を速やかに洗浄室へ運搬でき、清潔/不潔区域がきちんと区切られた環境で安全に患者様を受け入れられるようになっています。
手術は、先進的な技術の進歩によりオープン手術から内視鏡手術へ変わり、ナビゲーションシステムを活用した手術等、手術方法も大きく変化してきました。そのため、1つの手術を行うには医師・看護師・臨床工学技士・放射線科技師等の他職種との連携が不可欠です。
安全な手術を提供するために職種を越え、協力して業務に携わっています。
当院は、13科の診療科手術に対応し、がん拠点病院であるため多くのがん患者様の手術や人工関節手術などの整形外科手術を数多くおこなっています。件数は年間5000件を超えており、年々全身麻酔での手術件数が増加傾向となっています。また、緊急手術にも対応しています。
私たちは、病院の理念にもある『良質で心温まる医療を提供する』ために個々のスキルを向上させ、チームで協働し地域の患者様へ侵襲を最小限にし、早期回復できるよう取り組んでいきます。毎年、年末に手術室で1年間安全に手術ができた感謝と安全祈願のために『メス納め』を開催しています。安全なくして安心はありません。これからも患者様により寄った安全で安心できる医療、看護を提供していきます。



メス納め
HCU病棟
HCU病棟
看護師長 高野祥子
2019年4月に高度治療室(High Care Unit:HCU)が開設され、今年度で7年目になります。病床数は12床(個室4床・オープン病床8床)です。
診療科を問わず、重症度が高く高度な治療や看護ケアが必要な患者様、全身麻酔後の患者様、緊急入院、病院内の急変患者様の受け入れを行っており、月平均100~120人、年間およそ1400人前後の患者様を受け入れています。
看護部の理念「私だったら 私の家族だったら どんな看護を受けたいのかを考えて看護を提供する」を基に、HCUの看護方針「寄り添い、応える看護を提供いたします」を実践しています。HCU病棟は4対1の看護体制で特定看護師も在籍しており、24時間集中的な治療とケアを行っています。一般病棟とは違う特殊な環境であり、患者様が安心して安楽に過ごせ、1日でも早く一般病棟へ戻ることができるように、個別性のある急性期看護を行っています。
緊急入院され、生命の危機にある患者様や、治療の選択を迫られる患者様・ご家族様には、医師の病状説明に同席させていただき、ご家族様の思いを傾聴し、治療方針の選択の支援や精神的なケアを行っています。
予定手術の患者様には、HCU看護師が前日に術前訪問を行い、病棟の構造や手術の流れを説明し不安の軽減に努めています。
HCU病棟には専従の理学療法士が配置され、入室早期からリハビリ介入を行いADL低下予防やせん妄予防に努めています。また、栄養士が介入し早期に栄養を開始できるように取り組んでいます。看護師やリハビリ、栄養士で連日多職種カンファレンスを行い、時には各認定看護師の介入のもと、患者様の回復に向け医療チーム一丸となってケアを行っています。
HCU病棟には様々な医療機器を使用している患者様が入院されています。そのような患者様には、臨床工学技士が設置・点検を行うことで高度な医療が提供できています。
緊張が常に絶えないHCU病棟ですが、これからも医師・看護師・理学療法士・臨床工学技士・栄養士・看護補助者・認定看護師・入退院支援看護師等の多職種と協働しながら、患者様が早期に回復できるように急性期看護を提供していきます。

4階東病棟
4階東病棟
看護師長 片桐美奈子
4東病棟は、開設当初より小児科・新生児治療室・婦人科を担ってきましたが、地域の医療ニーズに応じて役割を広げながら発展してきました。現在は腫瘍内科・呼吸器内科を加えた混合病棟として、幅広い年齢層と疾患に対応しています。
小児科・新生児治療室では、感染症や慢性疾患の治療に加え、早産児・低出生体重児の専門的ケアをおこなっています。食物アレルギーの負荷試験では安全性を重視しながら日帰りで実施できる体制を整備しています。喘息や気管支炎では標準化された治療パスを導入し、医師と看護師が連携のうえ、早期にご家庭や学校に復帰できるように支援しています。新生児治療室では、状態が不安定な赤ちゃんに対して、専門的知識と技術を持つ看護師が常時ケアにあたり、緊急時にも迅速に対応(SIPAP装着や救急搬送など)ができるように、日々研鑽を重ねています。近年、新潟県の出生率は2015年の約1.44から2024年には1.14へと低下しており少子化か進んでいます。社会環境が変化する中で、地域の子どもたちの命と成長を支える役割の重要性をあらためて感じながら日々の看護にあたっています。
腫瘍内科においては、化学療法・分子標的治療・免疫療法など多様ながん治療に対応しています。当院は令和5年より「がんゲノム医療連携病院」に指定されており、患者さん一人ひとりの体質や遺伝子特徴をふまえた、最適な治療が選択できるように支援しています。看護師は治療の中で感じやすい不安や辛さらが少しでも和らぐように、そして患者さんが日々、療養しながら生活の質が維持できるように個別性を重視した支援をさせて頂いています。また緩和ケアチームや多職種と協働しながら、苦痛を最小限とし安心して治療に向き合える環境を整えています。
呼吸器内科以外にも整形外科をはじめ、さまざまな診療科の患者さんも入院されています。ご高齢の方が治療を終えたあとに安心して日常生活にもどれるよう、医療ソーシャルワーカーやリハビリスタッフなど多職種と力を合わせて支援をおこなっています。患者さんとご家族の思いを大切にし、カンファレンスを重ねながら退院後の生活を見据えたサポートを心がけています。
私たち4階東病棟は新生児から成人まで幅広い患者さんに寄り添い安心していただける看護をお届けしています。病院・看護部理念に基づき、地域の皆さまに信頼される病棟であるために、スタッフ一同これからもより良い医療と看護を提供できるよう努めてまいります。

4階西病棟
4階西病棟
看護師長 横山智美
4階西病棟は産婦人科と乳腺外科を主科とする病床です。40床の女性のみの病棟で、そのうちの3床は陣痛開始から産後回復まで過ごせるLDR(Labor Delivery Recovery)になります。令和4年より乳腺外科が当病棟に新たに加わりました。
婦人科・乳腺外科では手術目的の方、化学療法や放射線療法の手術後の追加療法を受ける方、緩和ケアや終末期を迎える看取りのケアを行っています。昨年度の婦人科手術は454件、乳腺外科手術は209件でした。女性特有の手術後のホルモンバランスの変動やそれに伴う身体的・精神的な不調といった多様な心理的影響に対しても寄り添った看護を提供しています。また地域がん診療拠点病院として乳がん認定看護師、化学療法認定看護師の協力を得て、個々の状態に合わせた指導を行い入院患者さんやご家族の方が安心して治療に望めるように対応をしております。
当院は地域周産期母子センターの役割も担い、近隣の病院・産院からの母体搬送の受け入れをしています。昨年度の分娩件数は359件で、10年前の年間1000件に比べると、この10年でかなり減少をしていますが、その一方で帝王切開は10%増加している傾向です。
昨今は心理的、精神的不安定な妊婦さんや育児サポート不足、社会的ハイリスク妊婦さんが年々増加している状況です。少子化による分娩件数の減少に伴い、今年度より背中からの硬膜外麻酔を行うことで痛みを和らげる無痛分娩や、出産直後のお母さんと赤ちゃんが入院して体調の回復や育児の不安解消のため助産師より専門的サポートが受けられる産後ケア入院が開始となりました。また生後間もない新生児の姿を記念して撮影するニューボーンフォトが導入予定となります。食事につきましても、管理栄養士と相談しながら、産科食の見直しを行い褥婦さんに快適な入院生活ができるよう取り組んでいます。
出産は人生の一大イベントです。どの方にも「この病院で産んでよかった」と思って頂けるケアを目指し、安心して産み育てていくための地域との切れ目ない支援体制の整備にも力を入れ関わっています。スタッフ一同「1人1人の想いに応える看護」を目指し頑張って行きたいと考えております。
5階東病棟
5階東病棟
看護師長 金内里恵
創立80周年に当たる2015年当時、泌尿器科・循環器内科・血液内科の3科混合病棟だった5階東病棟は、同年に泌尿器科が7階西病棟へ移動し、一時期は総合診療科の担当病棟として機能しましたが、2023年3月の総合診療科終了を経て、現在は循環器内科と血液内科の混合病棟として運営されています。
80周年記念誌の中で、当時の看護師長・土田八重子師長が「この記念誌が発行される頃には、ICU・CCUが増設され、急性期病院としての役割がより果たされ、看護師が生き生きと看護実践していることを願っています」と記しています。その言葉通り、2018年にはHCU病棟が開設し、重症かつ緊急性の高い患者はより専門的なケアを受けられる環境へと移りました。HCU病棟での集中治療を終えた患者を5階東病棟で受け入れる流れが確立され、5階東病棟の看護は、緊迫した時間の中で命と向き合う看護から急性期を乗り越えた患者の回復を支えるケアや、慢性疾患と共に生きる方々の生活に寄り添う看護へと役割が変化しています。
超高齢化社会の進行により循環器疾患や血液疾患の患者も高齢化が進み、高齢独居世帯や社会的背景に課題を抱える患者が増えています。そして、当病棟に入院する患者の多くが退院後も疾患と共に生きていかなければならず、症状の再燃や悪化、合併症予防のための指導や支援が必要不可欠です。慢性心不全の繰り返される症状の再燃や、化学療法の副作用などにより、徐々に日常生活動作が1人で行えず弱っていく患者も多くいます。患者一人一人がその人らしく生活できるよう、私たち病棟看護師は、退院支援看護師や医療ソーシャルワーカー、リハビリ担当者、栄養士、薬剤師、地域医療福祉関係者など多職種と連携し退院支援にあたっています。
これからも5階東病棟は、循環器内科・血液内科の専門性を活かし急性期病院としての役割を担いながら、急性期・回復期から慢性期、そして在宅へと繋げるためのケアの質を高めていくことが必要だと考えます。社会的背景に配慮した支援や指導のできる看護師の育成やチーム力の向上を目標に掲げ、日々取り組んでいきたいと思います。
90周年を迎えた今、私たちはこれまでの歩みを胸に、これからも一人ひとりの命と暮らしに寄り添う看護を続けてまいります。

5階西病棟
5階西病棟
看護師長 平沢芳子
5階西病棟は2005年新築移転後より呼吸器センターとして呼吸器内科、呼吸器外科が共に関与する疾患に対して迅速な治療を行い、あらゆる呼吸器疾患に対して専門的医療を提供してきました。しかし、2020年コロナ感染症が拡大し、当院もコロナ感染症患者受入れのため、5階西病棟はコロナ病棟となりました。なので、5階西病棟での直近10年間に起こった最大の出来事はコロナ病棟での取り組みだと思います。未知のウィルスへの不安の中、コロナ病棟立ち上げから患者受け入れと、当時のスタッフの皆さんのご苦労は計り知れないものだったと思います。
コロナ病棟立ち上げのため呼吸器内科のメイン病棟は6階西病棟となり、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科の混合病棟となりました。私は6階西病棟に2022年に配属され、6階から5階西病棟へのお引越しと共に移動して現在に至ります。ですので、私にとっての5階西病棟での一番の出来事と言えば、6階西病棟の診療科が丸ごと5階西病棟に引っ越しをしたことです。コロナ感染症も5類となりコロナ病棟はクローズとなりましたが、呼吸器内科としては重症化したコロナ肺炎患者の受け入れ対応が予測され、病床の半分を陰圧管理できる5階西病棟を有効活用する事となり、2023年6階西病棟から5階西病棟にまるごと大移動を行いました。通常業務の中、多職種の方々の協力で患者さまを安全に移動することが出来ました。病棟ごとに病床の作りが幾分違うので、物品の配置など移動してすぐにスムースに業務ができるように事前の準備、患者さまも誰をどの部屋に移動するなど当日の采配まで非常に大変だったなぁと思い出します。
もうひとつの大きな変化といえば、耳鼻咽喉科の体制が変わった事ではないでしょうか。耳鼻咽喉科は長きにわたって1人医長で外来、入院、手術を行っていましたが、2020年~医師数が増え治療内容も多岐になりました。現在は医師4名となり、中越地区の頭頚部がん治療の拠点病院となっており、悪性疾患を中心とした手術や放射線治療、抗がん剤治療を行っています。週3日、年間200件近くの手術を行っています。苦痛症状に対しては緩和ケアチームと連携しその人らしく過ごせるように支援しています。
2023年度からの2年間の取り組みで『チーム力を高めて楽しく働き、患者さんの笑顔の病棟』という自分たちのありたい姿を目的に挙げフィールドイノベーション活動を行いました。その効果として、部署全体での協力体制やコミュニケーションが向上し、スタッフ間の関係性、お互いを思いやり、声を掛け合う姿勢が増えています。チーム力だけでなく、看護実践力の向上にも繋がっています。この活動の灯を消さぬように、今年度も部署目標に挙げ継続しています。心温まる良質な看護を提供できるように、これからも頑張ります。
6階東病棟
創立90周年を迎えて
看護師長 小林洋子
創立80周年から10年、医療が進歩したように6階東病棟は変化しました。他の病棟は単科から混合病棟へ変化しましたが、6階東病棟は変わらず整形外科の単科の病棟で骨や関節、筋肉・靭帯・神経といった運動器の疾患や外傷(けが)の治療、機能回復を専門とし、主に手術治療を目的とする病棟です。
小児から高齢者まで幅広い患者様が入院されます。手術件数は年々増加しており、今では1500件/年を超える勢いで手術治療が行われています。時には50床のベッドでは足りず、緊急入院や予定入院を受け入れるために患者様とその家族に協力を得ながら、他病棟に移動していただき治療の継続をお願いしています。協力していただいた患者様には感謝申し上げます。
医療の進歩で、今まで以上に専門性の高い手術治療を中心とする病棟に変化しました。急性期病院であることから、入院期間が比較的短期間であり近年は、平均在院日数が12日程度です。私たち看護師は、周術期管理として、手術を受ける患者様の全身管理や疼痛コントロール、創部の管理を行うとともに、運動機能が制限された患者様に自立に向けた日常生活の援助を理学療法士や作業療法士と連携し、早期離床や歩行訓練など安心と安全な看護を提供しています。
2022年から積極的に退院調整に取り組み始めました。以前は決められた曜日で術後のリハビリ状況を共有することが目的で主治医・看護師・理学療法士でリハビリカンファレンスを行ってきましたが、治療を受けた患者さん・ご家族が手術後に安心して住み慣れた地域で生活ができるように新たに退院支援看護師をメンバーに加え、多様な専門職が連携してサポートできるように多職種カンファレンスとして成長しました。退院支援看護師が窓口となり、地域のケアマネージャーや施設担当者と連携することでよりスムーズな退院を提供することができています。
2023年からは二次性骨折予防への取り組みを開始しました。二次性骨折予防とは、大腿骨近位部骨折など骨粗鬆症が原因で起こる骨折をした患者様に対して、再び骨折すること(二次骨折)を防ぐための取り組みです。6東病棟にも骨粗鬆症マネージャーである看護師が1名誕生し、病棟看護師への知識習得に向けた取り組みや医師や薬剤師、看護師などの多職種連携によって行われる骨折リエゾンサービスの提供を担っています。転倒予防や食事指導を病棟看護師が患者様やご家族に生活指導を行い、日常での骨折リスクが回避できるようにサポートしています。
これからも、患者様が安心して医療を受けられるよう、チーム一丸となってより良い医療の提供に努めてまいります。

6階西病棟(休止中)
休止中
7階東病棟
7階東病棟
看護師長 松本昌子
長岡中央病院に脳外科・神経内科病棟が開設されたのは、旧病院の時です。それから早39年になります。当時を知っている人はほとんど院内にはいません。脳外科・神経内科から始まり、呼吸器外科・胸部外科の混合病棟であったと思います。
今現在、脳外科、神経内科、血管外科、呼吸器外科、眼科の混合病棟になり、病床数は50床です。脳神経外科は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳腫瘍などの患者様が入院されています。神経内科は、脳梗塞、神経難病であるALS、パーキンソン病などの患者様が入院されています。血管外科は閉塞性動脈硬化症、透析に必要なシャント作製や狭窄に対する治療などで入院される患者様、呼吸器外科は、気胸、肺腫瘍などの患者様、眼科は白内障、緑内障、網膜剥離などで入院される患者様、本当に多種多様な患者様が当病棟には入院されてきます。そのため、様々な専門的な看護を提供をしています。
看護体制は7:1看護で看護補助者含めて37名のスタッフで看護を提供しております。
早期の退院を目指して、医師、看護師、看護補助者などが協力し、治療や看護を行っています。多くの医師がいますが疲れている時でも、笑顔で接してくれ、本当に助かっています。看護師も20代から50代まで幅広い看護師がいますが、先輩は本当に後輩の面倒をよく見て一緒に考え看護を提供しております。
忙しいなかでも、患者様をどうしていったらよくなるかを考え、リハビリや栄養科、ソーシャルワーカー、退院支援の看護師と情報共有を行っております。
患者様が安全に入院生活を送るためには、様々な危険予知をしていきながら、日常生活援助を行っていく必要があります。日々カンファレンスをし、安全な療養環境の実現を目指しています。看護師や看護補助者などの協働とコミュニケーションが大切だと思います。認定看護師から助言を得たりすることもスタッフの意識の変化になり、「どうしたらよいのか?」と考える日々が、勉強につながっていると思います。
今後も高齢化は進み、認知症患者の入院も増えてくる中で、地域としてACPの取り組みが本当に必要です。それは、医師の病状説明後に、患者様やご家族が、説明の内容をきちんと理解し、納得して方向性を決めることができているのか?と考えることがあるからです。看護部の理念にもあるように、もし「自分だったら・・自分の家族だったら」が考えられる看護の実践に努めて行かなくてはいけないと感じております。そのためには、私たち病棟スタッフは、患者様、ご家族との信頼関係を築いて行く必要があります。そして、患者様が安心して入院生活を送ることができるように努めていきます。
7階西病棟
7階西病棟
看護師長 板屋綾子
2018年10月3階東病棟(腎臓内科・代謝「内分泌・糖尿病」内科)がHCU開設のために閉鎖されました。病棟編成により腫瘍内科が4階東病棟へ、腎臓内科、代謝内科が7階西病棟へ移動し泌尿器科と眼科の混合病棟になりました。その後眼科が7階東病棟へ移動し、現在は泌尿器科、腎臓内科、代謝内科・耳鼻科(周手術期を除く)48床の混合病棟です。
病棟スタッフは師長1名、主任2名の看護師31名、看護補助者の介護福祉士4名、看護クラーク1名、医師クラーク1名、ナイトアシスタント1名の38名です。医師は泌尿器科5名、腎臓内科2名、代謝内科3名、耳鼻科4名です。
2チームで固定チームナーシング体制をとっています。Aチームは腎臓内科、代謝内科、Bチームは泌尿器科を担当し、耳鼻科は両チームで担当をしています。
腎臓内科は慢性腎臓病、ネフローゼ症候群の疾患が多く、透析療法が必要な方や腎臓病の教育入院の方の看護を行っています。腹膜透析導入の際には退院前・退院後訪問を行い、在宅での状況を確認し、患者様が退院後困らないように支援をしています。
代謝内科は糖尿病、電解質異常、内分泌疾患の患者様がいます。糖尿病の方には自己血糖測定、インスリン注射ができるように、糖尿病看護認定看護師と糖尿病療養指導士が中心となり指導を行っています。
泌尿器科疾患では、尿管結石、前立腺肥大症、腎盂腎炎、尿路感染等の良性疾患から腎癌、膀胱癌、前立腺癌などの悪性疾患の方がいます。手術など急性期ケアから化学療法、終末期ケアまで幅広い看護を行っています。
耳鼻科は喉頭癌、中咽頭癌などの化学療法、放射線療法の患者様に対し、治療中の苦痛・疼痛の緩和に努めています。
2025年7月よりリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算算定病棟に指名され、リハビリ専従が2名病棟に配置されました。多職種でリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料に係る計画書を作成しています。毎週火・金曜日は多職種でのカンファレンスも行っています。
またクリニカルパスを積極的に取り入れ、看護の質の標準化・効率化を図っています。毎日予定入院が5~6人、月・水・木曜日は泌尿器科手術が2~6件、化学療法が平日2~4名あります。短期入院が多く、病棟稼働率、回転率も高い病棟ですがスタッフのコミュニケーション、チーム間の応援体制、多職種連携のとれた笑顔あふれる、とても明るい病棟です。
看護学生の実習病棟としても選ばれることが多く、系統外の学校からも実習生が来ます。学生からは「7階西病棟は笑顔でコミュニケーションがとれており、患者へのケアやご家族への対応も笑顔が印象的であった。」「忙しい中でもスタッフが声をかけあい、コミュニケーションがよくチームで看護をしていることを学ぶことができた。」と学びの言葉をいただきました。
これからも患者様が早期に退院し、安心して日常生活に戻れるよう多職種と連携し、看護部の理念:『私だったら、私の家族だったらどんな看護を受けたいかを考えて看護を提供する』を大切に笑顔で看護を提供していきます。
8階東病棟
8階東病棟
看護師長 中島麻美
8階東病棟は消化器外科と形成外科の混合病棟です。外科では食道・胃・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓・乳腺の疾患の手術、化学療法、放射線療法を行う患者さんの看護を行っています。形成外科では乳房再建術・難治性潰瘍治療・軟部腫瘍摘出術などの患者さんの看護を行っています。
今年の春に他病棟から移動してきた私の病棟についての印象をいくつかお伝えします。
まず消化器外科についてですが、私が学生や新人の頃から勤務されている医師もいらっしゃいますが、年齢を感じさせることなくお元気で驚いています。外科は手術件数も多く、長時間の手術もあります。予定の手術件数も多いですが緊急手術も追加で行われている現状があります。入院と手術の予定をみながら円滑に手術や治療が行えるようにベッドコントロールをするのが私の仕事の一つですが、まだまだ不慣れで苦労しています。
また、ストーマ造設をする患者さんが多いことに驚きました。同時期に10名近くのストーマ患者さんが入院されていたこともありました。装具選択や指導の場面では、看護師の知識と経験がとても重要になってきます。
形成外科では繊細な手術や処置が行われている印象です。そんな繊細な創部ですが、認知力が低下している患者さんにガーゼ-を剝がされてしまうということも多々あります。疾患の影響で治癒するまで時間がかかり、自宅で処置を継続していただくための指導も必要になります。
8東病棟の看護方針は「優しく ゆきとどいた ケアを提供する」となっています。患者さんやご家族は手術や治療・退院後の生活に様々な不安を持たれています。患者さんやご家族の思いを受け止め、個々に合わせた丁寧な関わりを心がけています。外科も形成外科も高齢の患者さんが増えています。患者さんの退院後を見据えた退院調整にも力を入れています。
毎日慌ただしいですが、スタッフ間でコミュニケーションを取り合って、患者さんやご家族が安心して過ごせるような看護を提供していきたいと考えています。

8階西病棟
8階西病棟
看護師長 田邉朋美
厚生連長岡中央綜合病院の最上階の西病棟が消化器病センターの消化器内科病棟です。
東病棟の消化器外科と共に消化器疾患全般に渡る治療、検査に携わっています。
構成メンバーは、医師10名・看護師30名・看護補助者5名・看護クラーク1名・ナイトアシスタント1名・医師クラーク1名と研修医や病棟薬剤師など総勢50名近いスタッフで稼働しています。2025年度に入り、平均入院患者数は164人/月、平均病棟稼働率は83.4%、平均在院日数は8.4日で経過しています。緊急入院も60~80件/月と多忙ですが協力して対応しています。
主な疾患はがん患者が全体の約50%を占め、胃潰瘍・肝炎・肝硬変・肝性脳症・胆嚢炎・胆石・膵炎・消化管出血・潰瘍性大腸炎・クローン病・閉塞性黄疸・腸閉塞など多種に渡ります。近年、内視鏡による検査・治療が推進し、悪性腫瘍についても内視鏡で行うESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)での切除が普及し、2024年度は293件施行され、年々増加しています。また、検査目的でのEUS、ERCP、EGD、CF等や対症療法目的に行われるドレナージやステント留置など内視鏡全般では8579件実施されています。高齢化社会が進む中で当病棟でも70歳以上が約70%以上を占め社会現象が反映されています。そして、内視鏡の発展により身体侵襲が最小限に実施でき、早期回復につながる、検査や治療の選択肢が増え、患者個人に合った方法で医療を受けることができる体制が整備し受け入れています。
最新の医療と看護ケアを提供するために医師と共にクリニカルパスの充実を図り、入院期間5日間で設定された入院診療計画の作成と患者個々に寄り添った取り組みに向けて1人1人が研鑽を積んでいます。また、入院から退院までを多職種で連携して多角的に関わることができるように協働しています。
中越医療圏域において、当院はがん拠点病院と地域連携指定病院の役割を担っています。
消化器内科の患者さまがスムーズに入院し、安全安楽に入院生活を送り地域へ戻るお手伝いができるように実践していきます。

地域連携支援部
地域連携支援部
チーフマネージャー 藤田弥生
2001年(平成13年)、4月から地域保健福祉センターとして開設され、これまで以上に地域連携の充実を推進するため機能見直しが行われ、2018年(平成30年)4月から院内外に対して連携部署であることをわかりやすくするため「地域保健福祉センター」から「地域連携支援部」と名称を変更してスタートしました。
ここで地域連携支援部の紹介をさせていただきます。看護師、事務員、医療ソーシャルワーカーが協働で運営している部署で頼りになる超ベテラン集団です。
ここ10年間で大きく変化したことは、入退院支援部門で2016年(平成28年)10月から退院支援看護師が各病棟専任として配置されました。患者様・ご家族様の意向を伺いながら、病棟看護師、医師多職種と話しあい、ケアマネや施設の相談員等と連携しながら、退院調整を行い入院前の場所に退院できるようにサポートしています。
2018年(平成30年)4月から入院支援看護師が配置されました。2020年令和2年10月入退院支援センターが開設され、多職種と連携しながら運営しています。入院支援看護師は、予定入院患者に入院前支援を実施しています。いまは、予約入院患者の58%に入院前支援を開始し、患者様・ご家族様が安心して入院治療に取り組めるように外来・病棟看護師や多職種との連携強化に努めています。

入院支援看護師
入退院支援センター
退院支援看護師
令和3年地域医療支援病院に承認され、また、令和5年8月には、紹介受診重点病院となり、病診連携室の役割が更に重要となりました。病診連携室は、患者様がスムーズに病院を受診できるように事前に紹介状をもらい受診準備を行っています。近隣の病院や医院に広報誌を年4回発行し連携強化を図っています。

病診連携室
医療ソーシャルワーカー
患者サポート
医療福祉相談室では、医療ソーシャルワーカーは、患者様やご家族が抱える社会的・経済的・心理的問題に関する相談に応じ各種制度の利用や院内や地域の関係機関と連携し社会復帰や在宅療養や転院や施設入所のお手伝いをさせていただいております。詳細はソーシャルワークー科の紹介をご覧ください。
当病院はがん拠点病院で、がん相談支援センターを設置しています。がんのことならなんでも、だれでも相談できるところで対面でも、電話でも受けています。毎月第3木曜日にがんサロンも行っております。多くに方の参加をお待ちしております。
患者様・ご家族様が相談しづらい事やどのように相談したらよいのか分からない事等のお話を伺い患者様と医療者の橋渡しの役割を担っているのが、患者サポートです。その支援を通じて質の高い医療を提供すことが最大の使命です。正面玄関、西玄関でスムーズな受診ができるように各種案内を行っております。気軽にお声がけください。
居宅介護支援事業所は、病気や高齢のために介護が必要になっても、住み慣れた自宅で生活が継続できるように在宅生活を支援しています。看護師と介護支援専門員の2つの資格を持ち相談業務に対応しています。
長岡中央訪問看護ステーション・サテライトとちおは、「安心して在宅療養できるように支える訪問看護」を目標とし0歳~100歳超まで、様々な病気を抱えている利用者様に柔軟に対応できるような体制を心がけています。開業医の先生方、地域の介護サービスの方とも連携して、病院と地域の橋渡しとして活動しています。

ケアマネージャー
訪問看護師
サテライトとちお
事務員は訪問看護ステーションのレセプト、介護保険意見書など、書類関係の処理、地域連携支援部の事務全般を行なっています。地域連携支援部の支えてくれています。
地域連携支援部は地域医療支援病院として、またがん拠点病院として、大きな役割を担っています。コロナ感染拡大で、ボランティア活動も一時休止していたものの、少しずつ再開しておりますし、出前講座で講師の派遣、院内広報誌のすまいる長中の事務局であり、地域の皆様にこの長岡中央綜合病院を活用していただけるように地域連携支援部全体で取り組んでおります。
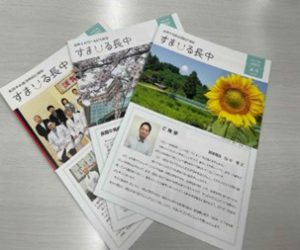
広報誌すまいる長中
左から藤田チーフマネージャー/小林先生(病診連携室室長)/矢尻病院長(地域連携支援部長)/田中副事務長
事務員
地域の皆様を医療・福祉・介護を総合的にサポートしている部署です。地域連携支援部では、患者様に選ばれる病院になれるよう、親切・丁寧な対応を心がけています。
これからもよろしくお願いいたします。

ソーシャルワーク科
ソーシャルワーク科
科長 舩越愛
昭和47年当院に1名の医療ソーシャルワーカー(以下MSW)が初めて配置されました。そのMSWの働きにより院内に医療福祉相談室が開設され、当院におけるMSWの業務基盤を作りました。
1名のMSWからスタートした医療福祉相談室ですが、社会情勢の変化により病気の治療だけでは対応できない心理的・社会的課題を抱える患者の支援において社会福祉の専門職であるMSWの必要性は高まり、複数配置が進みました。
昨今は、病院完結型から地域完結型医療体制への転換により病院の機能分化が進む中、ソーシャルワークを通して地域の社会資源を把握し日常的に地域関係機関と良好な連携関係を築いているMSWが担う役割は大きいと感じています。
平成20年にはMSWの基礎資格である社会福祉士が診療報酬点数上に初めて明記され、MSWを増員する後押しとなりました。平成30年になり新潟県厚生連の組織体系にMSWの専門職科として地域連携支援部の中にソーシャルワーク科が位置付けられ、当院にソーシャルワーク科主任、科長が配属されました。これは先輩方がMSWとして実績を積み重ね、病院に必要な専門職であることを明らかにし、発信してきてくださったおかげであると思っています。現在当院では、社会福祉士を基礎資格としたMSW7名が勤務しています。
MSWは倫理綱領・業務指針に基づき①療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助、②退院援助、③社会復帰援助、④受診・受療援助、⑤経済的問題の解決、調整援助、⑥地域活動を行います。病気や障害は患者に生活しづらさや不安、人との関係性や社会的役割の不十分さをもたらすことがあります。MSWは、患者が自身の強みを活かし自身が希望する生活を送ることができるようにともに考え、援助します。同時に患者が生活する地域へ目を向け、人や組織等患者を取り巻く様々な環境に働きかけ、地域づくりに参画します。
開院90周年の今年、ユニフォームを医療福祉相談室開設以来着用していた白衣からスクラブに変更しましたが、先輩から受け継いだMSWマインドは変わらずに私たちの軸となり、引き続きミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク実践に取り組んでいきます。


中央看護専門学校
平成25年~令和7年までの歩みについて
事務部長 山口英樹
平成25年4月に長岡中央綜合病院の敷地内に現在の学校を移転新築し、令和7年現在12年が経過した。設計段階から検討を重ね学生目線での設備、環境が整えられた。例えば、ガラス張りで明るい教室、渡り廊下で隣接している長岡中央綜合病院へ30秒で実習に行ける、実習室は2教室30床のベッドを設け3人に1人がベッドを活用し看護技術を高めることができるなどである。様々な環境を整えることで、学生、保護者からは学びやすい環境であると喜ばれている。令和4年の第5次カリキュラム改正にて名称を正式名称としJA新潟厚生連中央看護専門学校に変更した。令和7年4月に69期生を迎え、令和6年度までの卒業生は3258名となった。今現在も以前と変わらず卒業生の大多数は、新潟県内にあるJA新潟厚生連の病院で働き活躍している。
わが国では、世界のどの国も経験をしたことのないような超少子高齢化社会、人口減少社会に突入している。2025年(令和7年)現在、人口の4人に1人が75歳以上の高齢者になり、医療・介護・福祉サービスの需要が急速に増加し社会保障制度の維持・継続が危ぶまれている。これに対応するため、厚生労働省が「高齢者が重度な介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケア体制」地域包括ケアシステムを構築した。全国の看護系の大学、専門学校もこれらの事を念頭に置き、令和3年には科目の単位数を97単位から102単位にするようカリキュラム改正がなされた。また、地域・在宅看護論の単位数を増加し、多職種連携の学習の強化もうたわれた。本校においても社会情勢に合わせ、より身近な地域を理解できるための人と暮らし、医療連携、地域・在宅看護の基礎Ⅰ・Ⅱと幅広い知識の習得を目指し科目の再構成を行った。
また、平成25年4月に移転新築を境に更なる看護師確保にも力を入れ学生の定員数を80名に増員し質の高い看護師育成に努めてきた。しかし、令和に入ってから新潟県内にも看護大学が増設され、大学進学を希望する学生が多く、専門学校に入学する学生が減少する状況が続いた。厚生連病院で活躍する看護師の育成のために教職員が一丸となって現代に合わせホームページ、インスタグラムの開設、各イベントの参加などを積極的に行い広報活動にも力を入れているが、学生確保に苦慮しており令和8年度の入学生から定員を60名と減らすこととなった。しかし、学生数が少ない状況ではあるが、入学した学生全員がJA新潟厚生連の使命である地域に寄り添い質の高い信頼される医療の提供できる看護師になれるよう、教職員は日々、看護師国家試験の合格100%を目指し様々なプログラムを考え学生と共に努力し学習指導にあたっている。
新潟県内の看護師確保が問題となっているが、今後もより質の高い看護が提供できるよう学生指導に精進し地域医療に貢献していきたい。
※昭和27年4月から平成24年までのJA新潟厚生連中央看護専門学校の歴史、あゆみについては80周年記念誌を参照して下さい。

付記
2022年(令和3年)保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正(第5次カリキュラム改正)
この改正の趣旨は、少子高齢化が一層進む中で、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステム構築の推進に向け、人口及び疾病構造の変化に応じた適切な医療提供体制の整備が必要となった。また、医療・介護分野においても、AI(Artificial Intelligence:人工知能)、 IoT(Internet of Things:モノのインターネット)等の情報通信技術(ICT)の導入が急速に進んできている。これらの変化に合わせて、患者をはじめとする対象のケアを中心的に担う看護職員の就業場所は、医療機関に限らず在宅や施設等へ拡がっており、多様な場において、多職種と連携して適切な保健・医療・福祉を提供することが期待されており、対象の多様性・複雑性に対応した看護を創造する能力が求められている。
看護師学校養成所カリキュラムの見直し
1)規則別表三
- 総単位数を現行の「97単位」から5単位増の「102単位」とする。
- 教育内容の区分について、「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」「統合分野」の区分を1つにまとめて「専門分野」とする。
- 「基礎分野」の区分の教育内容である「科学的思考の基盤」及び「人間と生活・ 社会の理解」の単位数について、現行の「13 単位」から1単位増の「14 単位」とする。
- 「専門基礎分野」の区分の教育内容である「人体の構造と機能」及び「疾病の成 り立ちと回復の促進」の単位数について、現行の「15 単位」から1単位増の「16 単位」とする。
- 「専門分野」の区分の教育内容である「基礎看護学」の単位数について、現行の「10単位」から1単位増の「11 単位」とする。
- 「専門分野」の区分の教育内容である「在宅看護論」について、名称を「地域・ 在宅看護論」に改めるとともに、規定順を変更し、基礎看護学の次に位置づけ、単位数を現行の「4単位」から2単位増の「6単位」とする。
- 「専門分野」の区分の教育内容である「成人看護学」「老年看護学」の臨地実習の単位数について、現行それぞれ「6単位」と「4単位」であったものから「合 計4単位」とする。
- 「専門分野」の区分の臨地実習について、総単位数の 23 単位から各教育内容の単位数の合計17単位を減じた6単位については、学校又は養成所が教育内容を問わず実習単位数を自由に設定することができることとする。
医療技術職
—薬剤部
薬剤部
薬剤部長 近藤宏
創立80周年(2015年・平成27年)以降、創立90周年(2025年・令和7年)までの薬剤部の沿革史について記載します。
この10年を振り返ると機器の利用、病院薬剤師としての業務拡大がされた10年でした。2025年10月現在、人員は薬剤師26名(事務員1名、薬剤部補助員7名)から、薬剤師31名(事務員1名、薬剤部補助員10名)へと増員しました。薬剤師業務を非薬剤師へタスクシフトすることにより院内調剤そして薬剤師業務の拡大と向上、男性の育児休暇、定年退職後の再雇用など時代に合わせた働き方を推進し、同時に働きがいのある職場を目指してきました。
病院薬剤師確保に苦慮しながら、人員確保に取り組んだ10年だったと感じています。
2015年(平成27年)
・(3月) 注射自動払出システムUNIPUL ®導入
入院注射セットの平均終了時刻が16:32から15:53へと約40分短縮しました。その結果、調剤室からの補助人員が早く調剤室業務に戻れるようになりました。(助手のタスクシフト)ヒヤリハット件数が導入前では月平均91.2件であったのに対し、導入後は10.8件と約88.1%減少しました。
2018年(平成30年)
・(5月) 調剤支援システム F-wave®導入
導入前後で待ち時間を延長することなく取り間違いエラーを大幅に減らすことができました。


2020年(令和2年)
・(4月) 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の活動内容の変化
大きな変更点は、薬剤師が主体となったことです。介入患者も薬剤師がメインで決めることになり、de-escalationや適正抗菌薬への変更、抗菌薬の終了時期など薬剤に関する提案が増加しました。
・(10月) 入退院支援センター開設に関与
「休薬確認」については、持参薬すべてに関与しました。事前の情報を入院後の情報共有に活かし入院後の業務負担軽減しながら、限られた時間(11:30~13:00、その他必要時)での関与ではあるが予定入院患者の休薬等すべてを確認している。休薬確認等の問い合わせも週数件あり、リスクマネジメントにもつながっている。
・(10月) 病棟薬剤業務実施加算1の取得・開始
各病棟に専任の薬剤師が週20時間以上、該当の業務にあたることが条件の加算です。必要人員を配置することは極めて困難で試行錯誤の連続でした。

2021年(令和3年)
・(10月) チーム医療への関与強化(化学療法関連)
がん患者全員(入院・外来)への関与を目標に初回指導(入院:投与前の詳細な説明、服薬指導含む)および新規レジメン・レジメン変更時の患者には最低限関与し、がん拠点病院として取り組んだ。

2022年(令和4年)
・(5月) 抗がん剤調製について、日・祝日もすべて薬剤部で対応(土曜日は以前より関与)
・(11月) 院内処方箋に検査値および禁忌となる腎排泄型薬剤に注意を促す表記を実施
腎機能低下患者等への投与量が適正であるかの確認など疑義照会をより強化した。
2023年(令和5年)
・(12月) 周術期薬剤管理加算の取得・開始
薬剤部で全身麻酔薬の共通薬剤個人セットの運用を開始した。また、周術期プロトコル、手順書整備、周術期評価を必要に応じて手術室担当薬剤師、手術関連スタッフと連携した。
2024年(令和6年)
・(1月) 院内フォーミュラリの作成・運用開始
41品目の薬品が削除(一部臨時使用)され、第1推奨薬、第2推奨薬への処方統一に取り組んだ。
・(3月) 全自動錠剤分包機 トーショー/Xana-2040UF®(2台)搬入
旧分包機は、2001年10月より使用していたので23年ぶりの新錠剤分包機の導入でした。
・(7月) 薬剤管理指導料が初の1,000件超え
2025年(令和7年)
・(4月) 院内処方における「問い合わせ簡素化」についての取り決め
医局との取り決めにより薬剤部でオーダー修正可能になり、医師等の負担軽減に関与した。
・(9月) 当院の無痛分娩開始に伴い、薬剤の調製を薬剤部で開始
最後に創立100周年に向けて、さらなるIT化、AIの活用などにより、どんな薬剤部となっているか非常に楽しみであります。それに向かって長岡中央綜合病院 薬剤部は問題点を解決しながら、さらに飛躍して参ります。
歴代薬剤部長(創立80周年以降)
2012年(平成24年4月)から 2015年(平成27年3月) 徳間一夫
2015年(平成27年4月)から 2019年(平成31年3月) 鈴木和吉
2019年(平成31年4月)から 近藤宏
薬剤部長 近藤宏
放射線科
開院90年を迎えて
放射線科技師長 伊藤哲也
令和7年は戦後80年であり、昭和100年にあたります。そんな年に長岡中央綜合病院は開院90年をむかえました。これも何かの偶然なのか、日本人として今の時代をどのように生きぬいていけば良いのか、いろいろ考えさせられる一年のように思われます。
戦前に既に長岡中央綜合病院の前身である中越医療組合病院(S9年4月)が開設され、10年後に新潟県農業会中央病院(S19年9月)を開設、戦災で全焼し、長町の津上寮を借り診療、のちに再建する。新潟県生産農業協同組合連合会中央病院(S23年8月)開設、その5年ほど後に新潟県厚生農業組合連合会中央綜合病院(S27年5月)開設と記録にあります。戦前、この地域に医療が根ざしていたことに驚きます。
また、昭和33年に中庭にコンクリート造りの照射室が新設され、CO60固定式深部治療措置を設置、食道がん、乳がん、肺がんなどの外部照射線治療が始まるとの記録があります。
診療放射線技師においては、昭和23年4月に研究会、初回会合11名との記録があり、石沢治亮氏、藤木昇氏が長岡中央病院に在籍し参加しています。なお現在の新潟県厚生連診療放射線技師数は147名、長岡中央綜合病院は診療放射線技師33名、医学物理士2名となり医療技術の変遷とともにかなりの大所帯となったものだと感じます。
さて、ここ10年間の長岡中央綜合病院の変遷として、一番大きなものはやはり放射線治療棟開設であると思います。令和元年に放射線治療装置を更新し、従来の1台体制より近年の高精度放射線治療の進捗状況を鑑み、汎用型の放射線治療装置(True Beam、バリアン社製)と強度変調放射線治療(IMRT)に特化した放射線治療装置(トモセラピー、ACCURAY社製)を導入し、新たに治療棟を建設、放射線治療科を設立しました。また、令和3年より定位放射線治療を開始し、令和6年より動体追尾照射(Synchrony)が搭載されました。動体追尾照射は患者様の呼吸を赤外線カメラとX線写真で観察し、体表面、体内の動きをリンクさせて呼吸で動いてしまう腫瘍を文字通り追尾しながら放射線を照射する治療法となります。詳細は長岡中央綜合病院ホームページ放射線治療科、診療内容でご確認して頂きますと幸いです。
また放射線診療科においては、平成30年に多目的血管撮影装置(DSA装置)と心臓カテーテル撮影装置(フィリップス社製)が更新されました。特に心臓カテーテル検査においては最新装置では同時に2方向からの透視撮影を行うことが可能となり、検査時間の短縮、造影剤使用量の低減が実現しました。心臓カテーテル検査室で行われるIVRには冠動脈拡張術PCI、血管拡張術(冠動脈以外)PTA、血管塞栓術TAE、アブレーション、ペースメーカ、ICD植込み術など多種にわたります。
末筆となりますが、当放射線科はそれぞれの放射線診断装置(CT,MRI,RI等)や放射線治療装置の特性を生かし、更なる高精度化を目指し、中越医療圏のがん診療連携拠点病院としての使命を胸にスタッフ一丸となって日々精進して参ります。

検査科
ISO15189認定について
検査科部長 中野正明
検査科と病理部は、2021年4月16日付けでISO15189の認定を受けました。ISOとはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略で、産業の国際標準を定める国際機関であり、その中でISO15189は臨床検査に特化したものです。すなわちこの認定は、本院の検査科と病理部が国際規格に基づく技術・能力を有する臨床検査室であると客観的な外部評価を受けたことを意味するものです。なお、認定機関は公益財団法人である日本適合性認定協会(Japan Accreditation Board; JAB)です。私が本院に赴任したのは2019年4月ですが、ISOの認定取得はそれ以前から当時の富所病院長や古俣技師長らにより計画されており、私の赴任後に認定取得に向けて具体的な活動が開始されました。なお、活動開始当初の各部門の主要なメンバーは、古俣直樹技師長以下、小杉久良技師長(病理部)、吉田和永主任(血液・輸血)、江口克也主任(生化学)、石橋美由紀主任(一般検査)、内山博子主任(生理検査)、村山由美子技師(細菌検査)などでした。
具体的な活動としては、まず2019年5月13日に積水メディカルのコンサルタントなどによるラボツアーが行われました。このラボツアーは、検査科と病理部の各部署においてISO15189の規格を満たしていない事項・箇所をコンサルタントに指摘していただく点検作業でした。一例を挙げますと、検査科の正面の大きなドアは開け閉めが面倒なこともあり、日勤帯ではほぼ常に解放されていましたが、検査室の安全性や機密保持などの観点から、ドアは閉めるよう指導されました。ラボツアーではこれ以外にも実に様々な指摘事項が挙げられ、検査科と病理部でこれらの指摘事項をISOの要求レベルに改善・改変し、この認定取得に係る各種要求事項をクリアすることが、当面の目標・課題となり、要員一丸となって作業が開始されました。
また、同年10月には主な要員が内部監査員養成セミナーを受講しました。これはJAB臨床検査室審査員でもある積水メディカルの担当者による講義や演習であり、受講者は修了証を授与され、これによりISOの要求事項にもある内部監査という作業を行う体制も整備されました。そもそも内部監査とは,検査室がISO15189の要求事項を満たしているかどうかを自分たちで各部署をチェックすると共に、もし不適合が発見された場合はそれに対して是正処置を行う役割があり、内部監査はいわば検査室における自浄作用であり、検査科と病理部の要員が自らの知識・経験をもって検査室を改善する仕組みとも言えるものです。なお、退職や転勤で内部監査の資格を持つ要員が減少したため、2024年5月に再度養成セミナーが開催され、内部監査の新たな資格者が補充されています。
ラボツアーや内部監査員養成セミナーなどを経て、認定に向けた作業が進められ、2020年初め頃からの新型コロナ禍の影響で計画通りに進行しないこともありましたが、2020年度内になんとか申請手続きが終了し、2021年4月での認定となりました。国内では253番目、新潟県内では労働衛生医学協会、新潟大学病院、新潟市民病院、長岡日赤、魚沼基幹、がんセンターに次ぐ7施設目の認定でした。2021年5月13日には当時の富所院長や渡辺事務長にご出席いただき、認定報告会が開催されました。富所院長からは認定取得における検査科・病理部の職員の努力への慰労と感謝の言葉が述べられ、感謝状の贈呈もありました。
認定後は、検査科と病理部の主要なメンバーが、8つのワーキンググループ(WG)を組織して、組織の維持・向上に日々努めています。ちなみに、WG1はQMS(quality management system)管理、WG2は文書・記録管理、WG3は委託・購買管理、機器試薬・消耗品管理、WG4は相談・苦情・不適合管理、WG5は教育、WG6は環境安全、WG7は検査手順、WG8は検査案内・HIS・LISとなっています。そしてこれらの各領域において、PDCAサイクルを回し、継続的改善に向けて努力しています。すなわち、方針・目標などのルールを決め(Plan)、それを実施する(Do)。その後の経過を検証し(Check)、見直す点があれば改善する(Action)という仕組みで、順次これを繰り返していくわけです。
ISO15189の認定により、臨床検査の精度が確保され、またそれによって医療の品質が担保されます。さらに、技師の能力向上、業務の標準化や運営の効率化、医療サービスの向上など様々な効果が期待され、先進医療や臨床治験の推進につながる可能性もあります。また実利的にも、入院患者に対して国際標準検査管理加算が算定され、年間で400万円前後の増収が見込まれ、また、この認定により2023年12月には、がんゲノム医療連携病院の指定を受けることが可能となりました。また、最初の認定はISO15189の2012年版でしたが、新たに2022年版の認定基準に更新されたため、認定基準変更の周知・理解に努め、2025年2月に2022年版の認定も得られています。
ISO15189の認定作業の先頭で頑張っていただいた検査科の技師長は、作業を開始した2019年当時は古俣直樹氏でしたが、認定直前の2021年4月に吉田和永氏に交代し、2025年4月からは岡真由美氏が担当しています。今後ともISO15189認定の維持に努め、臨床検査の信頼性と安全性を高めて、更なる医療への貢献に向けて努力する所存です。

ISO15189認定取得報告会(2021年4月16日)
病理部
職場紹介:この10年を振り返って
病理部技師長 小杉久良
創立90周年を迎えるにあたり、この10年間の歩みを振り返る機会を得ました。医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、病理部も様々な課題に取り組みながら、一つひとつ着実に前進してきました。ここでは当科の10年を象徴する出来事を振り返りたいと思います。
まず大きな転機となったのが、電子カルテと連携可能な病理支援システムの導入です。これまで稼働していた紙ベースのファイリング型システムは、電子カルテと連携がされていませんでした。他の部門と比べてかなり遅れており、情報の一元管理や他部門との連携に限界がありました。2021(令和3)年に電子カルテ連携型のシステムを導入したことで、検査依頼から結果報告までのフローが大幅に効率化され、診療科との情報共有も円滑になりました。これにより、検体の取り違えや報告の遅延といったリスクも減少し、質の高い病理診断を提供できる体制が整ったと思います。
また病理部にとって大きな挑戦だったのが、ISO15189認定取得です。医療の国際的な標準に則した品質マネジメント体制を構築するため、病理部と検査科が合同で取り組みました。標準作業手順書の整備、記録管理の徹底、内部監査や外部団体による審査など、慣れない業務に最初は戸惑うことも多くありましたが、全員で話し合いながら前向きに取り組んだ結果、2021(令和3)年に無事に認定を取得。病理診断の質と安全性を国際的に証明することができました。この取り組みが日常業務に根付き、スタッフの意識向上にも繋がっています。
さらに近年では、2023(令和4)年に当院ががんゲノム医療連携病院に指定されるにあたり、病理部でも新たな体制づくりが求められました。この指定を取得するためには先のISO15189の認定が必須となっていました。遺伝子変異の解析技術や新たな治療薬の開発が進む中で、従来の形態学を超えた高度な知識と技術が必要とされました。専門的な研修を受けたスタッフを配置し、検体の適切な前処理・保管体制の整備も進めました。今ではがんゲノム医療の推進において、病理部の果たす役割は、ますます重要になっています。
そして、忘れてはならないのが新型コロナウイルス感染症への対応です。2020(令和2)年初頭から始まったパンデミックは、病院全体に大きな影響を及ぼしました。病理部も院内感染防止対策委員会と連携しながらPCR検査体制の整備に尽力しました。当初は試薬や消耗品の確保に苦労し、さらに検査件数の急増に対応するために人員の配置や業務体制の見直しに日々頭を悩ませました。また途中コンタミネーションにより、検査ができない苦い経験もしましたが、感染症対策の最前線を一役担えたと思っています。
この10年を通じて、技術の進歩、制度の変化、そして世界的な感染症への対応など、様々な試練に向き合ってきました。その中で感じるのは「変化に対応し、柔軟に進化し続けること」の重要性です。病理部は患者様一人ひとりの治療方針に直結する重要な情報を提供する責任があります。今後も、これまで培った経験と信頼を土台に、高品質で安全な病理診断を提供したいと思います。
検査件数の推移
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
組織診 |
12989 |
12698 |
8878 |
8702 |
8665 |
8386 |
9423 |
9442 |
9335 |
9115 |
|
細胞診 |
21163 |
28194 |
23062 |
16006 |
15921 |
15097 |
14930 |
13745 |
13176 |
11580 |
|
術中迅速 |
222 |
227 |
208 |
260 |
282 |
244 |
258 |
258 |
267 |
288 |
|
テレパソロジー |
54 |
59 |
46 |
56 |
50 |
45 |
36 |
38 |
23 |
32 |
|
遺伝子検査 |
1003 |
1193 |
918 |
577 |
689 |
516 |
550 |
510 |
605 |
1123 |
|
病理解剖 |
15 |
11 |
10 |
13 |
11 |
9 |
6 |
6 |
7 |
7 |
|
新型コロナ検査 |
|
|
|
|
|
1484 |
4744 |
9736 |
787 |
26 |
10年間の主な出来事
2017年3月 上越総合病院で病理診断科が創設され検査件数が減少。
現在の受託医療機関:柏崎総合医療センター、けいなん総合病院、赤泊診療所
2020年3月 新型コロナウイルスが世界的大流行。病理部と検査科が連携してPCR検査体制を整備し運用開始。
2021年4月 ISO15189(2012)認定。2019年5月のキックオフから約2年間の準備期間を得て取得。
2021年7月 病理支援システム稼働。紙ベースのファイリングシステムから電子カルテと連携できるシステムを導入し、業務の効率化を図る。
2023年11月 病理支援システム導入後、運営会社倒産。保守ができず不安定な状態が続いたが、権利を譲渡された別会社と保守契約を結び、安全に運営され現在に至る。
2023年12月 がんゲノム医療連携病院指定。ホルマリン過固定防止対策による長期休日体制を整備。
2024年10月 ISO15189(2022)再審査認定。ISO15189(2012)から新基準(2022)に移行するため、再審査を受ける。
2025年9月現在
医師 1名
臨床検査技師 12名
事務員 2名


臨床工学科
臨床工学科の歩み
臨床工学科技師長 吉崎康徳
臨床工学技士は、医療機器の高度化・複雑化に伴い、それらを専門的に扱う技術者として1987年の『臨床工学技士法』の成立とともに国家資格として誕生した比較的新しい職種です。それまで、医師や看護師が扱っていた生命維持管理装置を専門職が担当することで、医療機器の安全性と有効性が格段に高まりました。臨床工学技士が他の医療スタッフと違うのは、医学と工学の両面を兼ね備えた国家資格ということです。医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う事を業とし、医師をはじめ、看護師などと共に医療機器を用いたチーム医療の一員として活躍しています。
新潟厚生連には、臨床工学技士法の制定前に無資格の医療技術者として採用されていた歴史があると聞いています。もともと臨床工学技士という資格は、透析業務に携わってきた多くの技師、さらには無資格で業務していた少数の体外循環技術者や人工呼吸器の取扱者のために作られたという側面をもっています。長岡中央綜合病院に、臨床工学技士がいつ配属されたのかは当時を知る先輩方がすでに定年を迎えており知ることができません。ただ、病院移転前の段階で、透析センターにて血液浄化業務に就いていたことは確かです。
2005年10月の移転新築時に、医療機器管理室が設置されたことに伴い従来までの透析センターでの「血液浄化業務」以外に「院内のME機器の中央管理」「ME機器の保守、管理」をスタートさせています。その後、業務拡張により「麻酔器点検」「オペ室腹腔鏡業務」「オペ室ナビゲーション業務(脳神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科)」「オペ室耳鼻咽喉科レーザー業務」「心臓カテーテル業務」「ペースメーカー(ICD)業務」「アブレーション業務」と院内において多岐に業務をおこなっています。麻酔器点検や腹腔鏡業務など、以前は医師や看護師が担っていた業務を私たちが引き継ぐことで、チーム医療の効率が格段に上がりました。今後も医師のタスクシフトシェアに伴い、業務が増えていくことが予想されています。私たちは、これからも時代のニーズに応え、安全で質の高い医療を提供するために、日々知識と技術の向上に努めていきます。
組織としての独立
厚生連内の臨床工学技士の近年の大きなトピックスとしては、2016年4月に臨床工学科として独立し、臨床工学技師長が配置されたことがあげられます。それ以前は、組織図上は透析センター配属であり、臨床工学科として独立していませんでした。明確に職種の責任者が配置されたことにより院内での存在感も急速に増したと感じました。長岡中央に技師長が置かれたことにより、その後に順次厚生連内の他の病院にも技師長が置かれました。
リハビリテーション科
リハビリテーション科
リハビリテーション科技師長 廣井鶴輝
当院のリハビリテーション科は昭和37年にマッサージ師2名でスタートし、昭和42年に有資格者である理学療法士1名が勤務となりました。
私は昭和63年に厚生連に就職し初任地が長岡中央綜合病院でした。当時は理学療法士6人、作業療法士2人、言語聴覚士2人の計10名の体制でした。そのころから当院は急性期病院の位置づけでしたが、長期的な入院によるリハビリテーションも提供し、自宅退院・社会復帰に向けた準備など、回復期の機能も担っておりました。介護保険制度などなく、退院前・後の訪問や、必要な介護用品の選定や家屋改造等環境調整なども行いました。
現在、理学療法士23名、作業療法士10名、言語聴覚士5名、のスタッフで構成され、総合的なリハビリテーションが可能な体制を整えています。
高度・急性期の病院機能
近年、病院の機能分化が進められ、当院においては高度・急性期を担う病院機能の位置づけです。急性期病院の役割は疾患の治療が優先であり、回復期機能を担う病院のようにリハビリテーションを専門とする病院ではありません。基本的には治療が終われば、退院もしくは転院というように入院期間は長くありません。早期介入により廃用予防を行うことはもちろんのことですが、「自宅退院が可能か」「転院でのリハビリ継続で自宅退院が可能か」「将来的に自宅退院が困難か」を入院後の早い段階で見極め転帰先を検討することが求められています。
連続性のあるリハビリテーションの提供
術後・発症後に休日があっても、早期介入かつ切れ目のないリハビリテーションを行うため、365日のリハビリテーションの提供(一部病棟から)を開始しました。今後さらに増員を図り、将来的には全病棟を対象とできるよう検討をしていきます。
リハビリ業務の専門化・細分化
対象となる患者さんは全診療科に渡り、より専門的な知識・技術が求められるようになりました。そのため「呼吸器リハチーム」「循環器リハチーム」「がんリハチーム」「HCU(High Care Unit:高度治療室)専任チーム」「糖尿病チーム」「腎チーム」等各領域に専門チームを編成しリハビリ診療を展開しています。
超高齢化社会への対応
今年7月から「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」を1病棟で導入しました。人口構造の変化により超高齢化社会を迎えた現在、入院患者さんは後期高齢者の占める割合が多くなってきました。とりわけ救急医療を扱う急性期総合病院では、高齢者が軽度の症状で入院しても臥床傾向となりやすく、治療のための入院が、逆に入院による活動性低下で廃用が進行しADL低下をきたす傾向があります。
この加算は病棟に専従・専任のリハ職種と管理栄養士を配置し、土曜日・日曜日及び祝日も対応することで廃用の発生を防止することが目的です。「疾患別リハビリテーションを提供しない患者さん」も対象に評価を行い、入院中のADL低下を防止するものです。
今後求められるもの
当院は基幹型の病院として高度医療を提供する医療機関です。今後、高度・急性期リハビリテーションを取り巻く環境は、今まで以上に多様化・複雑化し、様々な対応を求められることが予想されます。その中でリハビリテーションのニーズを的確に捉え役割を果たしてまいります。

栄養科
創立90周年という節目を迎え、これまでを振り返って
栄養科長 石原到
長岡中央綜合病院創立90周年という節目の年に長岡中央綜合病院のスタッフの一員として務めることができ嬉しく思います。
長岡中央綜合病院の10年を振り返り、平成30年に放射線治療病棟増築が行われ、平成31年にはHCU病棟開設、令和5年に、日本医療機能評価機構、病院機能評価認定(一般病院2)3rdG:Ver.3.0を取得、がんゲノム医療連携病院となり、これからも長岡の地域医療を守り続ける病院だと感じました。
これまでを振り返りますと、食糧難の時代から飽食の時代となり、食生活の乱れや運動不足、脂質の過剰摂取など、生活習慣病が問題となり栄養士・管理栄養士業務が重要視されてきました。そして平成18年に管理栄養士の業務が大きく変わりました。それは診療報酬改定により、栄養管理実施加算が新設されたからです。これにより、管理栄養士の業務が「物」から「人」へと変わり、給食管理だけでなく、患者さん個々に合わせた栄養状態を改善・維持するための栄養管理が管理栄養士としての役割になりました。
平成22年の診療報酬改定では栄養サポートチーム(NST)加算が認められました。栄養サポートチームとは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、その他の医療スタッフが協力してより重症な患者さんへの栄養管理を考えるチーム医療のことです。当院では診療報酬改定より前の平成17年に栄養サポートチーム活動を行なっていましたので、平成28年に加算算定を開始しました。
平成24年に栄養管理実施加算が入院基本料へ要件化され、栄養管理体制の確保がより重要なものと認知されました。その後も平成28年の診療報酬改定でがん、摂食・嚥下機能低下、低栄養の患者さんに対する栄養食事指導が栄養食事指導の対象に含まれました。これにより、特別な疾患がある方への、栄養食事指導が「咽せるから食べられない」、「栄養が不足している」など特別な疾患がない方にも、栄養食事指導が必要と認められました。これまで行なってきたことが診療報酬として認められ、とても嬉しかったことを覚えています。
令和2年には特定集中治療室における栄養管理として、早期栄養介入加算が新設されましたが、当院には特定集中治療室がなかったため、算定できませんでした。しかし、令和4年の診療報酬改定時に早期栄養介入加算の算定要件の見直しが行われ、当院のHCU病棟で加算算定が可能となり、令和6年より加算算定を行なっています。
また令和4年に周術期栄養管理実施加算が新設され、周術期栄養管理実施加算も算定するため、準備をし、同年より算定を開始しています。
これまで、病院の入院患者さんに給食を提供する給食管理、特別な疾患の方に行う栄養食事指導が主な業務でしたが、平成18年以降患者さんの栄養状態を改善・維持し、免疫力低下の防止や治療効果およびQOLの向上等を推進する観点から、栄養管理・栄養食事指導や栄養状態の評価・判定など、菅理栄養士としての役割が大きくなってきました。
これからもチーム医療の一員として、また歴史ある長岡中央綜合病院のスタッフの一員として、多職種と協力し業務を行なっていきたいと思います。

事務その他
—医事課
90周年寄稿
医事課長 髙橋秀幸
当院医事課は、管理業務3名、入院係15名、外来会計54名(業務委託)による計72名体制で業務を遂行している。業務範囲は広く、窓口対応、外来会計、入院会計、診療報酬請求業務(レセプト)のほか、各種統計の作成、医事データの分析、施設基準の維持管理など多岐にわたる。これらの業務は病院経営の根幹に直結するものであり、特に2年ごとに行われる診療報酬改定への対応は重要性が高く、高度な専門性と正確性が求められる。また、医師・看護師・コメディカルなど各職種との連携を図り、適切な診療報酬算定と業務効率化を推進することも、医療の質を支えるために不可欠な役割である。
直近10年間を振り返ると、業務環境は大きく変化してきた。平成28年2月には電子カルテを導入し、当初は入院部門のみであったが同年6月には外来にも拡大した。これにより、会計業務を含む事務処理の効率化が進み、ペーパーレス化や情報の一元管理が実現した。令和3年3月には県内医療機関に先駆けてQRコード決済を導入し、従来のクレジットカード・デビットカードに加え、多様なキャッシュレス決済が可能となったことで、患者利便性は大きく向上した。さらに令和4年10月にはマイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」の運用が開始され、顔認証付きカードリーダによるオンライン資格確認が普及した。これにより、従来の目視による保険証確認に比べ、窓口業務の効率化と正確性の向上が図られた。現在はスマートフォンによる「スマホ保険証」の導入準備も進めており、今後さらなる利便性向上が見込まれる。
一方で、制度面でも大きな変化があった。特に令和元年度から令和5年度にかけては新型コロナウイルス感染症対応により、多くの臨時的制度変更が行われ、診療報酬や請求方法に関する特例的取り扱いが頻繁に示された。医事課はそのたびに情報収集と周知を迅速に行い、円滑な運用に努めてきた。また、診療報酬改定のたびに厚生労働省へ提出する診療データは年々複雑化しており、正確な処理には高度な知識と分析力が不可欠となっている。そのため、職員一人ひとりが継続的に知識を更新し、制度改正やICT化に対応できる体制整備に取り組んでいる。
以上のとおり、医事課は会計・レセプト業務にとどまらず、制度改正対応や病院経営など多方面で病院経営を支える役割を求められている。今後も正確かつ効率的な事務運営を通じて、患者サービスの向上と病院全体の円滑な運営に寄与していく所存である。

医療支援課
医療クラーク
医療支援課長 石橋雅章
当院の歴史の中で、医師事務作業補助者(いわゆる医療クラーク)の導入は、医療の質を高める大きな転機のひとつでした。
導入は平成22年、県のふるさと雇用促進事業を活用し、わずか7名の派遣職員からのスタートでした。診断書や紹介状などの文書作成を中心に、限られた範囲で医師の事務負担を軽減することから始まりましたが、その後の診療報酬改定における「医師事務作業補助体制加算」の拡充を追い風に、業務内容も配置も着実に広がっていきました。
平成23年には「75:1加算」の施設基準を取得し、さらに「50:1」「40:1」と段階を踏んで体制を整えました。平成27年には病棟への配置を開始し、翌28年には電子カルテの稼働を機に外来・病棟を横断しての支援体制が整いました。その後も「20:1加算」「15:1加算」と算定基準を順次満たし、医師事務作業補助者は当院の診療体制に欠かせない存在として位置づけられていきました。最大で39名にまで体制は拡大し、外来・病棟・手術室・透析センター・入退院支援センターなど、病院のあらゆる場面に関わるようになりました。
その業務内容は年々広がり、紹介状や診断書といった文書作成補助に加え、検査や処方の代行入力、予約調整、入院や分娩の手続き説明、退院時サマリや逆紹介状の作成、さらには学会や研究データの登録にまで及んでいます。医師の働き方改革が進むなか、医師が診療に専念できる環境を整えるために、こうした業務を担う医師事務作業補助者の存在はますます重要性を増してきました。
とりわけ、退院時逆紹介状の作成や診療データ整理などは、診療報酬上の加算取得にも直結し、病院経営にとっても大きな貢献を果たしてきました。単なる「医師の事務作業の肩代わり」にとどまらず、チーム医療を支え、病院全体の診療の質を高める役割を担うまでに成長してきたことは、大きな誇りといえます。
90年の歴史を刻む当院の歩みの中で、医師事務作業補助者の導入と発展はまだ十余年の短い歴史かもしれません。しかし、この十余年の積み重ねは、医療の現場に新しい可能性を拓き、未来の地域医療を見据えた取り組みとして確かな足跡を残しています。
これからも私たちは、医師事務作業補助者をはじめとする多職種が一丸となり、患者さんに安心と信頼を届ける医療を実現していきます。そして、医師事務作業補助者が「縁の下の力持ち」としてだけでなく、地域医療を支える重要なパートナーとして存在感を発揮していくことを願っています。90周年を迎えた今、この歩みを次の100周年へとつなげていくことが、私たちの新たな使命であると考えています。
医師事務作業補助経過
平成22年(2010年) 県ふるさと雇用促進事業により、医師事務作業補助者として7名を採用
平成23年(2011年) 「75:1加算」施設基準を取得
平成25年(2013年) 「50:1加算」「40:1加算」を順次取得、職員数14名へ拡充
平成27年(2015年) 病棟配置を開始、「25:1加算」取得
平成28年(2016年) 病棟電子カルテ稼働に伴い全病棟配置完了、「20:1加算」取得
平成28年(2016年6月)外来系電子カルテ稼働、「15:1加算」取得
平成29年(2017年) 外来クラークの業務を医事課から医療支援課に移管
令和元年(2019年) 病棟で退院時逆紹介状作成を開始、総合入院体制加算を取得
令和3年(2021年) 37名体制に
令和5年(2023年) 一時的に39名体制となり、最大規模に
令和6年(2024年) 人員異動により37~38名体制で安定運用
令和7年(2025年) 現在、外来・病棟・各部門を含め38名体制で活動中
診療情報管理室について
診療情報管理室 矢引智子
創立80周年を迎えた後、当室は2016年4月に医事課から医療支援課所属となり、2021年7月に電子カルテの更新に伴い、病歴システムも更新し、現在に至っている。室長も富所隆医師の院長就任を機に、副院長の高村昌昭医師が7代目として引き継ぐこととなった。
医療支援課所属となったことで、病診連携室、いわゆる地域連携支援の業務は地域連携支援部へ引継ぎ、現在は診療情報管理中心に業務を遂行している。1974年から永久保存としてきた入院診療録については、利用状況を熟考した結果、過去20年間の保存とすることを病院で決定し、2024年に1回目の廃棄を行った。それに伴い、当院の診療録管理規程も過去20年間の保存に改めた。取り扱う情報については、病歴システムにあるもので47万件超となっている。(2025年9月17日現在)また、医療支援課では病院情報システム管理も担当するため、当室においても診療録管理体制加算に伴うサイバーセキュリティ体制強化にも関与することとなった。
2022年10月に経験した病院機能評価では、診療録の監査や記録の質向上にむけて取り組んだ結果、当室の業務フローを一から見直し整理できたこと、カルテの監査を行った結果、洗い出された問題点に対処できたことは、記録の質向上ならびに経費削減へ貢献できたと自負している。次の病院機能評価更新に向けて、更なる記録の質の向上、電子カルテ操作の習熟と、他部署にも認められる存在とならなければならないと感じている。
当院は地域がん診療連携拠点病院として、2007年症例より院内がん登録を行っている。2025年9月17日現在、約34,000件の登録があり、新潟県内でもその症例数は上位となっている。特に、下部消化管のがん(大腸がん)は全国でも上位に入る症例数であり、当院の消化器領域のがん医療の充実を証明する結果となっている。また、中越医療圏だけでなく、隣接医療圏からも多くのがん患者さんが来院されていることも、これらのデータから読み取ることができる。院内がん登録データについては、当院ホームページ*1にも掲載してあるため、そちらも参照願いたい。加えて、2023年12月にはかねてより懸案であった「がんゲノム連携病院」の指定を受け、そのデータ管理も当室で担っている。ゲノム診療に関しては、腫瘍内科の小林医師を始めとし、看護師、病理部、検査科等の関連部署と連携を密にして業務を遂行している。
次の10年で当室の業務は大きく変わることが予測される。現在、DPCにも使用しているICD-10(疾病、障害及び死因統計分類概要)がICD-11、つまり11版になることで、今までアナログで行っていたものがデジタル化され、それに伴い各種デジタル機器の取扱いに習熟することが求められる。技術的側面だけでなく、個人情報保護への理解、医療DXや人口減少に伴う業務の変化に柔軟に対応できる体制整備と人材育成、地域医療への貢献に繋げられるよう日々、努力を重ねていきたいと思う。
*1「長岡中央綜合病院」→「がん診療連携拠点病院」→「院内がん登録」
https://www.nagachu.jp/cancerhospital/innai/
システム管理室
医療支援課長 石橋雅章
当院が90年の歴史を刻む中で、医療現場の変化とともに歩んできたものの一つが「情報システム化」です。医療の根幹を支える仕組みとして、診療の安全性を高め、患者サービスを向上させ、そして職員の業務を効率化するために、システム導入と改善を重ねてまいりました。
1980年代、日本全体で医療の機械化・情報化が進み始めた時代、当院においてもいち早く医事業務の電算化を導入しました。これは単なる事務処理の効率化にとどまらず、患者さん一人ひとりの情報を正確に扱う基盤を整えるものであり、後の発展に大きな意義を持つものでした。その後も検査機器からのデータ集中管理や画像のデジタル化、伝票による依頼からオーダリングシステムへの移行など、医療の質向上に直結する取り組みを積極的に進めてきました。
医療情報の電子化には法的整備も欠かせませんでした。カルテは医師法に基づき作成・保存が義務づけられる準公式文書であり、その電子化には「真正性」「見読性」「保存性」という三つの条件が示されました。これらを満たすことにより、電子カルテが法的にも認められるようになり、当院もその流れに沿って体制を整備しました。
2001年には「e-Japan構想」が掲げられ、全国的に電子カルテ普及が進められました。当院では、2005年の新築移転を契機に県内に先駆けてフィルムレス化を実現。外来・入院の双方で高精細モニターを整備し、画像を瞬時に参照できる体制を整えました。これにより、診療の待ち時間短縮や過去画像との比較が容易となり、医療の質・効率の向上に大きな効果をもたらしました。また、フィルム購入費削減による経済的効果も少なくありませんでした。
さらに2010年代には電子カルテの全面稼働をはじめ、現在に至るまで救急時の情報閲覧機能やナースコールと連動したモバイルシステムなど、最新技術を積極的に導入してまいりました。こうしたシステムは、地域の中核病院としての使命を果たすうえで欠かせないものとなっています。
情報システム化の利点は、単に紙をなくすことにとどまりません。診療情報を迅速に検索し、検査や処方と連携させ、データを学会発表や診療研究に利用することで、医療の幅を大きく広げてくれます。一方で、操作習熟やセキュリティ対策など、新たな課題も常に存在します。その解決のために、多職種が協力し合い、改善を重ねてきたことこそが当院の強みであると感じます。
90周年を迎えるいま、これまで築いてきたシステム化の歴史は、職員一人ひとりの努力と挑戦の積み重ねの証です。これからも最新の情報技術を柔軟に取り入れながら、患者さんにとって安心・安全で質の高い医療を提供できる病院であり続けるよう、次の100周年に向けて歩みを進めてまいります。
長岡中央綜合病院 情報システム化の沿革
1985~1988年 第1次医事電算システム稼働(NEC)、薬品管理システム導入
1990~1996年 口座振替システム稼働(医事会計システム機能追加)
1992年 第1次給食管理システム稼働(BSNアイネット)
1993~1994年 第2次医事電算システム稼働(集中分散型へ移行、NEC)
1993年 第1次健診システム稼働(C-COM)
1994年 人事・給与システム稼働(サンテック)
1995年 財務会計システム稼働(サンテック)
1997年 院外処方箋発行システム稼働(医事会計システム機能追加)
2000年 第1次介護保険システム稼働(富士通WINCARE・CAREJOIN)、第2次健診システム稼働(富士通HAINS)
2001年 第3次病院情報システム稼働(富士通)
2005年 第4次病院情報システム稼働(富士通)、フィルムレス化開始
2007年 第2次介護保険システム稼働(富士通WINCARE V2)
2013年 第5次病院情報システム稼働(富士通)
2014年 第3次介護保険システム稼働(ワイズマン)
2016年 電子カルテ稼働(入院:2月~、外来:6月~)
2021年 第6次病院情報システム稼働(富士通)
2023年 日病モバイル導入(ナースコール連動)
2024年 救急時閲覧機能導入(2要素認証)
中央健診センター
中央健診センター
事務部長 長谷川嘉彦
中央健診センターは、1972年(昭和47年)4月に『治す医学から予防の医学へ』との健康のあり方に注目して、事務部に“健康管理課”が新設された。
1961年(昭和36年)2年計画で、農村における高血圧症(成人病)の調査を農村部・都市部の事業所や町内会の協力を得て1万人健診を実施し、日本農村医学会に報告したのが検診のはじまりで、当時Dr.をはじめとするスタッフは、各部署からの助勤体制で実施していた。
1965年(昭和40年)成人病検診車が配置された初年度の単独胃部検診は、年間1200名ほどであったが、2011年(平成23年)には8500名ほどになり、健診への意識の高さが年々増加しているのをうかがわせた。
また、1969年(昭和44年)に農村健康管理指導者が配置されてからは、県内各地への出張健診などもできるようになり、幅広い健診活動が繰り広げられるようになった。
1975年(昭和50年)には子宮がん検診車が配置され、今まで施設内でなければできなかった子宮がん検診も地域の中での受診が可能になり、乳がん検診(視触診のみ)と併せて実施されたことで、女性にとって身近な検診として受診できるようになった。
1981年(昭和56年)から82年には、全国共済農業協同組合連合会の委託を受け『農村における糖尿病』について調査・報告した結果この地域における糖尿病の有病率は全国的に見ても“高頻度地区”に属し、肥満についても高率であり、高血圧や検査異常は、いずれも日常生活(特に食生活)と密接な関係があるため、「健康管理は早期からの生活習慣の改善が必要である」と、健診の重要性が報告された。
1986年(昭和61年)に健診棟が新設されてからは、人間ドック・事業所健診など一部検査(婦人検診・胃内視鏡など)を除き本院に移動することなく受診できるようになった。
また、1992年(平成4年)4月には組織変更がなされ、健康管理課は、長岡中央綜合病院付属機関として位置づけされ、名称を【中央健診センター】と変更された。
2004年(平成16年)マンモグラフィー搭載の検診車が配置された。
2005年(平成17年)病院新築移転に伴い、センター内ですべて受診することができる施設となった。
現在成人病検診車3台・マンモグラフィー車1台・健康管理指導車1台を保有し、人間ドックをはじめ事業所健診や行政の特定健診・各種がん検診(胃がん・乳がん・子宮がん・肺がん)と利用者のニーズに合わせた健診内容で、健診センター施設内外で実施を行っている。
2017年度1泊2日ドックを廃止した。
2020年度新型コロナウイルス感染症の影響で緊急事態宣言が発令され、5月6月長岡市住民検診が中止となった。当該年度前半は、受診控えと体調不良によるキャンセルが相次いだ。
2021年度山田聡志センター長が就任され、経鼻内視鏡検査導入など健診センター利用者のサービス向上に努めている。
2022年度健診システムをタック総合健診システムに変更した。
2024年度三条総合病院閉院に伴い、同病院で実施していた健診事業の一部を引き継いだ。
2025年度健診センター2階に内視鏡室を整備し、経鼻内視鏡検査を開始した。同年、子宮がん検診車を廃止した。
総務課
創立90周年記念寄稿文
総務課長 磯部洋一
総務課は、病院運営の基盤を支える部署として、日々の業務に取り組んでおります。職員の労務管理、施設の維持管理、診療材料や医療機器の調達業務など、表には見えにくいながらも、病院全体が円滑に機能するための重要な役割を担っています。90年という長い歴史の中で、幾度となく訪れた制度改革や災害対応、感染症対策など、様々な局面においても、職員一丸となって柔軟かつ迅速な対応に努めてまいりました。
近年、医療現場を取り巻く環境は急速に変化しており、病院経営はかつてないほど厳しい局面を迎えています。特に、診療材料費の高騰と、最低賃金の引き上げに伴う委託費の増加が、医療機関の財務を深刻に圧迫しています。
診療材料費は、円安や原材料価格の上昇、物流コストの増加など複合的な要因により、年々上昇傾向にあります。医療の質を維持するためには、一定水準以上の材料を使用せざるを得ず、コスト削減が容易ではありません。
さらに、外部に委託している業務、清掃、給食、検査、設備管理などにおいても、委託先の人件費上昇により契約費用が大幅に増加しています。主な収入となる診療報酬では、これらの費用を吸収することが困難な状況であり、経営の持続性が脅かされています。
診療報酬の改定が十分にこれらのコスト増に対応していない現状では、自助努力だけでは限界に達しています。
この節目にあたり、私たちは改めて「地域に根ざした医療機関」としての使命を胸に刻み、次の100年に向けて、より安全で快適な医療環境の整備に尽力してまいります。働く職員が誇りを持ち、患者様が安心して来院できる病院づくりを、総務課としても全力で支えていく所存です。
最後に、これまで当院を支えてくださったすべての皆様に心より感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
教育研修センター
教育研修センター長 岩島明
教育研修センター 笠原良枝
教育研修センターは新潟県厚生連の各病院に設置されており、当院では平成31年4月に開設されました。当初は主に臨床研修に関する業務を行っておりました。その後専門研修、看護師特定行為研修など、研修制度に関する業務も担当する様になり、院内の各職種の研修について広く携わっています。
【臨床研修プログラム】
当院は臨床研修病院の指定を受け、2004年4月より臨床研修プログラムを開始いたしました。2025年度までに169名の研修医全員が1人の脱落もなく、2年間の初期研修を終了し、各地で活躍しています。また、定員は2003年度は6名でスタートし、2008年度に8名、2015年度からは10名と増員しております。
マッチングの結果により、フルマッチしない年もありますが、ほとんどフルマッチしています。
|
年 度 |
H28 |
H29 |
H30 |
H31 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
採用人数 |
9名 |
9名 |
10名 |
10名 |
10名 |
10名 |
9名 |
9名 |
10名 |
10名 |
4月入職時からのオリエンテーションのプログラムの作成と指導者の手配。それから引き続き2年間の研修プログラムの管理、休日(有給休暇の取得)の管理、院外研修の研修先との連絡、スケジュール管理などを行っており、最後の研修修了式の計画、実施まで行っています。
2025年11月にはJCEP(NPO法人卒後臨床研修評価機構)による第三者評価を受ける予定です。
【専門研修プログラム】
2024年4月より専門研修プログラムを開始し、2024年度より整形外科専門研修プログラムで2名、2025年度より内科専門研修プログラムで1名が研修を開始いたしました。
従来は専門研修はほとんどが新潟大学の各教室に入局して行われていましたが、別の選択肢を提供する意味で、市中病院で症例数の多い当院での専門医の研修を開始したのです。
【看護師特定行為研修】
看護師特定行為研修については別項に記載がありますのでご参照下さい。
すべての職員が常に自らを成長させるために努力することがよりよい医療を提供するための第一歩であり、今後は院内のスタッフ全員の自分たちの技能を向上させたいという意欲を認め、支えて伸ばしていく活動を行いたいと考えております。
病院機能評価
病院機能評価の認定
柏崎総合医療センター事務長 和田博美
(当時/長岡中央綜合病院 総務課長)
病院機能評価については、基幹型臨床研修病院の指定基準のひとつであり、地域医療支援病院の取り組みとしても推奨されていたため、管理者会議などで以前から話題に上がっていました。令和4年度診療報酬改定において「総合入院体制加算1、2」に医療機能評価の受審が要件化され(「総合入院体制加算3」を当時算定)、同年8月には地域がん診療連携拠点病院の指定要件に追加されるなど、制度改正が受審のきっかけです。
(公財)日本医療機能評価機構(JCQHC)による病院機能評価では同機構が設定した評価基準に基づき、同機構が中立的・客観的な立場で、「患者中心の医療の推進」「良質な医療の実践」「理念達成に向けた組織運営」の領域で構成される評価項目に基づき、医療機関の活動を実地調査と書面審査を通じて総合的に評価するもので、安全で質の高い、より良い医療を提供するための仕組みです。組織運営では「理念・基本方針」、「質改善活動の取り組み実績」、「ガバナンス」が特に重視されます。
令和3年10月、部課科長師長会議メンバー向けにキックオフミーティングを開催、川原経営総合センターによる職場ラウンドやヒアリングなど月1回のペースでコンサル支援を受けながら、各評価項目の責任者、職場長、病棟長、院内各種委員会が中心となって、コンサル指摘の改善、ローカルルールの廃止、各種マニュアルの見直しや整備などの準備に取り組みました。令和4年4月に就任された矢尻病院長が「当院の組織や医療の質が全国の標準と比べてどうなのか、自分たちの仕事を見直す機会にしよう!」と院内基幹会議で発信されたことで、自発的な改善活動が促されたように感じました。
令和4年8月にはコンサルによる本番さながらの訪問審査の模擬審査が行われて各自課題が更に明確化したことで、院内全体の士気が一気に上がりました。
審査前日にはケアプロセス調査対象病棟の医師、看護師、薬剤師、セラピスト、管理栄養士等々が協同し、熱心にカルテレビューの最終確認が行われました。
令和4年10月18日、19日、コロナ禍で院内クラスターが発生すれば延期の可能性もありましたが予定どおり、サーベイヤー6名(医師2,看護2,事務2)による訪問審査が行われました。ケアプロセス調査では6階東病棟(病棟長:浦川整形外科部長)、8階西病棟(病棟長:消化器内科・高村副院長)を病院が指定し、5階東病棟(病棟長:循環器内科・中村副院長)・8階東病棟(外科:河内副院長)を機構が指定、4病棟の典型症例について外来から入院、退院までの医療行為の適切性とその記録の適切性について確認が行われました。そのほか、2日間かけて全35部署部門でのヒアリング、領域別面接調査、意見交換が行われました。
初めての受審でしたが、S評価(秀でている)1項目☛「放射線治療機能」、A評価(適切)65項目と高い評価を頂き、令和5年2月に認定を受けました。
病院機能評価の受審準備が様々な改善のきっかけとなって、関係各所で現状と課題を把握し、その課題をどう改善して質の向上に繋げるのか、模索しながらも多職種多部門が連携して院内全体で取り組むというサイクルが生まれた貴重な機会となりました。
最後に、長岡中央綜合病院がより良い医療を提供し信頼される病院として、今後ますます発展していくことをご祈念申し上げます。
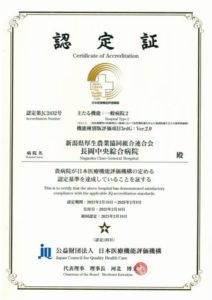

医療安全
医療安全の歩み
医療安全管理者 五十嵐久美子
医療安全という概念が確立したのは1990年代後半から2000年代初頭にかけてと言われています。当院が発足した90年前1935年頃には存在しない概念だったのかもしれません。
私が、医療に携わるようになった頃は、ミスは個人の不注意、個人で防ぐものと考えられていました。それから数十年…今の医療は安全になったのでしょうか?
1999年アメリカの医学研究所(IOM)が発表した「人は間違えるもの」という考え方のもと、医療事故防止対策も変化しました。個人から組織の問題ととらえ、手技や手順の共通化、フールプルーフ(間違った操作ができない)、医療デバイスの活用など、人間の間違いを最小限にする仕組みを作ることが医療安全対策の共通の認識となっています。
具体的には、日々報告されるインシデントレポ―トを分析し、同じようなことが起こらないようマニュアルを整備する、医療者が情報を共有し対策を周知する、患者さん一人ひとりに参加してもらい自身の安全に意識的にかかわってもらう、例えば名前を名乗る、説明で不明な点を明確にするなどです。このことで、リスクは0にはできないですが、事故の影響を小さくすることは可能と考えています。
80周年時の寄稿文を読み返してみますと、医療安全の活動は今でも変わっていません。特別なことはしておらず、日々粛々と起きてしまったことや危なかったことを確認し修正していく、これは何年たっても不変なのだということを改めて感じています。
その後の10年に少しだけ付け加えるとするなら、医療デバイスの活用は医療安全の仕組みの中に欠かせない物となっていることです。10年前にはなかった離床センサー付きベッド、フリーフロー防止付きの輸液ポンプ、頭部CTをAi診断するシステム、電子カルテの様々なアラート機能など、今では当たり前となっているものもありますが、すべてこの10年間に取り入れられたものです。コツコツとスタッフが書いてくれたインシデントレポートから得られた成果かもしれません。
これからの10年間は、更なる高齢人口の増加、医療従事者の減少と人力で補うことができない時代となっていくと思われます。Aiや医療デバイスを活用しながら安全を確保していくことは必須となります。しかしながら、どんなに発展しても「確認する」という人の行動は無くならないと思っています。やはり、最後は「人の力」です。マニュアルを遵守する、危険を察知する能力を育むなど教育や研修を通じて身に着けていかなければなりません。
そして最初の問い、医療は安全になったのでしょうか?
様々な取り組みで安全性は向上しました。継続して取り組まなければ安全はありません。繰り返し言い続けるやり続けることが医療安全につながるものと考えます。
感染対策
当院における新型コロナウイルス対応について
院内感染防止対策委員会 山﨑直子
2019年秋、中国武漢で発生したCOVID-19感染症の報道がなされた際は、どこか遠い国の話で、このように世界的なパンデミックの発生になるとは想像もしていなかった。
2020年1月、日本で初の感染者の報告あり、同年2月には新潟県でも陽性者が判明した。県内での陽性者増加や長岡近隣での発生は現実味を帯び、当院としての対策を協議するため、最初のCOVID-19院内感染対策小委員会を開催した。
病棟内での感染の広がりを防ぐ目的で、多くの患者様ご家族様には面会の制限や入院前のPCR検査にご協力いただいた。
職員に対しても検温や手指衛生の徹底といった基本的な感染対策の実施のほか、長期に渡り同居家族以外との会食を控えることや県外移動の自粛、多人数のイベント参加の禁止など厳しい対策を実施することになった。
2020年3月、新潟県の要請に基づき、5階西病棟に10床の入院病床を確保した。入院患者受け入れのため、5階西病棟に元々あった陰圧室以外にも陰圧となる病室の改修工事を行い、病棟の約半分をCOVID-19対応に使用する体制とした。
外来でも、以前からあった救急外来陰圧診察室以外に陰圧装置を設置し、有症状者の対応のため、帰国者・接触者外来を開設し、多くの患者様の対応を行った。
世界的な感染拡大のため、一時的にマスクやガウンといった個人防護具や手指消毒用アルコールの購入ができない状況にもあった。マスク類や手袋などは在庫がひっ迫し、患者対応のために必須である防護具をなんとか確保するため連日奔走した。
2023年7月26日 当院にて最初のCOVID-19陽性患者の入院受け入れを行った。その後、2025年9月7日までに計876名のCOVID-19陽性患者の入院受け入れを行ってきている。
入院受け入れを始めた当初は死亡率も高く、職員はN95マスクをはじめガウンや手袋など全身を覆う防護具で全身を覆い患者様の診療・ケアにあたる必要があった。防護具を着用して動くと非常に暑く、息苦しさも感じる。日々悪化する感染状況で、「自分も感染してしまうかもしれない」という不安を感じながらも多くの入院患者様を気持ちよく受け入れ、使命感を持って対応してくれた職員には頭が下がる思いであった。
院内ではできうる限りの感染対策を実施してきたが、病棟内での集団発生事例も発生してしまった。中には、もともとの治療による入院期間が延びてしまったり、入院制限をかけざるを得なかったため、患者様やご家族様、近隣病院にご迷惑をおかけすることになったことを申し訳なく思う。
2023年5月に新型コロナウイルスが5類感染症に移行したことにより専用病床が廃止され、一般病棟の各診療科で陽性患者の受け入れが始まった。スタッフの混乱が予想されたが、各病棟にてスムーズな受け入れを行うことができている。
現在、COVID-19感染症は流行の波こそあるが当初よりも弱毒化しており、エビデンスに基づいた対応が可能となってきている。
今後、またこのような感染症の流行がないとは限らない。今回の経験をもとに行政・近隣病院と連携しながら地域全体での感染対策を実施できるよう準備ができればよいと考える。
院内での感染対策のため、職員には長期に渡り行動制限を強いることになった。中には自身の結婚式の延期を余儀なくされたり、大切なイベントへの参加を断念したり、県外からの家族の帰省を中止するなど、医療従事者であるがゆえに、プライベートに制限を強いることになったことを心苦しく感じる。そのような状況でも懸命に業務にあたってくれた職員に心から感謝するとともに誇りに思う。
COVID-19対応の経緯
| 年 | 月日 | 出来事 |
|---|---|---|
|
2020年 |
2月 |
院内感染防止対策小委員会 開催 ・職員の出勤前検温義務付け |
|
2月6日 |
入院患者への面会原則禁止 |
|
|
2月14日 |
外来・救外でのゾーニングの開始 |
|
|
2月17日 |
発熱外来開始(救外3診)PCR検査開始(外注) 入院対応は2類感染症指定医療機関満床の場合のみ |
|
|
2月21日 |
職員への感染対策を強化 ・手洗いの励行 ・出勤前検温義務付け ・状況に応じ、サージカルマスクの着用 ・不要不急の外出を控える ・中国・韓国への渡航禁止 ・院内会議は時間短縮に努める(可能であれば延期・中止) |
|
|
2月28日 |
病院行事の中止の決定 ・農村医学会地方会中止 ・各職場歓送迎会・部署単位の交流会の中止 |
|
|
3月 |
県の要請に基づき、10床の入院病床確保 帰国者・接触者外来開設 外来各ブロックでの発熱者待機ゾーンの設置 エレベーター1基を感染症対応専用化 |
|
|
3月3日 |
産科 立ち合い分娩 母親学級 マタニティビクスの中止 |
|
|
4月1日~ |
職員健康観察記録票運用開始 (緊急事態宣言発出地域から帰省したもの、帰省者と接触したもの14日間の健康観察) |
|
|
4月6日 |
マスク・ガウンといった個人防護具の節約と在庫管理の徹底 (ゴーグル、ガウン、手指消毒用アルコールの入荷予定立たず) (フェイスシールド、N95マスク、手袋の在庫ひっ迫) |
|
|
4月10日~ |
院内PCR実施開始 職員食事休憩時の環境整備の徹底(向かい合わない・黙食・環境整備の徹底) |
|
|
4月20日 |
外来電話再診・処方の実施 |
|
|
4月27日 |
新型コロナ対応会議 ビニールカーテン設置工事(各外来ブロック、各受付窓口、薬局受け渡し口) |
|
|
4月28日 |
新型コロナ対応にかかる特殊勤務手当の運用開始 入院患者病棟外移動の制限 外来リハビリテーション一時中止 |
|
|
5月1日 |
5西での入院患者受け入れ準備開始 |
|
|
5月 |
長岡PCRセンター開設 → 当院からも職員派遣 |
|
|
7月 |
入院時COVID-19ワークフロー作成 5西陰圧工事 |
|
|
7月26日 |
陽性患者入院(当院1例目) |
|
|
9月 |
県の要請を受け抗体カクテルセンタ―設置(5西) |
|
|
10月3日 |
5西病棟 COVID-19専用病棟に変更 |
|
|
11月19 |
ID-NOWの導入 |
|
|
12月 |
職員用ゴーグルの配布(外来部門) |
|
|
2021年 |
1月 |
COVID-19感染陽性者死亡時の対応マニュアル作成 |
|
3月 |
職員向け 新型コロナウイルスワクチン接種開始 |
|
|
6月24日 |
院内発生レベルと対策・職員行動指針作成(流行状況により随時レベル変更) |
|
|
2022年 |
1月24日 |
全入院患者入院時PCRスクリーニング検査開始 |
|
6月13日 |
入院患者への面会と外出・外泊に関する当院の方針策定 |
|
|
2023年 |
2月 |
COVID-19死亡後の処置・遺体搬送マニュアル改訂 |
|
3月 |
政府より新型コロナ対策としてのマスクの着用は個人の判断にゆだねる方針 → 院内ではマスクの着用を原則とすることを決定 ポスター掲示 |
|
|
5月8日 |
感染症法上、2類から5類に変更 5階西病棟専用病床終了(各診療科にて入院受け入れ継続) COVID-19対応マニュアル作成 罹患職員就業制限期間変更・濃厚接触職員就業制限終了 面会禁止 → 面会制限へ緩和 職員の行動制限終了 |
|
|
6月12日 |
全入院患者PCRスクリーニング検査終了 分娩・緊急入院に関しては継続、全身麻酔科手術・気管支鏡前には抗原検査を実施 |
|
|
7月10日 |
入院患者の外出・外泊について緩和 |
|
|
8月 |
N95マスク欠品のため代替品対応 エンゼルケア時の特別処置中止 |
|
|
9月 |
COVID-19罹患職員の就業制限変更 → 7日から5日へ短縮 |
|
|
2025年 |
1月 |
COVID-19感染既往患者手術対応について(手術部・麻酔科) 対応変更 |
看護師特定行為研修
看護師特定行為研修の経過と今後の役割
特定行為研修管理委員長 岩島明
特定行為研修管理副委員長 平澤陽子
2014年6月より「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設され、2015年10月より研修が開始された。これにより、研修を受講した看護師により、手順書に従い、医師が行ってきた38の行為を、診療の補助として実施できるようになった。
実際に受講する内容としては、特定行為に関連したことはもちろん、学生時代に戻ったかの様に、もう一度、医学について、基礎的な解剖学、生理学、生化学、薬理学等を学び、すべての診療科において、病態の変化、疾患、患者の背景等を包括的に評価、判断し、対応できるようにトレーニングすることである。そして、研修を受けた看護師は特定行為のみならず、すべての面で質の高い看護、医療を提供できるように期待される。
当院における特定行為研修は、2019年8月に厚生労働省より指定研修機関と認められた。同年9月より規約を作り、研修プログラムを作成し、研修をスタートした。研修に関する重要事項の審議や研修の適正化、研修を円滑に進行するため、看護師特定行為研修管理委員会を組織した。研修管理委員会は、委員長は岩島副院長がつとめ、実際に携わる副委員長は歴代の副看護部長がつとめた(2019年~殖栗加代、2020年~金泉まゆみ、2022年~五十嵐里美、2025年~平澤陽子)。委員は病院長、麻酔科部長、事務長、看護部長、医療安全管理者、研修指導者代表(他組織で特定行為を取得済みであった丸山順子認定看護師)、総務課長、地域の外部有識者として長岡崇徳大学 森啓学長(2024年~特任教授)、長岡赤十字病院 岩崎佳子看護部長にご参加いただいた。
2020年9月第1期生として、特定行為区分「動脈血液ガス関連」(動脈血液ガス分析の直接動脈穿刺法・橈骨動脈ラインの確保)を修了した3名の看護師(佐藤淳夫、早川慶太、東慶一)が誕生した。この年より、特定看護師修了者を中心に「看護師特定行為研修修了者会議」が行われ、特定行為実施に向けた手順書の整備や運用検討、特定行為周知活動などの検討を開始した。
2021年9月、第2期生3名(関千代、高杉公輔、古川美帆)の看護師が誕生した。「看護師特定行為研修修了者会議」は「特定看護師連携会議」と名称を変更し、2022年1月「特定看護師活動規程」を制定し、看護師特定行為実施の目的を「長岡中央綜合病院の高度な医療機能、先進医療提供に応えるとともに、看護サービスの質の維持・向上を図るため、特定看護師として組織内における医療者間のタスクシフティング・タスクシェアリングの拡大に寄与し、当院及び地域と施設間の連携に対するリーダーシップを発揮すること」と規定するなど、体制の整備が進められた。しかし、なかなか特定行為の実施件数が伸びず、活動部署の検討、看護部・医局への周知活動、看護部教育研修「フィジカルアセスメント」への企画検討等が行われた。
2022年度は受講希望者はおらず、特定行為研修での学習方法の検討や特定行為研修修了者の活躍の場を拡げるための議論が重ねられた。また、並行して今後の社会動向に視点をおき、新たに領域別パッケージ研修導入に向けた検討も開始された。
2023年9月、特定行為区分「動脈血液ガス関連」を修了した看護師は院外3名(清水香奈、和田光子、伊藤あゆ)、当院1名(川野直樹)であった。外部受講生の受け入れにあたり、それまでの研修は全て集合研修だったが、eラーニングを取り入れ、効率よく且つ効果的な方法へシフトした。この変更により、受講者のスキル獲得にデメリットは感じられなかった。院外の受講生を迎え入れることが容易になり、多施設間での交流ができるようになったメリットが大きかった。また、新たに他施設で特定行為区分「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」を取得した特定看護師は、積極的に特定行為実践に取り組み症例件数を重ねることができた。そして、領域別パッケージ研修「在宅・慢性期領域」の施設整備が急ピッチで進められた。
2024年9月、特定行為区分「動脈血液ガス関連」を修了した看護師は院外1名(佐々木綾)、当院1名(高見奈央子)であった。研修項目では「臨床推論」のみ集合研修を行い、「フィジカルアセスメント」「臨床病態生理学」「薬理学」「疾病臨床病態概論」「特定行為実践/医療安全」は、ほぼeラーニング学習となった。そして、同年10月、領域別パッケージ研修「在宅・慢性期領域(気管カニューレ交換、胃ろうカテーテル交換、褥瘡又は血流のない壊死組織の除去)」受講者1名の研修が開始された。特定研修修了者の実践件数では、年間10件程度から70件程度と人によってバラつきはあるものの、自身でアセスメントをして実践している実績もあることから、組織として特定看護師をどのように活用していくかが課題となっている。
2025年9月、特定行為区分「動脈血液ガス関連」を修了する看護師1名(池野里紗)、「在宅・慢性期領域」を修了する看護師が1名(岩野明)誕生した。また、同年に「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「精神および神経症状に係る薬剤投与関連」を修了した認定看護師と特定看護師がおり、さらに、他施設で受講している「創傷管理関連」1名が修了予定となっており、研修修了者は11名となる予定である。さらに、次年度は「動脈血液ガス関連」2名、「在宅・慢性期領域」院外1名、院内1名の受講希望がある。専門職としてのやりがい、患者サービスの質向上のため、自らキャリアアップしていく看護師が増えていると感じている。
2040年代には、生産年齢人口の比率が減少し続け、高齢者1人に対して現役世代が1.5人という時代になることが予測されている。高齢世帯の約7割は単独または夫婦のみの世帯が見込まれ、生活に困窮する人や孤立しやすい状況となる人が増加する。そのため、医療提供は病院だけでなく、在宅や介護施設などの生活の場へ広がることが予測される。看護は、「医療の視点」と「生活の視点」の両面から人々を支えることができるという強みをますます活かす必要がある。1人ひとりの個別性を重視し、その人にとって最適な支援を提供していくことが求められる。そのためには、専門職としての知識・技術・態度の向上、キーパーソンとして多職種協働実践の推進、他施設や地域との連携を担うコーディネーターなど、活躍の場を拡大していく必要があり、継続していかなければならない。
ここまで述べてきたように、看護師特定行為研修を推進していくことは、看護師全体の能力向上と連動し、看護の質向上に寄与するものと考える。看護部教育体制と特定行為研修をコラボレーションさせ、今後も看護の創造・発展の道のりを歩んでいくことを期待する。


髙野理容室
髙野理容室
長岡中央綜合病院内理容室 髙野幸雄
長岡中央綜合病院様の90周年記念、誠におめでとうございます。
思えば80周年記念誌にも私共が記載させて頂きました。又こうしてお声が掛かり身に余る光栄に思います。
10年一昔、私には非常に早く感じられます。この間、世間では様々な事柄に遭遇しつつ、私なりに記憶を振り返れば特に医療機関に最も関連ある世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症、日本では東日本大震災、そして現在紛争中のロシアによるウクライナ戦争など世界は難題が山積しておりますが、取り分け私共理容室では新型コロナウイルス感染症には大いに悩ませられました。コロナに感染しないように連日神経を使い患者様とスタッフ3名の感染を防ぐため日常生活では消毒を徹底的に行い、感染者を理容室から出さない強い信念のもとに眠れない夜が続いた日々でした。毎日この難局にどう立ち向かうか模索した思いが忘れられません。連日理容室の利用者も激減し、この先どうしたものかと身の細る思いも経験いたしました。
今ではコロナ感染症も厚労省によると第5類に認定され巷では感冒に等しいなどと感染に対し安堵感があるように思われますが、私はそうは思いません。現に新たに変異株ニンバスNB.1.8.1が流行しているとのことで、この先も感染には警戒が必要と思われます。
私共理容室では長岡中央綜合病院様の理念である、
「地域の中核病院として皆様の健康を守る為、良質で心温まる医療を提供し、予防・保健・福祉活動を積極的に推進いたします」
以上を常に心掛け、患者様に満足のいく技術と癒しの空間など患者様とのコミュニケーションを図り真摯に取り組み勤めさせて頂きたいと思います。
尚、日頃職員の皆様には連日、病棟・病室・外来からの患者様の送迎を担って頂き心より感謝申し上げます。
振り返れば私は1966年(昭和41年)に長岡中央綜合病院に勤務し、縁あって翌年に理容室経営を担わせて頂きました。昭和では23年間、平成で30年間、令和では約7年間、実に通算で60年余りになります。
これも職員の皆様の温かい指導のもとに今日まで恵まれた環境のもと大過なく勤めさせて頂き、心より感謝申し上げます。
長岡中央綜合病院様の益々の御発展を心より祈念申し上げます。
たんぽぽ保育園
たんぽぽ保育園
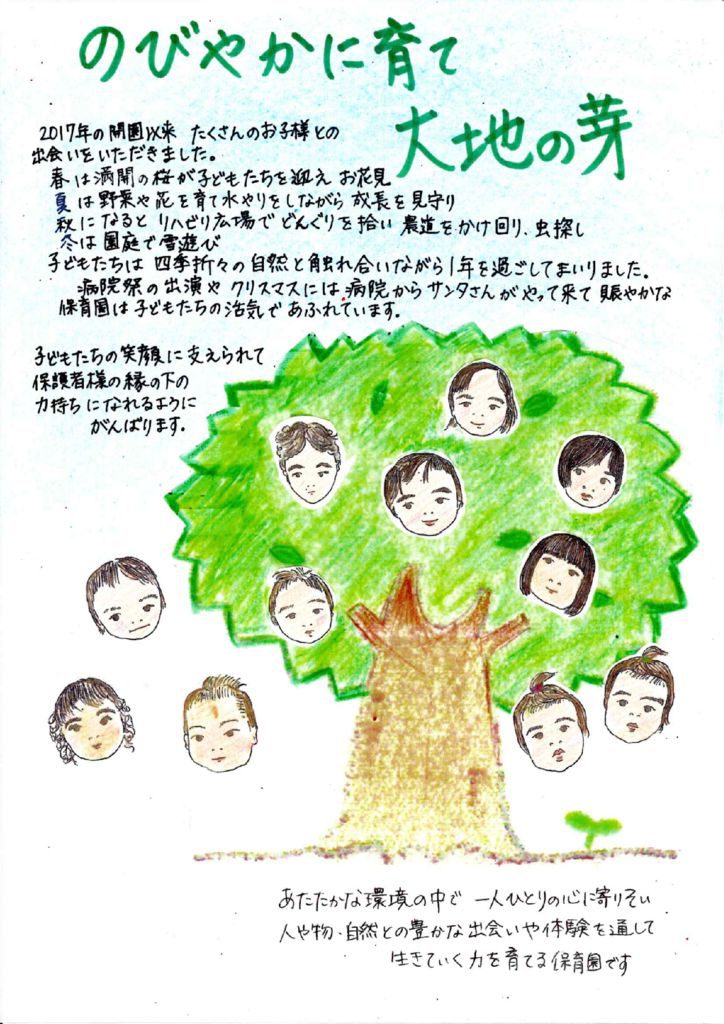
栃尾郷クリニック
栃尾郷クリニック
栃尾郷クリニック所長 宮﨑大輔
長岡中央綜合病院が開院90周年を迎えられたことに、心よりお祝い申し上げます。昭和10年の開院以来、この地の医療を支えてこられた先人のご尽力と、地域の皆さまの温かい支えに、深く敬意と感謝を申し上げます。
1945年8月の長岡空襲、1994年10月の中越地震、最近では2024年元旦の能登半島地震で地域とともに大きな試練を経験したことと思います。しかし、幾多の困難にも負けずに診療の灯をともしてきたその姿は長岡中央綜合病院の輝かしい歴史の1ページでもあると考えます。
私は栃尾郷病院を引き継ぐ形で平成28年8月に開設された栃尾郷クリニックに令和5年4月より所長として勤務しています。四季豊かな自然と人情あふれる栃尾の地で、日々の診療を通して感じるのは、長岡中央綜合病院の大きな存在です。栃尾で難しい精密検査・急患患者の搬送などいつも快く引き受けていただき感謝の念に耐えません。
これからも病院とクリニックが手を取り合い、どのような困難のときも地域に寄り添い続けられるよう、微力ながら尽力してまいります。90周年を新たな出発点として、未来へ歩みを進める長岡中央綜合病院のますますの発展を心より祈念いたします。
協栄会
協栄会
長岡中央綜合病院協栄会会長 大橋博文
中央綜合病院の納入業者会として、昭和32年頃、19社にて発足したそうです。会が発足した目的の1つに、新潟県厚生農業協同組合連合会の戸田文司会長(故)を支えるということがあったと聞き及んでいます。
初代会長は旭食品の谷内田博、現在の会長は10代目、船山株式会社の大橋博文(筆者)です。会は60年以上続いており発足当時19社から始まった会の会員数も年々増え、一時は80社を超える時もありましたが、現在では57社になっています。
(歴代会長)
|
代 |
氏名 |
社名 |
|---|---|---|
|
初代 |
谷内田博 |
旭食品株式会社 |
|
2代 |
平野正栄 |
平野産業株式会社 |
|
3代 |
中村正康 |
新潟乳業 |
|
4代 |
志田喜久治 |
志田材木株式会社 |
|
5代 |
近藤富雄 |
近藤電気株式会社(現株式会社イートラスト) |
|
6代 |
青柳博 |
青柳塗装株式会社 |
|
7代 |
坂田岩夫 |
船山株式会社 |
|
8代 |
小林立憲 |
株式会社新潟県厚生事業協同公社 |
|
9代 |
五十嵐智幸 |
株式会社新潟県ビル管理協同公社 |
|
10代 |
大橋博文 |
船山株式会社 |
主な協力協賛事業としては、病院祭への参加、さくら文庫への協力、講演会の開催、親睦納涼ビアパーティー等、年間を通じて病院事業に積極的に参加および協力をさせていただいております。
しかしながら、近年はコロナ禍、病院の経営環境の変化により今まで通りにいかなくなっているのも現実です。
この先、病院の経営環境、医師・看護師不足が深刻な問題となっている中で、協栄会として、環境の変化に対して、どのように対応していくべきかを考えながら、100周年に向けて、長岡中央綜合病院の協力業者会(協栄会)としての役割が果たせるよう努めていきたいと思います。
(文中敬称略)
祝辞
—OB寄稿
九十周年記念にあたり -「天職でありしさきはひ昭和の日」-
郡司哲己
本年七月に迎えた当院の九十周年記念の寄稿を求められ、思い出の断片で、一文を草するものです。
わたしは令和元年3月に満65歳で長岡中央綜合病院の小児科部長を定年退職、新潟大学医学部臨床准教授を兼任しておりました。その後三年間の小児科アレルギー専門外来の診療をつづけた後完全引退しました。
そもそも昭和60年4月、新潟大学の医局人事で文部教官助手から卒後八年目で小児副医長(当時医長は藤島暢先生)で赴任しました。爾来三十年余を大勢のスタッフのみなさんの協力を得ながら、毎日の患者さんが多すぎて繁忙ではあったものの充実した勤務ができました。
今年の「昭和の日」に際して、来し方を懐旧して、次の俳句を詠みました。
俳誌『円虹』令和七年七月号掲載の題詠推薦句。
「天職でありしさきはひ昭和の日」 郡司哲己
(「さきはひ」は「さいわい」の古語)
ちなみに四十代で始めた俳句が趣味で、現在まで続けており、七十歳を機に句集を二冊、昨年上梓しました。ただしこの句は昭和ですが、どちらかといえば平成が自分の壮年期。急速な昨今の医療者の過重労働の改善とは全くご縁のない、まだまだ過酷な勤務状況のご時世だったのでした。
昭和60年当時の産科は温厚篤実な永松幹一郎医長のもと、なんと産科医4名で県内で最大の分娩数を扱い、他院で断られたとび込みお産等も快く引き受けていました。当時の年間出生数は驚異の1500名前後、一定割合で小児科で要治療の病的新生児も多くなります。(それまで大半は母体搬送や他病院へ転送)福島江の上に仮設駐車場を設置した旧病院の時代のことです。とび込みお産の緊急避難的受け入れで当院産科で無事に出産後、ベッド移動しながらスタッフに泣いて感謝している産婦さんも実際に見聞きしました。こうした困っておられる妊産婦さんを断らずにとにかく受け入れるのは、次の加藤政美産科医長も同様でした。こうした産科医師たちのがんばりは自分には大きな励みになりました。
かかわる小児科医は自分ひとりでしたが、人工呼吸器の使用を始め、未熟児、新生児医療に真剣に取り組んだ結果、急速に救命率も向上し、診療した新生児はそのまま乳児、幼児期を通して小児科のかかりつけ患者となってくれます。モニター、精密輸液ポンプ、呼吸器備品等の必需品を故亀山宏平院長に直訴すると年度途中でも予算捻出して購入してくれました。「ヒトはまだ無理でもモノはなんとかする…。」
勤務して数年の小児科外来のさらなる盛況を見かねた故亀山宏平院長の小児科教授への要請も功を奏し、小児科医の派遣増員もかないました。ありがたいほどに患者さんが多く集まり、朝5時から診察順番の番号札をとりに一部の保護者が来院したり、午前と午後の延長から夕方の時間外にわたる診療と薬局や医事課会計事務の残業もほぼ毎日のことでした。
平成17年秋の新病院への移転時の44床への飛躍的な小児病床増でも、その予想を上回る入院数でした。その年の大晦日、たしかRSウイルス流行もあって、救外の入院受け入れを入れて、小児定床超えの73名入院が最大記録でした。各階病棟に一時ベッド借りしてほとんどが酸素投与を受ける小児患者をメモを片手に、翌朝の元旦に回診したのは、今も思い出に残っております。
日曜休日もほとんど休めず、時間外もポケベルが鳴る。救外でもこどもは小児科医が診察してくれると評判になり、親子が直接受診しては、指定日外でも呼び出されるような時代でした。
この三十年でしだいに同僚医師数も増え、お互いに専門分野を分担しあい、かなり勤務時間をまもれるようになりました。当地でも出生数は年々減少したため、小児病床数も段階的に減ってゆき、小児病棟は複数の科の混合病棟化してゆきました。
ところで今でも新たなおしごとにいくつかお誘いいただくことがありますが、ありがたくご辞退申し上げて、非常勤のデスクワークの社保支払基金の審査委員のみ継続中です。
「もう十分に精一杯、夜昼問わずに働きましたので…すこしでものんびりと余生を過ごせればありがたいです。」
振り返ってみて、ほんとうにたいへんな日々でしたが、小児科医としての長岡中央綜合病院での人生の半分を占める勤務時代に後悔はありません。小児科医として、おおぜいの未来のあるこどもを助けたり、ちからになれたことは、自分の天職だったと心から思えるのです。
以上
私の医師人生と長岡中央綜合病院(創立90周年記念誌に寄せて)
こしじ医院院長 児玉伸子
医師としての私の経歴の中で長岡中央綜合病院は欠かせない存在です。
広島県にてこの世に生を受け中学高校時代を神奈川県で過ごし大学でやっと新潟にたどり着いた私と、長岡の地を最初に結びつけてくれたのが長岡中央綜合病院です。私が大学を卒業した昭和55年当時は、今のような研修医制度もなく卒業後はすぐに大学の医局に入局し、市中のいわゆる関連病院で研修することが一般的でした。私も頭の上にタマゴのカラをのせたヒヨコ状態で最初にお世話になったのが長岡中央綜合病院です。仕事も初めて雪に被われた冬も初めてと初めてづくしの毎日でしたが、病院の医局の先輩方やスタッフの皆様には本当に暖かく迎えていただきました。当時の病棟の婦長さんは40歳そこそこの働き盛りの方でいろいろ注意されましたが、お互いに年齢を重ねた今でもお付き合いさせていただいています。今思い返しても楽しかった事とともに、恥かしくなることや申し訳なくなること等沢山の思い出がつまった日々でしたが、現在まで医師の仕事を続けてこられたのはこの一年間の豊かな思い出があったお陰と感謝しております。
その後いくつかの病院での研修を終え平成3年から再度お世話になり、8年間の勤務医としての奉職後平成11年10月に無床の診療所(こしじ医院)を開院し現在に至っています。卒後19年目に院長として診療所の開設は私の医師人生にとって大きな変換点でしたが、この時も当時の杉山一教病院長や医局の先生からの温かい励ましに助けられました。
“頑張ってやって下さい、それで何かあればいつでも紹介して下さい、何とかします。”
この言葉を支えに今までの診療を続けてきたといっても過言ではありません。おかげ様で何とか26年間継続することができております。
このように長岡中央綜合病院は私の医師人生の初めの一歩であり、その後の支えでもあります。今後の御発展をお祈りしております。
長岡中央綜合病院90周年によせて
長尾政之助
日々変わってゆく医療・経済・少子高齢化・介護の状況の中で90周年を迎えられおめでとうございます。大きな病院組織の運営は大変なご苦労と拝察いたします。小生は昭和63年から平成5年の父の死去による医院の継承まで在職させていただきました。
この度、90周年に当たり寄稿せよとの連絡をいただきました。30年が経過しておりますが今でも記憶によみがえる出来事を書き留めてみました。
小生は第2内科医局では腎膠原病班に属していましたので血液透析・腹膜透析部門での思い出が多くあります。長岡中央綜合病院は当時から腹膜透析では県内でも有数の症例を診ていましたが、慢性期の維持透析よりは急性腎不全や体外循環を用いた血液浄化治療に興味があり、急性腎不全の緊急透析や血漿交換、体外循環による免疫吸着など貴重な経験をさせていただきました。血液回路を改変自作して治療を行ったこともありました。症例があれば試みてみたかったECMO(体外式膜型人工肺)は残念ながらできませんでした。
長岡に赴任する前の昭和59年に、今から考えるとインフルエンザ脳症と考えられる19歳女性の症例があり、当直で診療し入院経過観察とした夜半に看護から呼吸が微弱になってきていると連絡を受け挿管、呼吸器管理となったケースでした。幸いにも1週間で離脱でき2週間後には歩いて退院していった患者さんでしたが、このような修羅場の経験がその後に役立ったものと思います。
様々な症例の診療にあたる機会に恵まれ経験を積み臨床医に育てていただき現在も大変お世話になっている長岡中央綜合病院に感謝申し上げます。
九十周年おめでとうございます
元形成外科部長 星榮一
(80周年記念誌編集委員)
「八十年のあゆみ」を執筆してから、早や10年も経過したとは夢のようです。その後気付いたことを列挙します。
1 病院名称の変遷
我が長岡中央綜合病院は、創立から現在までに8回も名称を変更しています。その大部分は経営主体の組織変更によるものです。まず昭和10年7月の創立時は、①中越医療組合病院でした。昭和13年に経営不振で閉院になり、昭和16年7月に経営主体が変更され②丸新連合会中央病院として再開されました。この時から中央病院になったわけです。次に昭和19年1月に組織変更により、③新潟県農業会中央病院になりました。終戦後さらに組織変更があり、昭和23年8月に④新潟県生産農業協同組合連合会中央病院となりました。昭和26年4月には⑤新潟県指導農業協同組合連合会中央病院と変更になりました。さらに昭和27年5月に⑥新潟県厚生農業協同組合連合会中央病院となり、昭和32年8月に⑦新潟県厚生農業協同組合連合会中央綜合病院となり、最後に平成8年4月に⑧新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院となり今日まで続いております。ここで初めて長岡が付き、一般的には長岡中央綜合病院と呼ばれているのは周知の通りです。
2 「八十年のあゆみ」に収録できなかった資料
「あゆみ」発行後の平成27年1月に総務課の倉庫で発見された未見の写真があります。もう半年早く発見されていれば、「あゆみ」に収録できたものにと残念です。これらの資料は、厚生連で毎年発行している「厚生連医誌」第26巻1号(2017年)に、10枚の写真を収録されています。また、総務課でも厳重に保管している筈なので、是非次の「百年のあゆみ」には収録して頂きたいと願います。
3 三宅正一胸像のこと
三宅正一は我が長岡中央綜合病院の生みの親です。市民には余り知られておりませんが、悠久山の松山の頂上に胸像がありました(写真1)(ぼんじゅーる、No467,2019年2月号)。この胸像は昭和59年の彼の三回忌に、社会党の有志の寄付で建立されたものです。しかし、令和5年ごろ松山頂上から胸像がなくなり、更地になっていました。どうもこの土地は、悠久山公園に隣接した個人の土地で、何らかの事情で撤去せざるを得なくなった様です。おそらく像を壊していることはなく、どこかの倉庫に保管されていることと思います。
三宅が昭和11年に初めて代議士に当選した際に、雑誌「改造」に「遺骨の一部は中越医療組合病院の一隅に埋葬して欲しい」と記載しています。出来れば長岡中央綜合病院の構内の片隅に胸像を設置できないかと願っています。
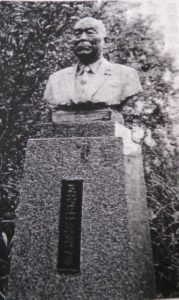
写真1
4 ヒポクラテスの木
このヒポクラテスの木は、単なる街路樹のプラタナスとは違い、ギリシャのコス島にあるヒポクラテスの木の遺伝子を持ったプラタナスなのです。蒲原株第1号の7と登録されています。
病院が新築移転した平成17年12月の移植時は、樹高4m、樹の広がり1.5m、根元の周径47cmでした(あゆみ、325頁)。植樹から20年が経ち、現在は樹高12~3mで外来棟の屋根よりも高く、樹の広がりは9m、根元の周径180cmと成長しています(写真2)。
この樹の親木である新潟大学医学部のヒポクラテスの木(蒲原株第1号)は昭和50年に植樹され50年たっていますが、樹高約30m、病院の8階の高さで、樹の広がり約20m、根元の周径275cmで、とても大きく成長しています(写真3)。我が長岡中央綜合病院のヒポクラテスの木もさらに大きく成長するものと思います。大切に育てたいと思います。

写真2
写真3
5 職員OB会について
職員OB会は令和6年6月の「OBのつどい」を最後に終了してしまいました。役員の高齢化による終了だそうです。なぜ、そうなる前に若手を入れて世代交代をしておかなかったのか不思議です。OB会は平成19年(2007年)に始まり、3年毎に「OBのつどい」を開催し、コロナの流行時には開催されませんでしたが、6回開催されました。登録会員は350名程おられました。
このまま職員OB会を無くしたままにしておくわけには行かないと思います。これから再結成するには、容易ではないと思いますが、やらなければならないと思います。どなたか再結成の活動をしようとする方は居ませんでしょうか?職員OB会を復活させましょう。
6 「八十年のあゆみ」の正誤表
「あゆみ」には大きな間違いはないようですが、小さな誤字、脱字がいくつかありました。私が目を通した範囲での正誤表を示します。また、昭和16年に再開した病院は丸新長岡中央病院ではなく、丸新中央病院であったようです。
(正誤表)
|
あゆみ頁 |
行 |
誤 |
正 |
|---|---|---|---|
|
14頁 |
みちくさ2 写真下 |
長尾義賀 |
長尾義賢 |
|
17頁 |
本文上から6行 |
神明町 |
新明町 |
|
21頁 |
1行目 |
長岡中央病院 |
中央病院 |
|
21頁 |
上から8行目 |
長岡中央病院 |
中央病院 |
|
21頁 |
写真8の説明 |
長岡中央病院 |
中央病院 |
|
22頁 |
上から6行 |
長岡中央病院 |
中央病院 |
|
22頁 |
みちくさ2 2行目 |
長岡中央病院 |
中央病院 |
|
28頁 |
上から18行 |
6月6日 |
6月16日 |
|
91頁 |
上から9行 |
増たこと |
増えたこと |
|
92頁 |
本文上から14行 |
(平成4)11月 |
(平成4)年11月 |
|
156頁 |
下から11頁 |
新た治療 |
新たな治療 |
|
176頁 |
上から7行 |
病院際 |
病院祭 |
|
178頁 |
本文上から7行 |
実践されていことは |
実践されていることは |
|
325頁 |
下から7行 |
5年 |
8年 |
|
342頁 |
下から9行 |
無いし教室 |
無いし鏡室 |
|
351頁 |
本文上から11行 |
医手術前に |
胃手術前に |
|
351頁 |
本文下から7行 |
海洋性疾患 |
潰瘍性疾患 |
長岡中央綜合病院はこの10年で大きく発展しました。次の10年後の百周年には更に発展しているだろうと思います。しかし、残念ながら恐らく私はそれまでは生きられないだろうと思います。さらなる発展を祈ります。
新潟県厚生連代表理事理事長
長岡中央綜合病院創立90周年に寄せて
新潟県厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長 塚田芳久
長岡中央綜合病院が創立90周年を迎えられました。衷心よりお祝い申し上げます。前身の中越医療組合病院は1935年(昭和10年)7月に開院し、以来90年という月日が経過したことになります。この間、一時閉院や戦争による空襲消失など、病院の歴史には紆余曲折がありました。1952年(昭和27年)に新潟県厚生農業協同組合連合会(以下新潟県厚生連)中央病院となり、新潟県厚生連の旗艦病院として病院・保健・介護の三事業と経営を支えてまいりました。二代目病院の近代化工事は1983年(昭和58年)まで続き、2005年(平成17年)に三代目病院が現在地に新築されました。病院立地の長岡市はもちろん、中越圏域全体や魚沼地域の基幹病院として、長岡赤十字病院、立川綜合病院と共に三病院体制を形成して救急や先進医療を牽引してきました。
病院では日夜、多くの手術、多くの検査を行って臨床医療に貢献し、医師教育や看護教育をはじめ多くの医療者育成の中心でもありました。病院に支えられた質の高い検診と地域との連携体制を構築し市民の健康も守ってきました。毎年新潟県農村医学会を開催し、新潟県厚生連の職能ごとの技術向上と医学研究の場も提供し、医療の質向上に寄与してきました。このように医療提供に加えて、人材育成や医療の質向上や研究・教育など幅広く大きな成果を収めた功績は大なるものがあります。
近年の日本は少子高齢化、人口減が進み、この10年間に施策を中心に日本の医療界を取り巻く環境は大きく変化しました。このたび90周年のあゆみを振り返るとともに、地域医療構想を含め、厚生連長岡中央綜合病院の将来のあり方を考える時期に差し掛かったと思います。創立90周年を契機と捉え、院内および各方面の関係者の意見を聞き、創立100年に向けて新しい時代に相応しい病院を模索していただきたいと思います。
おわりに、これまで支えて下さった従業員や地域の皆様に感謝申し上げ、厚生連長岡中央綜合病院の益々の活躍を心から期待申し上げます。合わせて、関係各位のご繁栄ご健勝を祈念申し上げて、創立90周年にあたりお祝いを申し上げます。誠におめでとうございます。
長岡市医師会会長
創立90周年を祝して
長岡市医師会長 草間昭夫
このたび、長岡中央綜合病院が創立90周年を迎えられますことを、心よりお祝い申し上げます。
長岡医師会史や80周年史を読み返し、あらためて本院を支えてこられた先人のご尽力に深い感銘を受けるとともに、中越地域の医療を担っていただいたことに心から感謝申し上げます。
創立以来の発展は言うまでもなく、2005年の新病院移転以降も、検診業務から最新のがん治療に至るまで幅広く地域住民の健康を支えられ、現在は「がん診療連携拠点病院」として重要な役割を果たしておられます。長岡救急3病院による救急輪番制は世界に誇るべきシステムと自負しておりますが、その一翼を担っていただいていることにも、深く敬意を表します。対応する医療圏は長岡市のみならず県央や魚沼地域に広がり、さらに災害時には県外への救急チーム派遣にも尽力されました。
この10年を振り返りますと、富所前院長には、病院管理者・臨床医としての豊富なご経験をもとに、長岡市はじめ国・県における医療課題にご指導を賜り、新米の医師会長である私の相談にも快く応じていただきました。現矢尻院長の理路整然としたお考えと力強いリーダーシップは、コロナ禍以降の厳しい医療情勢にあって、まことに心強く感じております。
2020年の新型コロナウイルス感染症流行時には、国・県の方針のもと県全体の患者対応に尽力されましたが、とりわけ市内の救急病院や多くの診療所、長岡市との連携により独自に病床を確保し、患者の受け入れ体制を整えられたことは特筆すべきことです。90年に及ぶ歴史の中で培われたチームワークの賜物であり、その成果として新潟県の感染症死亡率が全国最低水準となったことを、私どもも大きな誇りとするところであります。今後も新興感染症への対応において、「オール長岡」の力を存分に発揮してくださるものと確信しております。
また、少子高齢化の進行に伴い小児科・周産期医療の経営的困難、医師偏在や医療従事者確保の課題、医療DX推進に伴う負担増など、医療環境は一層厳しさを増しております。その中にあって毎年10名近くの研修医を受け入れ、熱心にご指導いただいていることは、県内への医師定着に大きく寄与しております。さらに、過疎地医療への積極的な取り組みとして栃尾・山古志地域にご尽力いただき、リモート診療などの先進的試みは、私たち診療所医師を新たな診療形態へと導いてくださるものと期待しております。
今後とも中越地域住民のため、引き続きご指導とご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、長岡中央綜合病院のさらなるご発展と、職員の皆様のご健勝・ご活躍を祈念いたしまして、創立90周年のお祝いの言葉といたします。
長岡中央綜合病院名誉院長
長岡中央綜合病院90周年を記念して
長岡中央綜合病院名誉院長 富所隆
開院90周年、おめでとうございます。
先日80周年記念誌を作成したばかりと思っていたら、もう90周年と聞かされ、時の速さに驚いています。1980年4月~2022年3月まで42年間を振り返り、記憶に残っている病院生活をここに記させて頂きます。
学生時代、県から奨学金をもらっていた身でしたので、初期研修終了後に県立病院で働くように求められていました。ただ、後期研修として3年間の猶予を与えてもらい、県内の消化器内科が盛んな病院を探しておりました。元より臨床が好きで、大学での研究生活を送る才は自分には無いと感じていましたので、当時医師を募集していた長岡中央・長岡日赤・県立新発田を順に見学する予定でした。
1980年1月、初期研修を受けていた県立がんセンターの指導医だった故小越和榮先生に連れられて、研修後の就職先を求めて、初めて長岡中央綜合病院を訪れました。福島江沿いの6階建ての本館・こぢんまりとした委託棟(旧結核病棟)・内視鏡室などを見学し、夜になり、故高橋剛一先生、故杉山一教先生に連れられて、殿町にあったキッチンフロリダでシャリアピンステーキをご馳走になりました。美味しいワインも飲まされて、気がついてみれば、“春からお世話になります”と返事をしておりました。後に“ステーキ1枚で買われた男”などと冷やかされたものです。
さて、当初3年間の予定で赴任したわけですが、働いてみるとこれがやけに楽しい。医局は他科の医師も含め、皆一家言を持つ人物ぞろいで、また、家族のように親しい。釣りにゴルフに麻雀、将棋に囲碁に、もちろん医療もたくさん学ばせて頂きました。看護師さんたちも、夜遅くまで診療に付き合ってくれましたし、その後の慰労会にも嫌な顔もせず参加してくれました。患者さんへの態度などもしっかりと指導してくれました。“お前は要らない”と私を追い出してくれたがんセンターを追い抜くことを目標に、内視鏡検査に励みました。
あっという間に3年が経ちましたが、県立病院に戻る気持ちにはなれず、そのまま当院にお世話になることに決めました。
赴任当時、年間の内視鏡件数は2,000件に満たず、主に症状のある人に行われているような状況で、しかもこの当時は、胃カメラ検査は死ぬほどつらい検査で、めったに受けるものではないと揶揄されているといった有様でした。症状も無いのに内視鏡で検診を受けるなどありえないというのが、地域の人たちの常識でした。これでは、胃がんで亡くなる人を無くすなど到底及ばないと思われました。内視鏡検査をもっと身近な手軽なものに、というのが最初の目標でした。
内視鏡検査の予約制は廃し、朝ごはんを食べていなければ、いつでも受けられるようにしました。内視鏡検診のモデル地区として、前の日に山古志村へ機器を運んで、早朝から地域で内視鏡検診を始めました。村の人たちに内視鏡を受けてもらうために、夜毎、各部落を訪ね、啓発のための講演活動をやったことは、楽しい思い出です。残念ながら、この検診は中越地震で終了することになりましたが、これらの取り組みを経て、内視鏡の件数は年々増加し、赴任した7年後には年間1万件に達するほどの増加を見ました。これは故杉山一教先生の深いご理解と、戸枝一明先生を始めとする同僚の先生方・看護師さん等コ・メディカルの方々の大いなる協力があってのことだと、感謝の念に堪えません。
さて、小生が医師になったころ、胃潰瘍はH. Shayのバランス説により、攻撃因子(酸・ペプシン)と防御因子のバランスが崩れることで発症するという理論で説明されていました。そんなところに表れたのが、後にノーベル賞に輝いたウォーレンとマーシャルが発見したピロリ菌でした。初めは胃炎の原因くらいに考えられていましたが、その後多くの研究が進められ、胃・十二指腸潰瘍、更には胃がんの原因と考えられるようになってしまいました。小生も当初は、にわかに信じられない報告でした。胃潰瘍や胃がんが感染症だった?、後に胃がん検診のあり方を変える事にもなる、地動説から天動説に代わったかのような、大きな発見でした。長岡市医師会や行政の努力で、現在、長岡市では成人および中学2年生に対してピロリ菌の検診が行われています。自らが、胃がんになるリスクを知ることができ、しかも、除菌することでそのリスクを軽減できることが広く知られています。いつの日か、長岡市で胃がんのために命を落とす人が一人もいなくなる日が来ることを、夢見ています。
思い起こせば、1980年4月から、42年間、お世話になりました。楽しくて無我夢中の42年間でした。故亀山先生・故杉山先生・吉川先生と3人の病院長に仕え、その指導の下、病診連携室の立ち上げ、臨床研修指定病院の取得、地域がん診療連携指定病院の取得など、数々のプロジェクトに参加させて頂きました。この間、病院の新築移転・電子カルテの導入、中越地震や水害も経験しました。中越地震の時、多くの職員が自ら病院に駆けつけ、夜を徹して入院患者の安全確保・救急患者の受け入れを行ってくれたことに、心を打たれました。あの数日間に患者を搬送してきた救急車の数は130台を超えました。正に戦場と化した救急室で奮闘してくれた多くの医師・看護師には感謝の言葉しかありません。
2017年4月に小生は第10代目の病院長を拝命いたしました。念願のHCUを開設し、地域医療支援病院の指定を受けたまでは良かったのですが、2019年12月コロナウイルス感染症の拡大のおかげで、残りの任期はコロナとの戦いに明け暮れました。
2022年3月、後を矢尻洋一現病院長に託し、42年間の務めを無事に終えることができました。本当に多くの職員に支えて頂いたことは言うまでもありません。小生がこの病院に赴任した頃、医師数は50名そこそこ、全職員数は400数十名でした。現在、医師は120名を超え、全職員数は1000名を超えています。そしてこの間、医療は極めて複雑化し、患者さん一人にかかる業務量は格段に増加しました。また、人口減少時代に突入したわが国では、少子高齢化を背景に、働き手がどんどん減少してきています。国は、年々膨張する社会保障費用を持続可能なものにするために、過酷な診療報酬制度を我々医療機関に押し付けてきています。今、社会インフラの中で最も大切であるはずの医療が、そしてそれに携わる医療従事者が、「蟹工船」や「女工哀史」に似た状況に陥るかもしれないという危機感を、一体どのくらいの国民が知っているのでしょうか。厚生連の経営状況について、様々な報道で耳にします。そうした現状の中、黙々と診療を続けている職員のみなさんにはもう励ます言葉など無いのですが、長岡中央綜合病院がこれからも、地域の方々の命と健康を守り続けて行ってくれること、そして、地域の人々から愛されて、信頼される病院であり続けることを願っています。さらに、そこで働くすべての職員が、自らの仕事に誇りを持っていてくれることを心から願います。
—
※見出しのクリック/タップで内容が展開表示されます。